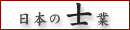14年11月26日
労働契約法の改正
労働契約法は、ほぼ確立された判例を立法化したものである。したがって、主張の場においてはほとんど影響がないものと受け止められた。労働契約法の規定を実体法として主張することができるのであれば民法規定を出すまでもなくなった程度である。
その労働契約法も、第18条の登場で、判例を実体法にするのに止まらず、新たな労働秩序を形成する役割をもつことになった。
≪同一の労働者との間で有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合は、労働者の申込により、無期労働契約に転換できる。≫
労働契約法は取締法規ではなく、あくまでも私法に属する。したがって、罰則は無いが、当事者が争う際に決め手となる。
第19条と強く関連するが、5年も更新しているのならば、労使の信頼関係も十分あるし、有期契約の意味あるの?ということである。法成立にあたっての調査結果がこの18、19条に反映されている。
ただ、いざ法定化されると使用者の不安を誘い、5年になる前に契約を断ち切ろうとする傾向も出た。今、少し落ち着いたかのようで、5年を待たずして無期転換の申し出も受け付ける使用者も増えつつあると聞く。
この「5年」設定は、既に大学の先生において確か10年に読み替えられている。
今回は、
≪一 「特定有期雇用労働者」とは、専門的知識等を有する有期雇用労働者(一年間当たりの賃金の額が一定の額以上である者に限る。)であって、当該専門的知識等を必要とする業務(五年を超える一定の期間内に完了することが予定されているものに限る。以下「特定有期業務」という。)に就くもの(以下「第一種特定有期雇用労働者」という。)及び定年(六十歳以上のものに限る。)に達した後引き続いて当該事業主等に雇用される有期雇用労働者(以下「第二種特定有期雇用労働者」という。)をいう。≫
(議案情報)
(リーフレット)
第一種、第二種ともに手続きが必要となっている。詳細はいずれ出る。
「特定有期業務」の内容も同様。
こう見てみると、労基法14条との関連も押さえる必要がある。
≪第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。≫
労基法の「専門的知識等」業務従事者とダブることが多いと思われるが、労基法では5年までの契約しかできない(当然、更新を除く)とある。しかし、労契法では5年を越えるものに適用するとある。その処理の仕方として、「一定の事業の完了に必要な期間」の契約という合わせ技で解消してある。さらに、今議論し続けられているホワイトカラーエクゼンティブでの観点である、「 (一年間当たりの賃金の額が一定の額以上である者に限る。)」とまで付いてきている。
発明対価の著作権の所属問題など、日本のサラリーマンのなかには想像が難しいほど優秀で貴重な存在もいる。それはそれとして、使用者が5年設定で不安を如実化したのと同じく、労働者は安易な適用に不安をもつ。使用者もサラリーマンも、優秀な者がいれば、普通もおり、もう少しというのも存在するわけである。
高齢者の方はまたの機会とするが、いずれにせよ、労契法は私法である。19条もある。それから、待遇における無期有期の均等化の流れも進みつつある。もとより長期継続的な労使間を志向するならば、何が「得」か「損」かという観点は抑えるべきであるが、その結果が現状なので、法制度の変遷も視野に入れつつ、どうあるべきかを考えていく時期であろう。
その労働契約法も、第18条の登場で、判例を実体法にするのに止まらず、新たな労働秩序を形成する役割をもつことになった。
≪同一の労働者との間で有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合は、労働者の申込により、無期労働契約に転換できる。≫
労働契約法は取締法規ではなく、あくまでも私法に属する。したがって、罰則は無いが、当事者が争う際に決め手となる。
第19条と強く関連するが、5年も更新しているのならば、労使の信頼関係も十分あるし、有期契約の意味あるの?ということである。法成立にあたっての調査結果がこの18、19条に反映されている。
ただ、いざ法定化されると使用者の不安を誘い、5年になる前に契約を断ち切ろうとする傾向も出た。今、少し落ち着いたかのようで、5年を待たずして無期転換の申し出も受け付ける使用者も増えつつあると聞く。
この「5年」設定は、既に大学の先生において確か10年に読み替えられている。
今回は、
≪一 「特定有期雇用労働者」とは、専門的知識等を有する有期雇用労働者(一年間当たりの賃金の額が一定の額以上である者に限る。)であって、当該専門的知識等を必要とする業務(五年を超える一定の期間内に完了することが予定されているものに限る。以下「特定有期業務」という。)に就くもの(以下「第一種特定有期雇用労働者」という。)及び定年(六十歳以上のものに限る。)に達した後引き続いて当該事業主等に雇用される有期雇用労働者(以下「第二種特定有期雇用労働者」という。)をいう。≫
(議案情報)
(リーフレット)
第一種、第二種ともに手続きが必要となっている。詳細はいずれ出る。
「特定有期業務」の内容も同様。
こう見てみると、労基法14条との関連も押さえる必要がある。
≪第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。≫
労基法の「専門的知識等」業務従事者とダブることが多いと思われるが、労基法では5年までの契約しかできない(当然、更新を除く)とある。しかし、労契法では5年を越えるものに適用するとある。その処理の仕方として、「一定の事業の完了に必要な期間」の契約という合わせ技で解消してある。さらに、今議論し続けられているホワイトカラーエクゼンティブでの観点である、「 (一年間当たりの賃金の額が一定の額以上である者に限る。)」とまで付いてきている。
発明対価の著作権の所属問題など、日本のサラリーマンのなかには想像が難しいほど優秀で貴重な存在もいる。それはそれとして、使用者が5年設定で不安を如実化したのと同じく、労働者は安易な適用に不安をもつ。使用者もサラリーマンも、優秀な者がいれば、普通もおり、もう少しというのも存在するわけである。
高齢者の方はまたの機会とするが、いずれにせよ、労契法は私法である。19条もある。それから、待遇における無期有期の均等化の流れも進みつつある。もとより長期継続的な労使間を志向するならば、何が「得」か「損」かという観点は抑えるべきであるが、その結果が現状なので、法制度の変遷も視野に入れつつ、どうあるべきかを考えていく時期であろう。