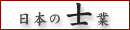15年07月24日
懲戒処分の研究 [古典編]
『5 法律のあいまいさについて』
《法律の勝手な解釈が悪いことである以上、法律のあいまいさについても同じことがいえよう。なぜならそのばあい、法律は解釈される必要を生ずるからだ。法律が大衆のことばで書かれていないばあい、この不都合はまたずっとはなはだしくなる。
法律の条文が大衆にはわからない死語で書かれていて、神がかった御宣託のようにぎょうぎょうしくしまいこまれていたのでは、それは一種の家内問答集でしかなくなってしまう。そして国民はじぶんの財産と自由に関して、とるべき態度をみずから判断することがてきなくなり、このために法律を解釈することのできる少数の者の従属の下におかれなければならなくなる。
だが、反たいに、万人がこの神聖な法典を読むことができ理解することができるなら、もし法典が万人の手におかれたなら、犯罪はそれだけ減少するだろう。なぜなら、犯罪を犯す人間は、その犯罪に対して科される刑をよく知らないか、まったく知らないのだということはうたがいない事実だからである。刑罰が不確実であるということと無知とが、つねに人間の欲望と感情の雄弁を助けるのだ。》
解釈を必要とする法律の文章はその作成を躊躇し、避けるべきである。
なお、ベッカリーアの中心的意図は生きた、自明な法律の文章の要求というよりも、少数者が権力をほしいままにするツールであることの批判にあるが、それはそれとして、現代日本にあって法律の解釈は社会生活において基本的作業となっている。法律というのもここでは避け、就業規則を含める労働法体系といおう。
現在も引き続き、予見可能な労働紛争解決制度が目指されているところである。解雇、未払い賃金、ハラスメント、精神疾患等々色々なトラブルにおいて、ある程度見込まれる決着水準などあるようでもありまた無いようでもあるともいえる。
ところが、そのような制度に入ってトラブルを決着する予見可能性より前に必要なこととして、そのような制度に入る前にしておくべきことというのが周知されていない。それは、法的根拠とする実定法の要件具備のための行動であり、それは相手方への意思表示であったり、証拠確保活動であったりする。こういったことの重要性についてあまり理解されておらず、知識が実体法止まりであったり争った結果である判例知識止まり要するに一般教養に終始する例が多い。ただし、ベッカリーアの意図とは異なり、現代の法律は高度であり、一部の専門家の存在は必要としかいえない。また、社会契約説をベースにできるほどまでは日本社会の国民総体は成熟していないとみる。また戦後の日本社会は上下関係の軸がかなり薄まったものとなったが、「旧日本文化」との訣別という態度は国民相対として表現していない。したがって、まだ「美徳」は遺っており、それが詐欺犯罪にしばしば利用されるという厄介な文化として展開している。
それと、日本の法律は日本の伝統とか民族行動の集大成から出来ているものではなく、明治以降の近代化、外国文明の受け入れによって構成される。所謂「翻訳」文化の問題が生ずるものであり、これまで存在しなかったイメージを新造語で表していくわけであり、もともと近代法と国民は乖離した関係であることは避けられず、その関係の距離を近づけていく作業が法側においても国民においても努力されていっているものである。
最後に、ベッカリーアは「印刷術の発明」に触れている。今で言えば、スマホを含むインターネットの発明である。知りたい用語で検索すれば情報を見つけることができ、またその情報はすべての利用者が発信可能な状態にある。その世界で、利用者は自らの判断で情報の取捨選択を行っている。現在でも、就業規則を社長の引き出しにしまいこんでいるとか労働条件を通知していないとかの例があるが、トラブル要因を「製造」するだけでしかないことは明らかなのである。これも予見可能性の問題である。
《法律の勝手な解釈が悪いことである以上、法律のあいまいさについても同じことがいえよう。なぜならそのばあい、法律は解釈される必要を生ずるからだ。法律が大衆のことばで書かれていないばあい、この不都合はまたずっとはなはだしくなる。
法律の条文が大衆にはわからない死語で書かれていて、神がかった御宣託のようにぎょうぎょうしくしまいこまれていたのでは、それは一種の家内問答集でしかなくなってしまう。そして国民はじぶんの財産と自由に関して、とるべき態度をみずから判断することがてきなくなり、このために法律を解釈することのできる少数の者の従属の下におかれなければならなくなる。
だが、反たいに、万人がこの神聖な法典を読むことができ理解することができるなら、もし法典が万人の手におかれたなら、犯罪はそれだけ減少するだろう。なぜなら、犯罪を犯す人間は、その犯罪に対して科される刑をよく知らないか、まったく知らないのだということはうたがいない事実だからである。刑罰が不確実であるということと無知とが、つねに人間の欲望と感情の雄弁を助けるのだ。》
解釈を必要とする法律の文章はその作成を躊躇し、避けるべきである。
なお、ベッカリーアの中心的意図は生きた、自明な法律の文章の要求というよりも、少数者が権力をほしいままにするツールであることの批判にあるが、それはそれとして、現代日本にあって法律の解釈は社会生活において基本的作業となっている。法律というのもここでは避け、就業規則を含める労働法体系といおう。
現在も引き続き、予見可能な労働紛争解決制度が目指されているところである。解雇、未払い賃金、ハラスメント、精神疾患等々色々なトラブルにおいて、ある程度見込まれる決着水準などあるようでもありまた無いようでもあるともいえる。
ところが、そのような制度に入ってトラブルを決着する予見可能性より前に必要なこととして、そのような制度に入る前にしておくべきことというのが周知されていない。それは、法的根拠とする実定法の要件具備のための行動であり、それは相手方への意思表示であったり、証拠確保活動であったりする。こういったことの重要性についてあまり理解されておらず、知識が実体法止まりであったり争った結果である判例知識止まり要するに一般教養に終始する例が多い。ただし、ベッカリーアの意図とは異なり、現代の法律は高度であり、一部の専門家の存在は必要としかいえない。また、社会契約説をベースにできるほどまでは日本社会の国民総体は成熟していないとみる。また戦後の日本社会は上下関係の軸がかなり薄まったものとなったが、「旧日本文化」との訣別という態度は国民相対として表現していない。したがって、まだ「美徳」は遺っており、それが詐欺犯罪にしばしば利用されるという厄介な文化として展開している。
それと、日本の法律は日本の伝統とか民族行動の集大成から出来ているものではなく、明治以降の近代化、外国文明の受け入れによって構成される。所謂「翻訳」文化の問題が生ずるものであり、これまで存在しなかったイメージを新造語で表していくわけであり、もともと近代法と国民は乖離した関係であることは避けられず、その関係の距離を近づけていく作業が法側においても国民においても努力されていっているものである。
最後に、ベッカリーアは「印刷術の発明」に触れている。今で言えば、スマホを含むインターネットの発明である。知りたい用語で検索すれば情報を見つけることができ、またその情報はすべての利用者が発信可能な状態にある。その世界で、利用者は自らの判断で情報の取捨選択を行っている。現在でも、就業規則を社長の引き出しにしまいこんでいるとか労働条件を通知していないとかの例があるが、トラブル要因を「製造」するだけでしかないことは明らかなのである。これも予見可能性の問題である。