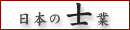07年06月23日
在籍出向者に対する復帰命令に労働者の同意が必要か
事案は、「Y1会社と訴外A会社は、両者の核燃料部門をそれぞれ分離・併合し、Y2会社を設立した。Y1会社はこの新会社設立に伴い、原子力部門の物的施設をY2会社に譲渡あるいは賃貸し、同部門の全労働者151名を自社に在籍したまま休職の形でY2会社に出向させた。なお、A会社からY2会社への出向者は105名であった。 Y2会社としては、当座Y1・A両社から拠出された人的・物的施設をそのまま利用し、将来これを統合あるいは合理化する予定であり、これに伴い両社からの出向者をほぼ同数になるよう人員調整することを考えていた。また、発足後間もない時期には適材適所の人員配置をする必要もあり、そのために一部の出向者を元の会社に復帰させることも十分に予想された。 一方、Y1会社でも、Y2会社が独立の企業としての基盤を備えるまでは、Y2会社での人員整理や人員配置等の都合から出向者を自社に復帰させる場合があることを予定していた。また、Y1会社から出向を命じられた者も、出向の際の労働組合とY1との協議を通じてこのことを了解していた。 Xは、Y1会社に雇用され勤務していたが、Y2会社設立に伴い、Y2会社に出向を命じられた。XはY1会社入社以来病気その他の理由で無断欠勤、欠勤、遅刻が多く、このことはY2会社出向後も変わりなかった。そのため、Y1会社は、XをY2会社に出向させておくのはA会社に対する信義上妥当でないと考え、また、自社で生じた欠員を補充する必要から、Xに自社への復帰を命じた。しかし、Xはこれをかたくなに拒否したため、Y1会社はXを懲戒解雇した。 Xは、Y1・Y2両社に対し、雇用契約上の地位確認等を請求したもの」である。
これは、古河電気工業・原子燃料工業事件であるが、最高裁(最判S60,4,5)は、Xの上告を棄却して、次のように判示した。
労働者が使用者(出向元)との間の雇用契約に基づく従業員たる身分を保有しながら第三者(出向先)の指揮監督の下に労務を提供するという形態の出向(いわゆる在籍出向)が命じられた場合において、「その後出向元が、出向先の同意を得た上、右出向関係を解消して労働者に対し復帰を命ずるについては、特段の事情のない限り、当該労働者の同意を得る必要はない」ものと解すべきである。けだし、右の場合における復帰命令は、指揮監督の主体を出向先から出向元へ変更するものではあるが、労働者が出向元の指揮監督の下に労務を提供するということは、もともと出向元との当初の雇用契約において合意されていた事柄であって、在籍出向においては、出向元へ復帰させないことを予定して出向が命じられ、労働者がこれに同意した結果、将来労働者が再び出向元の指揮監督の下に労務を提供することはない旨の合意が成立したものとみられるなどの特段の事由がない限り、労働者が出向元の指揮監督の下に労務を提供するという当初の雇用契約における合意自体には何らの変容を及ぼさず、右合意の存在を前提とした上で、一時的に出向先の指揮監督の下に労務を提供する関係となっていたにすぎないものというべきであるからである。
要するに、在籍出向の形態が問題になるのであり、出向元への復帰を予定していないような特段の事由がない限り、復帰命令に労働者の同意は必要ないということです。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。
これは、古河電気工業・原子燃料工業事件であるが、最高裁(最判S60,4,5)は、Xの上告を棄却して、次のように判示した。
労働者が使用者(出向元)との間の雇用契約に基づく従業員たる身分を保有しながら第三者(出向先)の指揮監督の下に労務を提供するという形態の出向(いわゆる在籍出向)が命じられた場合において、「その後出向元が、出向先の同意を得た上、右出向関係を解消して労働者に対し復帰を命ずるについては、特段の事情のない限り、当該労働者の同意を得る必要はない」ものと解すべきである。けだし、右の場合における復帰命令は、指揮監督の主体を出向先から出向元へ変更するものではあるが、労働者が出向元の指揮監督の下に労務を提供するということは、もともと出向元との当初の雇用契約において合意されていた事柄であって、在籍出向においては、出向元へ復帰させないことを予定して出向が命じられ、労働者がこれに同意した結果、将来労働者が再び出向元の指揮監督の下に労務を提供することはない旨の合意が成立したものとみられるなどの特段の事由がない限り、労働者が出向元の指揮監督の下に労務を提供するという当初の雇用契約における合意自体には何らの変容を及ぼさず、右合意の存在を前提とした上で、一時的に出向先の指揮監督の下に労務を提供する関係となっていたにすぎないものというべきであるからである。
要するに、在籍出向の形態が問題になるのであり、出向元への復帰を予定していないような特段の事由がない限り、復帰命令に労働者の同意は必要ないということです。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。
07年06月22日
個別労働紛争解決制度2
前回の続きです。
前回述べた労働基準監督署・労働局等によるいわば行政型ADRや司法型ADR(調停)の制度は、解決案に対し強制力がないため、当事者同士での任意の話合いが成立しなければ、紛争の解決に結びつかないという指摘がなされていました。
一方、個別労働紛争の解決には、雇用・労使関係の制度や慣行等の専門的知見が要求されるだけでなく、労働者の生活基盤に直接影響を及ぼすため迅速な解決が要請されるのに、裁判をするには時間がかかりすぎることも問題視されていました。
そこで、個別労働関係事件についての裁判所による簡易迅速な紛争解決手続を定めた「労働審判法」が、平成16年4月に成立し、平成18年4月1日から施行されています。
1 目的(1条参照)
個別労働関係民事紛争について、裁判官と労働関係に関する専門的な知識経験を有する者が、事件を審理し、調停による解決の見込みがある場合には、これを試み、その解決に至らない場合には、権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判を定める手続を設け、あわせて、これと訴訟手続とを連携させることにより、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする。
2 対象事件
「労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争」(1条) 労働者と事業主との間の紛争ですから、例えば、労働者同士のセクハラ事案は対象にならないのではないかと思われます。ただ、その場合でも、事業主の管理責任(民法715条の使用者責任)を問う場合であれば、可能かと思われます。
3 管轄
(1)相手方の住所、営業所等の所在地を管轄する地方裁判所、(2)労働者が現に就業しあるいは最後に就業した当該事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所、(3)当事者が合意で定める地方裁判所、であり、いずれも地方裁判所の管轄となっています。
4 労働審判委員会の構成
裁判官たる労働審判官1人と労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2人で構成される。
5 迅速な手続
特別な事情がある場合を除いて、3回以内の期日で審理を終結しなければなりません。したがって、訴訟では1年以上かかるのはザラですが、この手続では3,4ヶ月で終結すると思われます。そのためには、当事者の迅速な争点及び証拠の整理が要求されるでしょう。
6 労働審判の効力
調停が成立するか労働審判に適法な異議の申立がないときには、裁判上の和解と同一の効力を有します。また、労働審判に対して、告知を受けた日から2週間以内に異議の申立があれば、労働審判はその効力を失います。この場合には、労働審判手続申立の時に当該地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます。このことは、異議を申立てるということは訴訟を覚悟でしなければならないということを意味し、労働審判の実効性が確保されるものと思われます。 また、労働審判においては、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払等の給付を命じて、個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができる(20条)ため、例えば、解雇が無効であっても、労働者としては職場復帰を望んでいない場合には、金銭補償で解決することも考えられます。
7 労働審判によらない労働審判事件の終了
労働審判委員会は、事案の性質に照らし、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないとみとめるときには、労働審判事件を終了させることができます。この場合にも、6と同様に訴えの擬制がなされます。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。
前回述べた労働基準監督署・労働局等によるいわば行政型ADRや司法型ADR(調停)の制度は、解決案に対し強制力がないため、当事者同士での任意の話合いが成立しなければ、紛争の解決に結びつかないという指摘がなされていました。
一方、個別労働紛争の解決には、雇用・労使関係の制度や慣行等の専門的知見が要求されるだけでなく、労働者の生活基盤に直接影響を及ぼすため迅速な解決が要請されるのに、裁判をするには時間がかかりすぎることも問題視されていました。
そこで、個別労働関係事件についての裁判所による簡易迅速な紛争解決手続を定めた「労働審判法」が、平成16年4月に成立し、平成18年4月1日から施行されています。
1 目的(1条参照)
個別労働関係民事紛争について、裁判官と労働関係に関する専門的な知識経験を有する者が、事件を審理し、調停による解決の見込みがある場合には、これを試み、その解決に至らない場合には、権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判を定める手続を設け、あわせて、これと訴訟手続とを連携させることにより、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする。
2 対象事件
「労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争」(1条) 労働者と事業主との間の紛争ですから、例えば、労働者同士のセクハラ事案は対象にならないのではないかと思われます。ただ、その場合でも、事業主の管理責任(民法715条の使用者責任)を問う場合であれば、可能かと思われます。
3 管轄
(1)相手方の住所、営業所等の所在地を管轄する地方裁判所、(2)労働者が現に就業しあるいは最後に就業した当該事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所、(3)当事者が合意で定める地方裁判所、であり、いずれも地方裁判所の管轄となっています。
4 労働審判委員会の構成
裁判官たる労働審判官1人と労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2人で構成される。
5 迅速な手続
特別な事情がある場合を除いて、3回以内の期日で審理を終結しなければなりません。したがって、訴訟では1年以上かかるのはザラですが、この手続では3,4ヶ月で終結すると思われます。そのためには、当事者の迅速な争点及び証拠の整理が要求されるでしょう。
6 労働審判の効力
調停が成立するか労働審判に適法な異議の申立がないときには、裁判上の和解と同一の効力を有します。また、労働審判に対して、告知を受けた日から2週間以内に異議の申立があれば、労働審判はその効力を失います。この場合には、労働審判手続申立の時に当該地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます。このことは、異議を申立てるということは訴訟を覚悟でしなければならないということを意味し、労働審判の実効性が確保されるものと思われます。 また、労働審判においては、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払等の給付を命じて、個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができる(20条)ため、例えば、解雇が無効であっても、労働者としては職場復帰を望んでいない場合には、金銭補償で解決することも考えられます。
7 労働審判によらない労働審判事件の終了
労働審判委員会は、事案の性質に照らし、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないとみとめるときには、労働審判事件を終了させることができます。この場合にも、6と同様に訴えの擬制がなされます。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。
07年06月21日
個別労働紛争解決制度1
最近は、統計上景気が回復したとされていますが、バブル経済崩壊後は、リストラ等による不当解雇や賃金未払いなど、労働者と使用者との間の個別労働紛争は、相変わらず増えています。
労働局などに寄せられる相談で最も多いのが、やはり解雇事案であり、次が労働時間、賃金引下げなどの労働条件の低下の事案、これにいじめ・嫌がらせの事案が続きます。
このように労働者と事業主との間に個別労働紛争が生じた場合、顧問の弁護士や社会保険労務士などによって、「企業内において自主的解決」を図るのがベストである。このような法律の専門家が企業内に存在する場合には、紛争を未然に防ぐため、就業規則の充実が図られているものと思われます。しかし、それでも、個別労働紛争は起きるものです。
企業内に法律の専門家がいない場合には、法律知識等の不足により紛争の自主的解決が困難となる場合が多くなります。そこで、都道府県労働局企画室または労働基準監督署に設けられている「総合労働相談コーナー」では、自主解決のための情報提供や相談・助言を行っています。
また、都道府県労働局長は、個別労働関係紛争に関し当事者の双方または一方から紛争解決について援助を求められた場合には、企業内自主解決ができるよう、当事者に対し、必要な助言又は指導を行います。もっとも、男女雇用機会均等法にかかる事案については、勧告も行います。
さらに、都道府県労働局長は、紛争当事者の双方または一方から「あっせん」の申請があった場合に、紛争解決のために必要があると認めるときには、都道府県労働局にある「紛争調整委員会」にあっせんを行わせます。あっせんは、当事者双方の主張の要点を確かめ、実情に即したあっせん案を作成・提示しますが、当事者の一方から不参加の意思表示がなされると、あっせん打ち切りとなります。また、あっせん案は、必ず受諾しなければならないものではないのです。このように強制力がないのです。
そこで、労働審判制度の登場となりますが、次回に譲ります。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。
労働局などに寄せられる相談で最も多いのが、やはり解雇事案であり、次が労働時間、賃金引下げなどの労働条件の低下の事案、これにいじめ・嫌がらせの事案が続きます。
このように労働者と事業主との間に個別労働紛争が生じた場合、顧問の弁護士や社会保険労務士などによって、「企業内において自主的解決」を図るのがベストである。このような法律の専門家が企業内に存在する場合には、紛争を未然に防ぐため、就業規則の充実が図られているものと思われます。しかし、それでも、個別労働紛争は起きるものです。
企業内に法律の専門家がいない場合には、法律知識等の不足により紛争の自主的解決が困難となる場合が多くなります。そこで、都道府県労働局企画室または労働基準監督署に設けられている「総合労働相談コーナー」では、自主解決のための情報提供や相談・助言を行っています。
また、都道府県労働局長は、個別労働関係紛争に関し当事者の双方または一方から紛争解決について援助を求められた場合には、企業内自主解決ができるよう、当事者に対し、必要な助言又は指導を行います。もっとも、男女雇用機会均等法にかかる事案については、勧告も行います。
さらに、都道府県労働局長は、紛争当事者の双方または一方から「あっせん」の申請があった場合に、紛争解決のために必要があると認めるときには、都道府県労働局にある「紛争調整委員会」にあっせんを行わせます。あっせんは、当事者双方の主張の要点を確かめ、実情に即したあっせん案を作成・提示しますが、当事者の一方から不参加の意思表示がなされると、あっせん打ち切りとなります。また、あっせん案は、必ず受諾しなければならないものではないのです。このように強制力がないのです。
そこで、労働審判制度の登場となりますが、次回に譲ります。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。
07年06月20日
組合併存下における不当労働行為
事案は、「Y会社には、Y労働組合(約120名、以下労組)とY分会(20数名、以下分会)の2組合が併存していた。年末一時金に関して、Yと労組・分会とは一回目は妥結に至らなかった。労組との2回目の団交において、Yは前回の約束に基づいて「生産性向上に協力すること」という前提条件を付けた上で支給額上積み回答を示し、労組側はこれを受諾し、労働協約を締結し、Yは労組の組合員及び非組合員に対し、年末一時金を支給した。 他方、分会との2回目団交の席上、Yは、「生産性向上に協力する」という前提条件を付けた上、労組に提示したものと同一内容の回答を行った。分会は、「生産性向上に協力する」という条件は、人員削減を伴う合理化、労働組合潰しなどにつながると考え、その意味・内容を質問したが、具体的な説明は得られなかった。その後の団交においても、Yは、右前提条件と一時金回答とは一体のものであると主張した。分会は両者を切り離すべきことを主張して対立し、交渉は妥結せず、分会員に一時金は支給されなかった。 そこで、分会は、不当労働行為を理由に都労委に救済を申し立てた。都労委は、「生産性向上に協力する」という表現が極めて抽象的でその真意が測りかねる点があり、また、一時金につき妥結に至らなかったのはYが前提条件を一時金回答と不可分のものとした態度に基因するから、分会員に一時金が支給されない結果をもたらしたことは分会員に対する不利益取扱いであり、同時に分会の弱体化を企図したものであるとして、一時金の支給を命じた。Yはこれを不服とし、都労委(X)を被告として救済命令の取消訴訟を提起したもの」である。
これは、日本メール・オーダー事件であるが、最高裁(最判S59,5,29)は次のように判示して、Xの命令を取消した原審を破棄した。
1 その前提条件は抽象的で具体性を欠くことから、一時金の積上げを実施する前提として提案するに当たって、Yは分会の理解を得るために十分な説明が必要であるのに協力義務の履行として具体的になすべきことの説明をしていない。にもかかわらず、右一時金の積上げ回答に本件前提条件を付することは合理性のあるものとはいい難く、したがって、分会がこれに反対したことも無理からぬものというべきである。
2 本件の前提条件は、労組の側から上積み要求実現のための交換条件として持ち出されたものとみるべきであるから、その内容上、労組とは組織とその方針を異にしていた分会として当然に受け入れられるものでないことは、Yとしても予測しえたはずである。
3 分会が少数派組合であることからすると、分会所属の組合員が一時金の支給を受けられないことになれば、同組合員らの間に動揺を来し、分会の組織力に影響を及ぼしその弱体化を来すと予測できる。Yが右のような状況の下において本件前提条件にあえて固執したということは、かかる状況を利して分会及びその所属組合員をして、右のような結果を甘受するのやむなきに至らしめようとの意図を有していたとの評価を受けてもやむをえない。
4 Yの右行為は、それを全体としてみた場合には、分会に所属している組合員を、そのことの故に差別し、これによって、分会の内部に動揺を生じさせ、ひいては分会の組織を弱体化させようとの意図の下に行われたものとして、労働組合法7条1号及び3号の不当労働行為を構成するものというべきである。
使用者が、併存する複数の組合に同一条件を提示し、一方の組合はこれを受諾して協約を締結したが、他方の組合はこれを拒否したため、結果として両組合間に差別状態が生じた場合に、常に不当労働行為になると判示しているわけではないことに注意を要します。それは、団体交渉における取引の自由、労働組合の選択の自由があるからです。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。
これは、日本メール・オーダー事件であるが、最高裁(最判S59,5,29)は次のように判示して、Xの命令を取消した原審を破棄した。
1 その前提条件は抽象的で具体性を欠くことから、一時金の積上げを実施する前提として提案するに当たって、Yは分会の理解を得るために十分な説明が必要であるのに協力義務の履行として具体的になすべきことの説明をしていない。にもかかわらず、右一時金の積上げ回答に本件前提条件を付することは合理性のあるものとはいい難く、したがって、分会がこれに反対したことも無理からぬものというべきである。
2 本件の前提条件は、労組の側から上積み要求実現のための交換条件として持ち出されたものとみるべきであるから、その内容上、労組とは組織とその方針を異にしていた分会として当然に受け入れられるものでないことは、Yとしても予測しえたはずである。
3 分会が少数派組合であることからすると、分会所属の組合員が一時金の支給を受けられないことになれば、同組合員らの間に動揺を来し、分会の組織力に影響を及ぼしその弱体化を来すと予測できる。Yが右のような状況の下において本件前提条件にあえて固執したということは、かかる状況を利して分会及びその所属組合員をして、右のような結果を甘受するのやむなきに至らしめようとの意図を有していたとの評価を受けてもやむをえない。
4 Yの右行為は、それを全体としてみた場合には、分会に所属している組合員を、そのことの故に差別し、これによって、分会の内部に動揺を生じさせ、ひいては分会の組織を弱体化させようとの意図の下に行われたものとして、労働組合法7条1号及び3号の不当労働行為を構成するものというべきである。
使用者が、併存する複数の組合に同一条件を提示し、一方の組合はこれを受諾して協約を締結したが、他方の組合はこれを拒否したため、結果として両組合間に差別状態が生じた場合に、常に不当労働行為になると判示しているわけではないことに注意を要します。それは、団体交渉における取引の自由、労働組合の選択の自由があるからです。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。
07年06月19日
就業時間外職場外ビラ配布行為と懲戒処分の可否
事案は、「Xは、Y会社に技術者として勤務する者で、事件当時、工業学校卒業後に入社して以来14年近くが経っていた。この間、Xは、Y会社の従業員で組織する訴外A組合において様々な役職に就いたことがあったが、事件発生時には役職になく、組合主流派を労使協調路線と批判する立場をとっていた。 そのXが、他の数名と手分けして、昭和43年大晦日から翌44年元旦にかけての深夜に、Y会社の従業員社宅へビラ約350枚を配布した。ビラは、発行者の表示がなく、その内容は、Y会社に関して、(1)70年革命説を唱え反共宣伝をしている、(2)差別・村八分をはじめおよそ常識と法に反して労働者を締め上げている、(3)他の会社より低い給料・少ない賞与を押し付けている、(4)種々の既得権を取り上げてきた、などの事実を指摘し、(5)日本有数の大会社の正体がどんなにきたないものか、どんなにひどいものかを体で知ったと論評し、(6)ことしこそ以前にもましてみにくく、きたないやり方をするだろうと予想し、また、(7)会社の悪巧みや策動を・・・・・・公然と暴露すべきで、会社はそのことを最も恐れているとか、(8)会社は自分で自分の首をしめており、天に向かって唾するもの、還りて己が面を汚すとはY会社のことだとする記載があった。 Y会社は、こうしたビラ配布が就業規則の懲戒事由である「その他特に不都合な行為があったとき」に該当するとして、Xを最も軽い懲戒である譴責処分に付した。これに対して、Xは、譴責処分の無効確認などを求めたもの」である。
ビラの内容が問題となったので、少し長くなりましたが、これは、関西電力事件であり、最高裁(最判S58,9,8)は次のように判示した。
1 労働者は、労働契約を締結して雇用されることによって、使用者に対して労務提供義務を負うとともに、「企業秩序を遵守すべき義務を負い」、使用者は、広く企業秩序を維持し、もって企業の円滑な運営を図るために、その雇用する労働者の企業秩序違反行為を理由として、当該労働者に対し、一種の制裁罰である懲戒を課すことができるものであるところ、「右企業秩序は、通常、労働者の職場内又は職務遂行に関係のある行為を規制することにより維持しうるのであるが、職場外された職務遂行に関係のない労働者の行為であっても、企業の円滑な運営に支障を来すおそれがあるなど企業秩序に関係を有するものもあるのであるから、使用者は、企業秩序の維持確保のために、そのような行為をも規制の対象とし、これを理由として労働者に懲戒を課することも許される」のであり、右のような場合を除き、労働者は、その職場外における職務遂行に関係のない行為について、使用者による規制を受けるべきいわれはないものと解するのが相当である。
2 これを本件についてみるに、右ビラの内容が大部分事実に基づかず、又は事実を誇張歪曲してY会社を非難攻撃し、全体としてこれを中傷誹謗するものであり、右ビラの配布により労働者の会社に対する不信感を醸成して企業秩序を乱し、又はそのおそれがあったものとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、是認することができないではなく、その過程に所論の違法があるものとすることはできない。・・・・・Xによる本件ビラの配布は、就業時間外に職場外であるY会社の従業員社宅において職務遂行に関係なく行われたものではあるが、前記就業規則所定の懲戒事由にあたると解することができ、これを理由としてXに対して懲戒として譴責を課したことは、懲戒権者に認められる裁量権の範囲を超えるものとは認められない。
職場外の職務遂行と関係のない行為に対する懲戒は、労働者の企業秩序遵守義務、使用者の企業秩序維持確保を根拠としていることに注意する必要があります。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。
ページ移動
前へ
1,2, ... ,30,31,32, ... ,44,45
次へ
Page 31 of 45
ビラの内容が問題となったので、少し長くなりましたが、これは、関西電力事件であり、最高裁(最判S58,9,8)は次のように判示した。
1 労働者は、労働契約を締結して雇用されることによって、使用者に対して労務提供義務を負うとともに、「企業秩序を遵守すべき義務を負い」、使用者は、広く企業秩序を維持し、もって企業の円滑な運営を図るために、その雇用する労働者の企業秩序違反行為を理由として、当該労働者に対し、一種の制裁罰である懲戒を課すことができるものであるところ、「右企業秩序は、通常、労働者の職場内又は職務遂行に関係のある行為を規制することにより維持しうるのであるが、職場外された職務遂行に関係のない労働者の行為であっても、企業の円滑な運営に支障を来すおそれがあるなど企業秩序に関係を有するものもあるのであるから、使用者は、企業秩序の維持確保のために、そのような行為をも規制の対象とし、これを理由として労働者に懲戒を課することも許される」のであり、右のような場合を除き、労働者は、その職場外における職務遂行に関係のない行為について、使用者による規制を受けるべきいわれはないものと解するのが相当である。
2 これを本件についてみるに、右ビラの内容が大部分事実に基づかず、又は事実を誇張歪曲してY会社を非難攻撃し、全体としてこれを中傷誹謗するものであり、右ビラの配布により労働者の会社に対する不信感を醸成して企業秩序を乱し、又はそのおそれがあったものとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、是認することができないではなく、その過程に所論の違法があるものとすることはできない。・・・・・Xによる本件ビラの配布は、就業時間外に職場外であるY会社の従業員社宅において職務遂行に関係なく行われたものではあるが、前記就業規則所定の懲戒事由にあたると解することができ、これを理由としてXに対して懲戒として譴責を課したことは、懲戒権者に認められる裁量権の範囲を超えるものとは認められない。
職場外の職務遂行と関係のない行為に対する懲戒は、労働者の企業秩序遵守義務、使用者の企業秩序維持確保を根拠としていることに注意する必要があります。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。