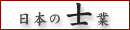07年06月25日
生理休暇の取得と精皆勤手当
事案は、「Xら4名は、Y会社における女子従業員で、Yの従業員組合Aの組合員でもあるが、昭和46年11月に生理休暇を2日取得したところ、精皆勤手当の算定に際して欠勤扱いとされ同月分の同手当が1000円しか支給されなかったため、本来5000円の手当受給権があるはずとしてその差額4000円の支給を請求したものである。 なお、YとA組合との間には、昭和46年3月以降「出勤不足日数のない場合5000円、出勤不足日数1日の場合3000円、同2日の場合1000円、同3日以上の場合なし」とする旨の同年11月の口頭による合意があった。また、原審の認定によれば、生理休暇取得者には、不就業手当としてXらには1日1460円から1510円の間の基本給相当額が支給されていたが、右46年合意に際し、生理休暇取得日数を出勤不足日数に算入する旨の口頭の約束があった。」というものである。
これは、エヌ・ビー・シー工業事件であるが、最高裁(最判S60、7,16)は、次のように判示して、Xらの上告を棄却した。
1 労基法67条(現68条)は所定の要件を備えた女子労働者が生理休暇を請求したときは、その者を就業させてはならない旨規定しているが、年次有給休暇については同法39条4項(現6項)においてその期間所定の賃金等を支払うべきことが定められているのに対し、生理休暇についてはそのような規定が置かれていないことを考慮すると、「その趣旨は、当該労働者が生理休暇の請求をすることによりその間の就労義務を免れ、その労務の不提供につき労働契約上債務不履行の責めを負うことのないことを定めたにとどまり、生理休暇が有給であることまでをも保障したものではない」と、解するのが相当である。したがって、「生理休暇を取得した労働者は、その間就労していないのであるから、労使間に特段の合意がない限り、その不就労期間に対応する賃金請求権を有しない。」
2 また、労基法12条3項及び39条5項(現7項)によると、生理休暇は、同法65条所定の産前産後の休業と異なり、平均賃金の計算や年次有給休暇の基礎となる出勤日の算定について特別の扱いを受けるものとはされておらず、、これらの規定に徴すると、「同法67条(現68条)は、使用者に対し生理休暇取得日を出勤扱いにすることまでも義務づけるものではなく、これを出勤扱いにするか欠勤扱いにするかは原則として労使間の合意に委ねられている。」
3 ところで、生理休暇の取得が欠勤扱いとされることによって何らかの形で経済的利益を得られない結果となるような措置ないし制度を設けられたときには、生理休暇の取得が事実上抑制される場合も起こりうるが、労基法67条(現68条)の上述の趣旨に照らすと、「かかる措置ないし制度は、その趣旨、目的、労働者が失う経済的利益の程度、生理休暇の取得に対する事実上の抑止力の強弱等諸般の事情を総合して、生理休暇の取得を著しく困難とし同法が女子労働者の保護を目的として生理休暇について特に規定を設けた趣旨を失わせるものと認められるのでない限り、同条違反とはいえない。」
生理休暇の有給性の問題と精皆勤手当の問題とは区別しなければなりません。最高裁が、生理休暇制度保障にいわば消極的な立場をとったのは、生理休暇制度の濫用防止を睨んでのことと思われます。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。
これは、エヌ・ビー・シー工業事件であるが、最高裁(最判S60、7,16)は、次のように判示して、Xらの上告を棄却した。
1 労基法67条(現68条)は所定の要件を備えた女子労働者が生理休暇を請求したときは、その者を就業させてはならない旨規定しているが、年次有給休暇については同法39条4項(現6項)においてその期間所定の賃金等を支払うべきことが定められているのに対し、生理休暇についてはそのような規定が置かれていないことを考慮すると、「その趣旨は、当該労働者が生理休暇の請求をすることによりその間の就労義務を免れ、その労務の不提供につき労働契約上債務不履行の責めを負うことのないことを定めたにとどまり、生理休暇が有給であることまでをも保障したものではない」と、解するのが相当である。したがって、「生理休暇を取得した労働者は、その間就労していないのであるから、労使間に特段の合意がない限り、その不就労期間に対応する賃金請求権を有しない。」
2 また、労基法12条3項及び39条5項(現7項)によると、生理休暇は、同法65条所定の産前産後の休業と異なり、平均賃金の計算や年次有給休暇の基礎となる出勤日の算定について特別の扱いを受けるものとはされておらず、、これらの規定に徴すると、「同法67条(現68条)は、使用者に対し生理休暇取得日を出勤扱いにすることまでも義務づけるものではなく、これを出勤扱いにするか欠勤扱いにするかは原則として労使間の合意に委ねられている。」
3 ところで、生理休暇の取得が欠勤扱いとされることによって何らかの形で経済的利益を得られない結果となるような措置ないし制度を設けられたときには、生理休暇の取得が事実上抑制される場合も起こりうるが、労基法67条(現68条)の上述の趣旨に照らすと、「かかる措置ないし制度は、その趣旨、目的、労働者が失う経済的利益の程度、生理休暇の取得に対する事実上の抑止力の強弱等諸般の事情を総合して、生理休暇の取得を著しく困難とし同法が女子労働者の保護を目的として生理休暇について特に規定を設けた趣旨を失わせるものと認められるのでない限り、同条違反とはいえない。」
生理休暇の有給性の問題と精皆勤手当の問題とは区別しなければなりません。最高裁が、生理休暇制度保障にいわば消極的な立場をとったのは、生理休暇制度の濫用防止を睨んでのことと思われます。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。
07年06月25日15:14:55 |
Category: 労働関係
Posted by: marutahoumuj