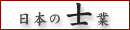12年09月05日
従業員の「出るところへ出る」とは、どういうことなのか H24.9月号
従業員の「出るところへ出る」とは、どういうことなのか
●社内で解決できない労使紛争が、その後どういう経緯を辿るのかイメージしておこう~
労使紛争が増加しています。よく、クライアント様にそのようなお話をしても自信満々に、「ウチは大丈夫」と安心しておられる経営者もあります。が、多くの事例を拝見する立場から申し上げると、その理屈は「ウチの子に限って!」と言う親の心理に似ています。現実はどこで起こってもおかしくないのです。
労使紛争を類型化すると、「解雇・退職勧奨など離職に関すること」、「労働条件の引き下げに関すること」、「賃金(残業代)の未払いに関すること」が多くを占めるのですが、最近ではここに「いじめ・嫌がらせ(いわゆるパワーハラスメント)」が増加傾向にあります。
こういったことが起こったとき、当事者同士で解決できなければ、紛争として表面化します。表面化とは簡単に言えば、従業員が「出るところに出る」ということです。揉めても従業員が出るところに出なければ、表面化せず、消えてゆくだけです。では、その「出るところ」とは、どのようなところがあるのでしょうか。その見通しを持っておくことは、紛争を拡大させないためにも重要なことです。
主に従業員が「出るところ」とは以下のコースがあるのです。
1.労働基準監督署への申告コース
2.あっせん申請コース
3.弁護士(裁判所)委託コース
4.合同労組加入コース
5.親族(例外)コース
1.労働基準監督署への申告コース
労働基準法104条では違反事実を労働者が労基署へ申告する権利を認めており、費用も懸からず、一番多いコースです。対応する労働基準監督官にもよるのですが、会社としても妥当な解決策を模索し易いコースと言えるでしょう。調査を拒否することはできません。
よく労基署は労働問題全てを管轄しているように勘違いされているケースがありますが、監督官が取り扱う法律は労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法など限られた特別法のみで、トラブルの多い同じ労働問題でも、社会保険や労災に関すること、育児介護やセクハラに関すること、人材派遣や偽装請負に関することなどは対象外です(これらは別の所轄があります)。
また解雇や未払い賃金に関しても、法違反として断定できないこと、例えば解雇紛争で解雇の有効性が争点の場合や、未払い賃金紛争で労働時間の解釈が争点などの場合、これらは民事紛争となり、行政機関である労基署の管轄外となります。
これらに関する申告の場合は、原則的には他の管轄がある場合はその窓口を紹介され、民事紛争に該当することは次に述べる「あっせん」などの他の解決機関を紹介されることとなります。労基法などに違反事実があると断定されたときは、「是正勧告書」なる行政指導の文書が手交され、一定期日までにその違反状態を自ら是正して報告するという流れで、通常このコースは終了することとなります。
先ほど妥当な解決が図りやすいと申しましたが、デメリット?としては、行政指導という性格から、場合により画一的に調査され、直接紛争とは関係のない他の事案(安全衛生管理状態など)や他の従業員のことについても、波及する可能性があることが挙げられます。また監督官は司法警察権を有しているため、行政指導に従わない場合は、刑事処分される可能性もあります。
2.あっせん申請コース
これは労使紛争であっても、前述のように行政指導に馴染まない民事紛争に関することや、裁判所へ行って争う意思まではないが、何らかの行動を起こしたいというような場合に、選択されます。公的に解決を援助するあっせん機関から「あっせん開始通知書」なるものが送られて来るものです。大阪の場合は、大阪労働局・大阪府労働委員会・大阪府社会保険労務士会にその機関があります。弁護士に頼らなくとも本人申請でできるので、よく利用される傾向にあります。
このあっせんは、参加に強制力はなく、受諾するかどうかは自由です。受諾しなければ即「打ち切り」となります。また開始されても、和解に至らなければ同様に「打ち切り」となります。その後労働者が諦めず、更に次の解決策を選択する可能性もあるので、紛争内容が言いがかりに近いものでなく、互譲の精神で会社にも解決の意思があるなら、受諾して和解することをお勧めします。場合によっては会社から先に「あっせん」をかけ、第三者の下で、解決を図ることもできます。
一般論として、あっせんは非対面方式で行い、法律を杓子定規に適用するのではなく、当事者の合意を最優先しますから、柔軟な解決方法が可能です。通常1日程度の期日で終了し、和解できれば民事上有効な和解契約書を交わします。裁判上の和解とは違いますので、強制執行力はありませんが、通常はその内容が履行されます。金銭解決でまとまること多いでしょう。和解契約書には紛争を蒸し返さない清算条項が入りますので、和解できればその紛争はそこで終了します。
3.弁護士(裁判所)委託コース
上記1,2に比べると会社としては更に要警戒のコースです。通常はいきなり訴状が来るのではなく、「ご通知」などの内容証明郵便が弁護士名で送付されてきます。そして一方的に設定した期日までに、誠意ある対応を会社が取らない場合、訴訟(仮処分や労働審判を含む)を起こして来るものです。
労働審判とは平成18年に始まった労働紛争に特化した裁判所での解決制度で3回以内の期日で短期間審理し、調停を試み、調停に至らない場合は審判(勝ち負け)が下されるものです。訴状が届いてから2週間程度で弁護士に答弁書を提出してもらう必要があり、会社側は日程的に非常にハードなものになります。
仮処分とは本訴訟前に、簡易な手続きで仮の措置を取るもので、解雇事案における仮の地位保全が典型的です。仮処分が下れば、その間、賃金も仮に支払い続けなければなりません。
後で、本訴訟で勝っても、返済されること見込みは薄く、かなりのダメージになります。
本訴訟はテレビドラマ等で少しイメージができますが、概して時間がかかり、地裁で1年程度は覚悟しておいた方がいいでしょう。高裁への控訴、最高裁への上告となると一体いつまでかかるのか予測不能です。裁判でも和解は試みられますが、裁判事務では必ず弁護士(できれば使用者側で労働問題を専門に扱う人)を立てる必要があります。
本訴訟にしても労働審判にしても裁判所からの呼び出しは無視することができず、会社も弁護士を立てて、主張しなければなりません。そういう意味で受諾が任意のあっせんとは違います。
また裁判所では、法律が厳格に解釈され、あっせんのようなグレーゾーン解決はありません。最終決着は勝つか、負けるかです。和解が成立しても強制執行力があり、これらはあっせんとの大きな違いです。
このコースは、会社が勝ってもほとんど実利的には無益です。何故なら例えば解雇紛争で勝ったとしても、当初の解雇した意思表示が有効となるだけで、特段何かを得る物ではありません。いわば無駄な時間と労力と費用と、更に精神的負担が浪費されるだけです。まして負ければ相当の痛手を負うことを覚悟しなければなりません。例えば残業未払い事案で負けると、会社にとっては不当に高額な残業代が認定されるだけでなく、付加金(倍返し)や遅延利息なども覚悟しなければなりません。また労働審判は非公開ですが、裁判は公開制であり、実社名で記録が残るため、会社の信用問題にも影響しかねません。
4.合同労組コース
駆け込む先にもよりますが、会社としては最も警戒すべきコースです。場合によっては、やくざ的な世界へ入り込んでしまうことも有り得ます。合同労組(ユニオンともいう)とは、一人でも加入できる会社外部の労働組合のことです。
企業内組合の場合は、自分たちの会社のこととして同じベクトルに向けることも可能ですが、会社に帰属意識のない合同労組は、会社と共同歩調で歩める可能性は極めて低く、むしろ何かに付けて揚げ足取りのように介入してくることが予想されます。
彼らは労働組合法という強烈な法律に守られており、団体交渉の申し込みがあれば拒否することはできません。また組合活動に伴う民事上、刑事上の責任は免責されています。団体交渉の過程で労働基準監督署もよく使いますが、労働委員会という不当労働行為を審査する行政機関も良く使います。不当労働行為とは会社が組合にしてはいけない行為のことです。
威嚇行為としてビラ撒きや街宣活動に及ぶこともあり、
精神的にかなり追い詰められることにもなりかねません。対立が激しくなると、会社の周りだけでなく、得意先や取引銀行周辺でもやります。役員の自宅周辺でやることもあります(ただこれは違法だが)。
退職後に加入されるよりも、在職中に加入されると、その従業員が辞めない限り、ずっと団体交渉に応じてゆく覚悟が必要で、出口のの見えない遠い道のりになります。団体交渉を弁護士へ委任することは不可能ではありませんが、裁判のように全面的に代理人になってもらってお任せする、というわけにな行かず、会社も相当のお付き合いをして行かねばなりません。
多少お金がかかっても、最終的に金銭解決できれば良い方でしょう。
5.親族(例外)コース
これは出るところへ出るというものではありませんが、稀にあるケースです。例えば労災事故に被災した従業員の親族が、会社へ直接交渉してくるものです。登場する人にもよりますが、ルールの無い世界なので、場合によっては非常に困惑する対応をしてくるケースがあります。
いずれにしても見通しを誤るのは危険です。また出るところへ出られる前に手を打てることもたくさんあります。まず、労務の専門家の助言を得るべきです。
文責 特定社会保険労務士 西村 聡
もっと見る :http://www.nishimura-roumu.com

●社内で解決できない労使紛争が、その後どういう経緯を辿るのかイメージしておこう~
労使紛争が増加しています。よく、クライアント様にそのようなお話をしても自信満々に、「ウチは大丈夫」と安心しておられる経営者もあります。が、多くの事例を拝見する立場から申し上げると、その理屈は「ウチの子に限って!」と言う親の心理に似ています。現実はどこで起こってもおかしくないのです。
労使紛争を類型化すると、「解雇・退職勧奨など離職に関すること」、「労働条件の引き下げに関すること」、「賃金(残業代)の未払いに関すること」が多くを占めるのですが、最近ではここに「いじめ・嫌がらせ(いわゆるパワーハラスメント)」が増加傾向にあります。
こういったことが起こったとき、当事者同士で解決できなければ、紛争として表面化します。表面化とは簡単に言えば、従業員が「出るところに出る」ということです。揉めても従業員が出るところに出なければ、表面化せず、消えてゆくだけです。では、その「出るところ」とは、どのようなところがあるのでしょうか。その見通しを持っておくことは、紛争を拡大させないためにも重要なことです。
主に従業員が「出るところ」とは以下のコースがあるのです。
1.労働基準監督署への申告コース
2.あっせん申請コース
3.弁護士(裁判所)委託コース
4.合同労組加入コース
5.親族(例外)コース
1.労働基準監督署への申告コース
労働基準法104条では違反事実を労働者が労基署へ申告する権利を認めており、費用も懸からず、一番多いコースです。対応する労働基準監督官にもよるのですが、会社としても妥当な解決策を模索し易いコースと言えるでしょう。調査を拒否することはできません。
よく労基署は労働問題全てを管轄しているように勘違いされているケースがありますが、監督官が取り扱う法律は労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法など限られた特別法のみで、トラブルの多い同じ労働問題でも、社会保険や労災に関すること、育児介護やセクハラに関すること、人材派遣や偽装請負に関することなどは対象外です(これらは別の所轄があります)。
また解雇や未払い賃金に関しても、法違反として断定できないこと、例えば解雇紛争で解雇の有効性が争点の場合や、未払い賃金紛争で労働時間の解釈が争点などの場合、これらは民事紛争となり、行政機関である労基署の管轄外となります。
これらに関する申告の場合は、原則的には他の管轄がある場合はその窓口を紹介され、民事紛争に該当することは次に述べる「あっせん」などの他の解決機関を紹介されることとなります。労基法などに違反事実があると断定されたときは、「是正勧告書」なる行政指導の文書が手交され、一定期日までにその違反状態を自ら是正して報告するという流れで、通常このコースは終了することとなります。
先ほど妥当な解決が図りやすいと申しましたが、デメリット?としては、行政指導という性格から、場合により画一的に調査され、直接紛争とは関係のない他の事案(安全衛生管理状態など)や他の従業員のことについても、波及する可能性があることが挙げられます。また監督官は司法警察権を有しているため、行政指導に従わない場合は、刑事処分される可能性もあります。
2.あっせん申請コース
これは労使紛争であっても、前述のように行政指導に馴染まない民事紛争に関することや、裁判所へ行って争う意思まではないが、何らかの行動を起こしたいというような場合に、選択されます。公的に解決を援助するあっせん機関から「あっせん開始通知書」なるものが送られて来るものです。大阪の場合は、大阪労働局・大阪府労働委員会・大阪府社会保険労務士会にその機関があります。弁護士に頼らなくとも本人申請でできるので、よく利用される傾向にあります。
このあっせんは、参加に強制力はなく、受諾するかどうかは自由です。受諾しなければ即「打ち切り」となります。また開始されても、和解に至らなければ同様に「打ち切り」となります。その後労働者が諦めず、更に次の解決策を選択する可能性もあるので、紛争内容が言いがかりに近いものでなく、互譲の精神で会社にも解決の意思があるなら、受諾して和解することをお勧めします。場合によっては会社から先に「あっせん」をかけ、第三者の下で、解決を図ることもできます。
一般論として、あっせんは非対面方式で行い、法律を杓子定規に適用するのではなく、当事者の合意を最優先しますから、柔軟な解決方法が可能です。通常1日程度の期日で終了し、和解できれば民事上有効な和解契約書を交わします。裁判上の和解とは違いますので、強制執行力はありませんが、通常はその内容が履行されます。金銭解決でまとまること多いでしょう。和解契約書には紛争を蒸し返さない清算条項が入りますので、和解できればその紛争はそこで終了します。
3.弁護士(裁判所)委託コース
上記1,2に比べると会社としては更に要警戒のコースです。通常はいきなり訴状が来るのではなく、「ご通知」などの内容証明郵便が弁護士名で送付されてきます。そして一方的に設定した期日までに、誠意ある対応を会社が取らない場合、訴訟(仮処分や労働審判を含む)を起こして来るものです。
労働審判とは平成18年に始まった労働紛争に特化した裁判所での解決制度で3回以内の期日で短期間審理し、調停を試み、調停に至らない場合は審判(勝ち負け)が下されるものです。訴状が届いてから2週間程度で弁護士に答弁書を提出してもらう必要があり、会社側は日程的に非常にハードなものになります。
仮処分とは本訴訟前に、簡易な手続きで仮の措置を取るもので、解雇事案における仮の地位保全が典型的です。仮処分が下れば、その間、賃金も仮に支払い続けなければなりません。
後で、本訴訟で勝っても、返済されること見込みは薄く、かなりのダメージになります。
本訴訟はテレビドラマ等で少しイメージができますが、概して時間がかかり、地裁で1年程度は覚悟しておいた方がいいでしょう。高裁への控訴、最高裁への上告となると一体いつまでかかるのか予測不能です。裁判でも和解は試みられますが、裁判事務では必ず弁護士(できれば使用者側で労働問題を専門に扱う人)を立てる必要があります。
本訴訟にしても労働審判にしても裁判所からの呼び出しは無視することができず、会社も弁護士を立てて、主張しなければなりません。そういう意味で受諾が任意のあっせんとは違います。
また裁判所では、法律が厳格に解釈され、あっせんのようなグレーゾーン解決はありません。最終決着は勝つか、負けるかです。和解が成立しても強制執行力があり、これらはあっせんとの大きな違いです。
このコースは、会社が勝ってもほとんど実利的には無益です。何故なら例えば解雇紛争で勝ったとしても、当初の解雇した意思表示が有効となるだけで、特段何かを得る物ではありません。いわば無駄な時間と労力と費用と、更に精神的負担が浪費されるだけです。まして負ければ相当の痛手を負うことを覚悟しなければなりません。例えば残業未払い事案で負けると、会社にとっては不当に高額な残業代が認定されるだけでなく、付加金(倍返し)や遅延利息なども覚悟しなければなりません。また労働審判は非公開ですが、裁判は公開制であり、実社名で記録が残るため、会社の信用問題にも影響しかねません。
4.合同労組コース
駆け込む先にもよりますが、会社としては最も警戒すべきコースです。場合によっては、やくざ的な世界へ入り込んでしまうことも有り得ます。合同労組(ユニオンともいう)とは、一人でも加入できる会社外部の労働組合のことです。
企業内組合の場合は、自分たちの会社のこととして同じベクトルに向けることも可能ですが、会社に帰属意識のない合同労組は、会社と共同歩調で歩める可能性は極めて低く、むしろ何かに付けて揚げ足取りのように介入してくることが予想されます。
彼らは労働組合法という強烈な法律に守られており、団体交渉の申し込みがあれば拒否することはできません。また組合活動に伴う民事上、刑事上の責任は免責されています。団体交渉の過程で労働基準監督署もよく使いますが、労働委員会という不当労働行為を審査する行政機関も良く使います。不当労働行為とは会社が組合にしてはいけない行為のことです。
威嚇行為としてビラ撒きや街宣活動に及ぶこともあり、
精神的にかなり追い詰められることにもなりかねません。対立が激しくなると、会社の周りだけでなく、得意先や取引銀行周辺でもやります。役員の自宅周辺でやることもあります(ただこれは違法だが)。
退職後に加入されるよりも、在職中に加入されると、その従業員が辞めない限り、ずっと団体交渉に応じてゆく覚悟が必要で、出口のの見えない遠い道のりになります。団体交渉を弁護士へ委任することは不可能ではありませんが、裁判のように全面的に代理人になってもらってお任せする、というわけにな行かず、会社も相当のお付き合いをして行かねばなりません。
多少お金がかかっても、最終的に金銭解決できれば良い方でしょう。
5.親族(例外)コース
これは出るところへ出るというものではありませんが、稀にあるケースです。例えば労災事故に被災した従業員の親族が、会社へ直接交渉してくるものです。登場する人にもよりますが、ルールの無い世界なので、場合によっては非常に困惑する対応をしてくるケースがあります。
いずれにしても見通しを誤るのは危険です。また出るところへ出られる前に手を打てることもたくさんあります。まず、労務の専門家の助言を得るべきです。
文責 特定社会保険労務士 西村 聡
もっと見る :http://www.nishimura-roumu.com