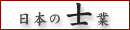11年10月12日
戦後混乱期か
生活保護受給者、過去最多に迫る204万人超 戦後混乱期並みに
《厚生労働省は12日、全国の生活保護受給者が、6月時点で204万1592人だったと発表した。戦後の混乱の余波で過去最多だった昭和26年度(月平均)の204万6646人に近づいた。》
《厚労省によると、今年6月は前月から1万5人増加した。世帯数は、147万9611世帯(前月比8354世帯増)で、過去最多を更新し続けている。》
<厚生年金>支給開始年齢引き上げに布石…厚労省案
《厚生年金の報酬比例部分の支給開始を65歳に引き上げる計画を早める厚生労働省案に対し、11日の社会保障審議会年金部会では「決まったものを途中で変えるのは国民の信頼低下を招く」といった意見が相次ぎ、実現の難しさを示した。68~70歳へ引き上げる案も今改革での導入は困難とみられている。しかし、定年制度の延長などを前提に「いずれはやむを得ない」との意見は複数出された。厚労省も「次」をにらみ、将来への布石として提案したというのが実情だ。 》
この2つのニュースが立て続けに発表されたが、普通は同じ厚労省なのに一体どうなっているのかと思うタイミングである。無論、端的に言ってしまえば、生活保護も増えるし、年金はますます期待度が薄まる。もはや年金記録の整備により回復した信頼ではあがなえない。定年がどうのこうのというのも、今の世代の話で、よきもあしきも転職が避けられないのが下の世代である。労働行政のリサーチもどうであろうか。産業界は厚労省の計画通り従うとも思えない。個人も納得しているとは思えない。生活保護に任せるという腹があるのかどうか。一行政が担う内容とはもはや思えない。各省から選び抜いた人材を新たな省に結集させるというのが、戦前の窮余の一策である。戦後混乱期の占領軍の生活保護制度等の資料も参考になろう。
《厚生労働省は12日、全国の生活保護受給者が、6月時点で204万1592人だったと発表した。戦後の混乱の余波で過去最多だった昭和26年度(月平均)の204万6646人に近づいた。》
《厚労省によると、今年6月は前月から1万5人増加した。世帯数は、147万9611世帯(前月比8354世帯増)で、過去最多を更新し続けている。》
<厚生年金>支給開始年齢引き上げに布石…厚労省案
《厚生年金の報酬比例部分の支給開始を65歳に引き上げる計画を早める厚生労働省案に対し、11日の社会保障審議会年金部会では「決まったものを途中で変えるのは国民の信頼低下を招く」といった意見が相次ぎ、実現の難しさを示した。68~70歳へ引き上げる案も今改革での導入は困難とみられている。しかし、定年制度の延長などを前提に「いずれはやむを得ない」との意見は複数出された。厚労省も「次」をにらみ、将来への布石として提案したというのが実情だ。 》
この2つのニュースが立て続けに発表されたが、普通は同じ厚労省なのに一体どうなっているのかと思うタイミングである。無論、端的に言ってしまえば、生活保護も増えるし、年金はますます期待度が薄まる。もはや年金記録の整備により回復した信頼ではあがなえない。定年がどうのこうのというのも、今の世代の話で、よきもあしきも転職が避けられないのが下の世代である。労働行政のリサーチもどうであろうか。産業界は厚労省の計画通り従うとも思えない。個人も納得しているとは思えない。生活保護に任せるという腹があるのかどうか。一行政が担う内容とはもはや思えない。各省から選び抜いた人材を新たな省に結集させるというのが、戦前の窮余の一策である。戦後混乱期の占領軍の生活保護制度等の資料も参考になろう。
11年10月06日
昭和の労務管理からの定点観測
昭和の労務管理を知る者にとって、労基法をはじめ民事訴訟の法的観点が会社の中に深く入ってくることは当時考えてもいなかったものである。あったことは、労働組合結成表明において憲法による保障が謳われ、それに多くの明治頃生まれの会長が激怒したようなことである。つまり、労働組合くらいしか法律を持ち出さなかった。
そこで、法的保障もなく労働者は働かされていたと外国の方や平成生まれの方は合点してしまうものであるが、全くそうではない。そこに、日本的もしくは発展途上的な性質とも受け取れるものがあった。
昭和の企業体制は鉄板なのであった。軍隊生活ほどではないが、相当な規律重視の秩序体制があった。除隊的な発想はなく、骨を埋めるのを前提にしているため、退職ましてや解雇ということは例外中の例外であった。労働者が憎む相手は社長や会社ではなく、上司や同僚や人事担当者である。まさしく「組織」であり、日本はこうした「組織」を各所に置く状態の、やはり封建体制というべきものであった。したがって、「組織外」の労基法をはじめ民事訴訟という中央的観点は、ほとんどその機能を期待されたものではなかった。占領軍の民主化政策がもっと長く続いておれば変ったはずであろうが、逆戻りに転じ、戦後的現象としてかつての国家を会社になぞらえる流れができ、それが自然に封建的なスタイルをとったまでである。
昭和の時代、まだ国家と会社の従属的関係はあった。公務員に関する制度の幾つかは会社にも流用された。無論、官報購読は必修である。
やはり契機は昭和の終わり頃の経済の自由化であろう。国家と会社の関係は、それまでの封建的な匂いのするものではなくなり、規制から緩和すなわち必罰主義に移ろっていく。それまでの規制内容自体が制度疲労化していたことも大きい。そして、機能を期待されてこなかった労基法や民事訴訟が活きてくる。封建的匂いが薄まる中で、これからも継続して揉まれる段階にある。
そこで、法的保障もなく労働者は働かされていたと外国の方や平成生まれの方は合点してしまうものであるが、全くそうではない。そこに、日本的もしくは発展途上的な性質とも受け取れるものがあった。
昭和の企業体制は鉄板なのであった。軍隊生活ほどではないが、相当な規律重視の秩序体制があった。除隊的な発想はなく、骨を埋めるのを前提にしているため、退職ましてや解雇ということは例外中の例外であった。労働者が憎む相手は社長や会社ではなく、上司や同僚や人事担当者である。まさしく「組織」であり、日本はこうした「組織」を各所に置く状態の、やはり封建体制というべきものであった。したがって、「組織外」の労基法をはじめ民事訴訟という中央的観点は、ほとんどその機能を期待されたものではなかった。占領軍の民主化政策がもっと長く続いておれば変ったはずであろうが、逆戻りに転じ、戦後的現象としてかつての国家を会社になぞらえる流れができ、それが自然に封建的なスタイルをとったまでである。
昭和の時代、まだ国家と会社の従属的関係はあった。公務員に関する制度の幾つかは会社にも流用された。無論、官報購読は必修である。
やはり契機は昭和の終わり頃の経済の自由化であろう。国家と会社の関係は、それまでの封建的な匂いのするものではなくなり、規制から緩和すなわち必罰主義に移ろっていく。それまでの規制内容自体が制度疲労化していたことも大きい。そして、機能を期待されてこなかった労基法や民事訴訟が活きてくる。封建的匂いが薄まる中で、これからも継続して揉まれる段階にある。
11年10月05日
電話での名乗り上げ
初めて電話をする人に対しては、まず名乗り上げを行う。これがマナーである。
ところが、相手側は何の用件でかかってきたかに気を使っているため、用件の方が実は肝心なのである。用件を聞き、自分にどういった関係のものであるかを判断する。そして、誰からかかってきたかについてはもはや覚えていない。覚えていないというよりも記憶していないのである。
この状態のとき、相手側は電話をかけた者に対してあらためて誰何しなければならない。そういう手間をとらせる点で、やはり順序的にマナー違反が濃厚である。まして普通の感覚であれば、既に受話器を置いてしまっている後である。
したがって、最初の名乗り上げは無論正しいが、用件が済んだ後あらためてまた名乗り上げしない場合は正しくないということである。たいてい、必死の頼み事であれば確実性を期すため、「〇〇までよろしく」と最後締めくくることになろう。弱いお願いの場合、よく失敗するというのも道理である。ビジネスその他組織行動の場面では、あまり気乗りのしない企画などで、相手側との連絡関係があやふやになる可能性が高いということである。
さらに、帰属意識の問題が絡む。組織行動においての参加意識の問題である。現代日本企業社会においては帰属意識を薄くする傾向がむしろ経営側に強く、それが従業員に移っている。それで契約関係といった法律がクローズアップされてきた。さらに、労務管理理論がバブル以降の日本社会に対してついていけなくなったという反省もある。結局、今言えることは、法的関係を突き詰めて言った後、フィットした労務管理理論がぼつぼつと出てくるだろうということである。法律関係の彼岸まで見通せたら、足元を見ようとするものである。
ところが、相手側は何の用件でかかってきたかに気を使っているため、用件の方が実は肝心なのである。用件を聞き、自分にどういった関係のものであるかを判断する。そして、誰からかかってきたかについてはもはや覚えていない。覚えていないというよりも記憶していないのである。
この状態のとき、相手側は電話をかけた者に対してあらためて誰何しなければならない。そういう手間をとらせる点で、やはり順序的にマナー違反が濃厚である。まして普通の感覚であれば、既に受話器を置いてしまっている後である。
したがって、最初の名乗り上げは無論正しいが、用件が済んだ後あらためてまた名乗り上げしない場合は正しくないということである。たいてい、必死の頼み事であれば確実性を期すため、「〇〇までよろしく」と最後締めくくることになろう。弱いお願いの場合、よく失敗するというのも道理である。ビジネスその他組織行動の場面では、あまり気乗りのしない企画などで、相手側との連絡関係があやふやになる可能性が高いということである。
さらに、帰属意識の問題が絡む。組織行動においての参加意識の問題である。現代日本企業社会においては帰属意識を薄くする傾向がむしろ経営側に強く、それが従業員に移っている。それで契約関係といった法律がクローズアップされてきた。さらに、労務管理理論がバブル以降の日本社会に対してついていけなくなったという反省もある。結局、今言えることは、法的関係を突き詰めて言った後、フィットした労務管理理論がぼつぼつと出てくるだろうということである。法律関係の彼岸まで見通せたら、足元を見ようとするものである。