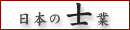13年09月13日
ドイツの解雇紛争処理実務 のコラムで
ドイツの解雇紛争処理実務に想う
JIL研究員 山本 陽大
《今年の7月に現地調査のためドイツへ出張した際、時間が空いたので、現地の弁護士に勧められ、労働裁判を傍聴しに行ってみた。》
《ドイツでは、労働裁判所法61a条という規定により、解雇事件については訴訟提起から2週間以内に和解手続(Güteverhandlung)を実施すべきこととされている。「ドイツにおける解雇事件は、その9割が裁判所での和解により終了している。」というのは日本でもよく知られた話であるが、現場はどうなっているのか、解雇法制の日独比較を研究対象としている筆者としては、大いに興味があった。》
《どの事件においても、裁判官(比較的若い、女性の裁判官であった。)が簡単に事実関係を確認したうえで、すぐに補償金(和解金)の支払いによる解決を当事者達に提案する。ここでの補償金額の算定について、法律上のルールはないが、実務では当該労働者の勤続年数×月給額×一定の係数(0.5~2.0、係数値は本人の年齢により変化する。)という算定式が確立しており、これに従って裁判官が電卓を叩き、金額を算出する。当事者達は、そのようにして算出された金額を前に、和解に応じるかどうかの話し合いを行うが、筆者が傍聴した6件中、1件を除いては、裁判官が提示した金額により和解が成立した(1件だけは、和解が成立せず判決手続へ移行したが、これは韓国系企業と韓国人労働者の間の解雇事件であった。)。短いものでは、1件の和解手続に15分もかかっていなかっただろう。》
《もっとも、このようなドイツにおける解雇紛争処理の実態は、法律のルールとはかなりかけ離れたものと映る。ドイツでは法律上、正当な理由の無い解雇は無効となり、労働者は原職復帰するのが原則とされ(解雇制限法1条)、極めて例外的な事案に限り金銭解決が可能とされている(同法9条および10条)(注1)。にもかかわらず、その実態は金銭解決による雇用の終了が、むしろ主流となっているのである。その点では、ドイツの解雇をめぐる「法の世界」と「事実の世界」は、乖離してしまっているともいえるだろう。》
《しかし、筆者は次のようにも考えた。確かに、「法の世界」と「事実の世界」は乖離しているけれども、法律のなかには、年齢が高い、あるいは勤続年数の長い労働者ほど、解雇から保護されるべきとの考え方に基づく規定が随所に登場する(例えば、解雇制限法1条5項、1a条および10条2項)。そして、このような法律のルールがあるからこそ、勤続年数と年齢を考慮要素に据えた補償金の算定式が、合理的で当事者らの納得も得られやすいものとして、和解実務上確立した地位を占めているのではないだろうか。言い換えれば、ドイツの解雇をめぐる「法の世界」には、「事実の世界」が一定程度安定的かつ合理的なものに落ち着くよう、下支えをしている側面があるのではないだろうか。》
《このように考えると、日本の問題点が浮かび上がってくる。日本では、労働契約法16条により解雇規制が行われているが、「それは、どのような労働者のどのような利益を守るためのものなのか?」、この点がいまひとつハッキリしていない。日本でもドイツと同様に、労契法16条自体は、違法解雇の法律効果を無効と定めているが、実務上解雇紛争の多くは、労働審判や紛争調整委員会のあっせんを通じて金銭解決により終了している(注2)。しかし、そこではドイツのような統一的な算定式などは存在せず、解決金額にもバラつきが見られるようである(注3)。日本でも、解雇の金銭解決制度の立法化が折に触れて話題となっているが、同制度を構想する際には、「そもそも解雇規制は、どのような労働者のどのような利益を守るためのものなのか?」という問題に立ち戻って検討する必要があるのではないだろうか…。》
ほぼ全文引用してしまうほど、この報告と感想は大事なポイントを突いていると思われた。
核心は、「法律のなかには、年齢が高い、あるいは勤続年数の長い労働者ほど、解雇から保護されるべきとの考え方に基づく規定が随所に登場する(例えば、解雇制限法1条5項、1a条および10条2項)。そして、このような法律のルールがあるからこそ、勤続年数と年齢を考慮要素に据えた補償金の算定式が、合理的で当事者らの納得も得られやすいものとして、和解実務上確立した地位を占めているのではないだろうか。」とする部分である。これはドイツ社会が共有する労働法の底に流れる思想と紛争処理形態との一致に気付いたというもので、文化思想的には「軍隊生活」について、かつて山本七平氏が指摘されたことと同じである。日本では、本当にあるべき制度形態が実行されているのかどうか。意見対立に止まる段階を超えて、本質的にあるべき形態を実現されうるのか。
尤も、そのドイツの法処理がドイツ国民の大多数に支持されているのか、それとも過半数をかろうじて超えている程度かを知る必要がある。隣の芝は青い類かの要確認。
JIL研究員 山本 陽大
《今年の7月に現地調査のためドイツへ出張した際、時間が空いたので、現地の弁護士に勧められ、労働裁判を傍聴しに行ってみた。》
《ドイツでは、労働裁判所法61a条という規定により、解雇事件については訴訟提起から2週間以内に和解手続(Güteverhandlung)を実施すべきこととされている。「ドイツにおける解雇事件は、その9割が裁判所での和解により終了している。」というのは日本でもよく知られた話であるが、現場はどうなっているのか、解雇法制の日独比較を研究対象としている筆者としては、大いに興味があった。》
《どの事件においても、裁判官(比較的若い、女性の裁判官であった。)が簡単に事実関係を確認したうえで、すぐに補償金(和解金)の支払いによる解決を当事者達に提案する。ここでの補償金額の算定について、法律上のルールはないが、実務では当該労働者の勤続年数×月給額×一定の係数(0.5~2.0、係数値は本人の年齢により変化する。)という算定式が確立しており、これに従って裁判官が電卓を叩き、金額を算出する。当事者達は、そのようにして算出された金額を前に、和解に応じるかどうかの話し合いを行うが、筆者が傍聴した6件中、1件を除いては、裁判官が提示した金額により和解が成立した(1件だけは、和解が成立せず判決手続へ移行したが、これは韓国系企業と韓国人労働者の間の解雇事件であった。)。短いものでは、1件の和解手続に15分もかかっていなかっただろう。》
《もっとも、このようなドイツにおける解雇紛争処理の実態は、法律のルールとはかなりかけ離れたものと映る。ドイツでは法律上、正当な理由の無い解雇は無効となり、労働者は原職復帰するのが原則とされ(解雇制限法1条)、極めて例外的な事案に限り金銭解決が可能とされている(同法9条および10条)(注1)。にもかかわらず、その実態は金銭解決による雇用の終了が、むしろ主流となっているのである。その点では、ドイツの解雇をめぐる「法の世界」と「事実の世界」は、乖離してしまっているともいえるだろう。》
《しかし、筆者は次のようにも考えた。確かに、「法の世界」と「事実の世界」は乖離しているけれども、法律のなかには、年齢が高い、あるいは勤続年数の長い労働者ほど、解雇から保護されるべきとの考え方に基づく規定が随所に登場する(例えば、解雇制限法1条5項、1a条および10条2項)。そして、このような法律のルールがあるからこそ、勤続年数と年齢を考慮要素に据えた補償金の算定式が、合理的で当事者らの納得も得られやすいものとして、和解実務上確立した地位を占めているのではないだろうか。言い換えれば、ドイツの解雇をめぐる「法の世界」には、「事実の世界」が一定程度安定的かつ合理的なものに落ち着くよう、下支えをしている側面があるのではないだろうか。》
《このように考えると、日本の問題点が浮かび上がってくる。日本では、労働契約法16条により解雇規制が行われているが、「それは、どのような労働者のどのような利益を守るためのものなのか?」、この点がいまひとつハッキリしていない。日本でもドイツと同様に、労契法16条自体は、違法解雇の法律効果を無効と定めているが、実務上解雇紛争の多くは、労働審判や紛争調整委員会のあっせんを通じて金銭解決により終了している(注2)。しかし、そこではドイツのような統一的な算定式などは存在せず、解決金額にもバラつきが見られるようである(注3)。日本でも、解雇の金銭解決制度の立法化が折に触れて話題となっているが、同制度を構想する際には、「そもそも解雇規制は、どのような労働者のどのような利益を守るためのものなのか?」という問題に立ち戻って検討する必要があるのではないだろうか…。》
ほぼ全文引用してしまうほど、この報告と感想は大事なポイントを突いていると思われた。
核心は、「法律のなかには、年齢が高い、あるいは勤続年数の長い労働者ほど、解雇から保護されるべきとの考え方に基づく規定が随所に登場する(例えば、解雇制限法1条5項、1a条および10条2項)。そして、このような法律のルールがあるからこそ、勤続年数と年齢を考慮要素に据えた補償金の算定式が、合理的で当事者らの納得も得られやすいものとして、和解実務上確立した地位を占めているのではないだろうか。」とする部分である。これはドイツ社会が共有する労働法の底に流れる思想と紛争処理形態との一致に気付いたというもので、文化思想的には「軍隊生活」について、かつて山本七平氏が指摘されたことと同じである。日本では、本当にあるべき制度形態が実行されているのかどうか。意見対立に止まる段階を超えて、本質的にあるべき形態を実現されうるのか。
尤も、そのドイツの法処理がドイツ国民の大多数に支持されているのか、それとも過半数をかろうじて超えている程度かを知る必要がある。隣の芝は青い類かの要確認。