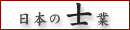14年09月23日
自律した働き方 と経営
残業代を支払わない会社は「労働基準法をなめている」
《残業はいとわないが、それに見合った処遇を――。こうした考えの若者が増加していることを指摘した調査結果が、ネット上で議論を呼んでいる。》弁護士ドットコム 9月23日(火)
《話題となったのは、日本生産性本部・日本経済青年協議会が、2014年度の新社会人約2200人を対象に実施した「働くことの意識」調査。「残業についてどう思うか」という質問に対して「手当がもらえるからやってもよい」と答えた若者が69.4%と過去最高だった。一方、「手当にかかわらず仕事だからやる」は下降線をたどっており、今回23.7%にとどまった。調査報告書は、「残業はいとわないが、それに見合った処遇を求めている傾向がうかがえる」とまとめている。
この調査結果に対して、ネットの掲示板サイトでは、「金貰う為に働いてるのに貰えない分まで仕事する意味がわからん」といった意見がある一方で、「残業代が欲しいなら、残業代が払えるほど利益を会社に与えろ」「まだロクに仕事も覚えてないのに…」「社会なめすぎ」といった意見もあった。》
バブル崩壊後の資金ショート、退職金債務超過などで、日本の会社の経営学は挫折した。そして世界主要国にも誇った昭和の「日本的経営」を取り崩した。背に腹は変えられない
ということである。以後、無秩序にも脱線する経営者も出て、また自然状態といおうか原状態のまま今日に至っている経営もあるし、またぞろ海外のモデルに頼ろうとする経営もある。
労働者の方はこの変化によって上手く「巻き添え」を逃れた中高齢者もいたが、多くはまだ労働の中心あるいは末端にいる者たちであり、この者らの多くは生活が立ち行かなくなる状態に陥っており、今日に至っている。
「日本的経営」のメインは日本的労務管理にある。法の介入も困難なほど強固な組織力がメインであった。戦争末期の挙国、報国、全体主義体制の流れが、戦後の社会動乱を経て辿って落ち着いたところに合流した。危機の中にあってその限界状況において確立されたもの、確かにそれはゆるぎない日本的性質のエッセンスが認められる。むろん、文学作品に記されているように、ある面理屈が通らず苛酷でもあった。地上げの心配がまとわりついたバブル現象もそうである。しかし、国家経済的には、成功した。そして、国家経済的に失敗すると、自律して考えることに慣れていない国民は路頭に迷った。
日本的労務管理論が急速にしぼみ、経営はそれを否定する方針を進めた。ただ生き残るためだけの理由なので、経営論は皆目ない。裁判ではたいてい会社の権利濫用や解雇無効という結果である。したがって、「労働者の味方」というよりも、会社の行為の理不尽さのみで判断が済んでいるのが殆どというものである。労働者は労務方針の根本的変化あるいは崩壊に遭い、労働が従来のように精神的にも収入的にも報われることがないことを知る以上、公的なものを軸として自律しようとする。世界に誇る強固な組織力は既に会社自らによって崩壊させている。
そのような平成の職場状況にあって、まだ従前の「日本的経営」のまま思考している者も目立つ。むろん、それは日本的組織のエッセンスではあるが、今はその時ではない。
また、<「会社は適正な業務量を設定したり、業務指示によって『残業をさせない』ことができます。>と波多野弁護士の言う通りであるが、「日本的経営」では殆ど意識する必要がなかったため、経営の指揮管理能力が今ほとんど水準に達していないのではないかという感触もある。セクハラ、パワハラの多くは上司など近い職制の者からのものであるが、トップが把握すらしていないというものも多く、解決能力も低いものが多い。
自律した働き方はまだ組織内ではなかなか難しいが、自律した経営はそれよりもずっと遅れている。そこにはまだまだ「日本的経営」が邪魔な障害物として漂っている。
《残業はいとわないが、それに見合った処遇を――。こうした考えの若者が増加していることを指摘した調査結果が、ネット上で議論を呼んでいる。》弁護士ドットコム 9月23日(火)
《話題となったのは、日本生産性本部・日本経済青年協議会が、2014年度の新社会人約2200人を対象に実施した「働くことの意識」調査。「残業についてどう思うか」という質問に対して「手当がもらえるからやってもよい」と答えた若者が69.4%と過去最高だった。一方、「手当にかかわらず仕事だからやる」は下降線をたどっており、今回23.7%にとどまった。調査報告書は、「残業はいとわないが、それに見合った処遇を求めている傾向がうかがえる」とまとめている。
この調査結果に対して、ネットの掲示板サイトでは、「金貰う為に働いてるのに貰えない分まで仕事する意味がわからん」といった意見がある一方で、「残業代が欲しいなら、残業代が払えるほど利益を会社に与えろ」「まだロクに仕事も覚えてないのに…」「社会なめすぎ」といった意見もあった。》
バブル崩壊後の資金ショート、退職金債務超過などで、日本の会社の経営学は挫折した。そして世界主要国にも誇った昭和の「日本的経営」を取り崩した。背に腹は変えられない
ということである。以後、無秩序にも脱線する経営者も出て、また自然状態といおうか原状態のまま今日に至っている経営もあるし、またぞろ海外のモデルに頼ろうとする経営もある。
労働者の方はこの変化によって上手く「巻き添え」を逃れた中高齢者もいたが、多くはまだ労働の中心あるいは末端にいる者たちであり、この者らの多くは生活が立ち行かなくなる状態に陥っており、今日に至っている。
「日本的経営」のメインは日本的労務管理にある。法の介入も困難なほど強固な組織力がメインであった。戦争末期の挙国、報国、全体主義体制の流れが、戦後の社会動乱を経て辿って落ち着いたところに合流した。危機の中にあってその限界状況において確立されたもの、確かにそれはゆるぎない日本的性質のエッセンスが認められる。むろん、文学作品に記されているように、ある面理屈が通らず苛酷でもあった。地上げの心配がまとわりついたバブル現象もそうである。しかし、国家経済的には、成功した。そして、国家経済的に失敗すると、自律して考えることに慣れていない国民は路頭に迷った。
日本的労務管理論が急速にしぼみ、経営はそれを否定する方針を進めた。ただ生き残るためだけの理由なので、経営論は皆目ない。裁判ではたいてい会社の権利濫用や解雇無効という結果である。したがって、「労働者の味方」というよりも、会社の行為の理不尽さのみで判断が済んでいるのが殆どというものである。労働者は労務方針の根本的変化あるいは崩壊に遭い、労働が従来のように精神的にも収入的にも報われることがないことを知る以上、公的なものを軸として自律しようとする。世界に誇る強固な組織力は既に会社自らによって崩壊させている。
そのような平成の職場状況にあって、まだ従前の「日本的経営」のまま思考している者も目立つ。むろん、それは日本的組織のエッセンスではあるが、今はその時ではない。
また、<「会社は適正な業務量を設定したり、業務指示によって『残業をさせない』ことができます。>と波多野弁護士の言う通りであるが、「日本的経営」では殆ど意識する必要がなかったため、経営の指揮管理能力が今ほとんど水準に達していないのではないかという感触もある。セクハラ、パワハラの多くは上司など近い職制の者からのものであるが、トップが把握すらしていないというものも多く、解決能力も低いものが多い。
自律した働き方はまだ組織内ではなかなか難しいが、自律した経営はそれよりもずっと遅れている。そこにはまだまだ「日本的経営」が邪魔な障害物として漂っている。
14年09月21日
紛争解決代理業務試論
特定社会保険労務士資格ができて数年経つが、まだ定着までには至っていない。むろん、もともと簡単な業務ではないこともあるにせよ、である。
初期の資格はあっせん代理人であったが、それもすぐに紛争解決代理人に引き上げられた。「あっせん代理人」はその名の通りで、顧問先なり関与先で生じた個別労使紛争を事業主の代理人として行動する(労務管理業務の延長)というものを想定されていたが、「紛争解決代理人」では個別労使関係に関する民事紛争の代理人という性格になった。この流れの詳細は今、調べていないが、この性格の違いは大きなものがある。
特定社会保険労務士において民事紛争解決についてのノウハウが醸成されていないことに尽きる。労働相談もできるし、判例もよく知っている。ただし、それは「あっせん代理人」の状態で止まっているに過ぎない。「民事紛争解決代理人」において必要なノウハウは解決手段、方法に尽きる。
訴訟上の和解、は数回審尋を開き労使の主張を経て、全体が見えたときに勧告がなされる。4回期日を開いたとすれば、5回目に勧告である。
その5回目だけを取り出したのが、あっせん制度と考えればよい。したがって、少なくとも4回とは言わずとも数回の主張の往復をあっせん期日前に済ませ、当日は全体を見据えての和解勧告相当期日と考えることができる。
あっせん制度では「紛争状態が生じていること」(労使の主張の食い違いが生じていること)を前提として申請受付するが、それは制度運営上の最低限のことであるに過ぎない。あっせん申請の受付ができることと、解決できることとは違うのである。
結果、あっせん制度は参加されない例が多く、一方参加されれば解決率は高い。(しかし、解決額は司法とかけ離れていると一般的に言われている。このことについては産業競争力会議などで分析中である。)普通の労働者が紛争解決しようと行動する契機になったことは評価でき、使用者の労働関係観も若干変化した―権利の濫用の表面化が加速。ただ、もうそろそろ簡易、迅速の謳い文句は変えるべきだろう。なお、昭和の内向型の組織からの脱皮を目前としながらも、新たな労務管理論は構築されていないことが不安の種としてある。
いずれにせよ、あっせん期日では訴訟上の和解勧告日相当の期日と設定しておく必要がある。基本「一回」の期日であり、なぜ1回で終了できるのかがポイントである。
紛争事情、本人の主張と要求事項、相手方の主張とそれへの対応、争点整理その他証明物保全など、これらを本人でできるならばその補佐人として、できなければ代理人として進める。
ここまで進めばたいていはあっせんで和解すると考えるが、和解するしないは当事者の自由である。また、相手方が特定社会保険労務士または弁護士をつけた場合、当事者間での和解が行われることもある。その場合は、代理人業務ではなく労務管理業務となる。(紛争解決業務については、既存の社労士業務と弁護士法との関係により、やや複雑である。依頼者には直接関係ないことではあるが。)
初期の資格はあっせん代理人であったが、それもすぐに紛争解決代理人に引き上げられた。「あっせん代理人」はその名の通りで、顧問先なり関与先で生じた個別労使紛争を事業主の代理人として行動する(労務管理業務の延長)というものを想定されていたが、「紛争解決代理人」では個別労使関係に関する民事紛争の代理人という性格になった。この流れの詳細は今、調べていないが、この性格の違いは大きなものがある。
特定社会保険労務士において民事紛争解決についてのノウハウが醸成されていないことに尽きる。労働相談もできるし、判例もよく知っている。ただし、それは「あっせん代理人」の状態で止まっているに過ぎない。「民事紛争解決代理人」において必要なノウハウは解決手段、方法に尽きる。
訴訟上の和解、は数回審尋を開き労使の主張を経て、全体が見えたときに勧告がなされる。4回期日を開いたとすれば、5回目に勧告である。
その5回目だけを取り出したのが、あっせん制度と考えればよい。したがって、少なくとも4回とは言わずとも数回の主張の往復をあっせん期日前に済ませ、当日は全体を見据えての和解勧告相当期日と考えることができる。
あっせん制度では「紛争状態が生じていること」(労使の主張の食い違いが生じていること)を前提として申請受付するが、それは制度運営上の最低限のことであるに過ぎない。あっせん申請の受付ができることと、解決できることとは違うのである。
結果、あっせん制度は参加されない例が多く、一方参加されれば解決率は高い。(しかし、解決額は司法とかけ離れていると一般的に言われている。このことについては産業競争力会議などで分析中である。)普通の労働者が紛争解決しようと行動する契機になったことは評価でき、使用者の労働関係観も若干変化した―権利の濫用の表面化が加速。ただ、もうそろそろ簡易、迅速の謳い文句は変えるべきだろう。なお、昭和の内向型の組織からの脱皮を目前としながらも、新たな労務管理論は構築されていないことが不安の種としてある。
いずれにせよ、あっせん期日では訴訟上の和解勧告日相当の期日と設定しておく必要がある。基本「一回」の期日であり、なぜ1回で終了できるのかがポイントである。
紛争事情、本人の主張と要求事項、相手方の主張とそれへの対応、争点整理その他証明物保全など、これらを本人でできるならばその補佐人として、できなければ代理人として進める。
ここまで進めばたいていはあっせんで和解すると考えるが、和解するしないは当事者の自由である。また、相手方が特定社会保険労務士または弁護士をつけた場合、当事者間での和解が行われることもある。その場合は、代理人業務ではなく労務管理業務となる。(紛争解決業務については、既存の社労士業務と弁護士法との関係により、やや複雑である。依頼者には直接関係ないことではあるが。)