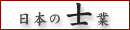15年05月17日
懲戒処分の研究 [古典編]
『4 法律の解釈』
《刑事裁判官は刑罰法規を解釈する権限をもたない。それは彼が立法者でないというその同じ理由にもとづく。裁判官は法律を、われわれの祖先から家族的な因習として、あるいは子孫が実行しなければならない遺言として受けとったのではない。生きて存続している社会、あるいはその社会の現実の意思の合法的に委託された者でありその代表者である立法者から、受け取っているのである。》
これを懲戒処分のために読みかえると、立法者は会社となり、また裁判官も会社となるものだが、それには「その社会の現実の意思」の委託という点に基くというところが肝要である。それぞれの処分が組織秩序に関して合理的なものであるかどうかということになる。
《法律の合法性は、古代の契約を実行する義務にもとづいて存在するのではない。古代の契約は無効である。なぜなら、古代の契約はその当時存在していなかった意思を拘束することはできないから。》
これについてはベッカリーアの註がわかりやすい。
《あなたががもし何か義務をはたすことを要求するばあい、あなたがたがその義務がどんなものであるかを知っていなくてはならないはずである。》
つまり、ここでいう「古代」とは時代観念のことではなく、「与り知らない契約義務」と解釈すればよいだろう。日常的なトラブルの大半の原因ともいえる。かつての長期雇用の秩序ならびに企業間安定取引下においては「あんうんの呼吸」でスピーディーかつ満足感が得られた一方で、代替わり等する度や経済環境変動により「与り知らない契約義務」がトラブルの原因として浮上してきたのはその成り行きである。近年では仕事の仕方の説明を巡って顕著になってきたといえる。「マニュアル」というツールがそういう背景で登場してきたものだが、それで網羅できるものでもなく、人材教育がうまくいかないことがきっかけとなってハラスメントや解雇問題というかたちに発展することが多い。
《裁判官は一種の完全な三段論法によらなければならない。まず大前提として、一般法に適用する法。小前提は合法または違法の行為である。そして結論は被告の無罪放免か刑罰である。》
「一般法」というのは民法や労働関係諸法令と、小前提は自社の懲戒規定に照らしてどうか、そしてその処断の判定という対応でよいと思われる。
《法律が成文としてはっきり規定されており、司法官の役目は、ただ国民の行為を審査し、その行為が違法であるか適法であるかを法律の条文にてらして判断することだけになれば、そしてまた、無知な者であろうと、有識者であろうとそのすべての行動を指導する正と不正の規範が、議論の余地のないものであり、単純な事実問題でしかないことになれば、そのときは国民が無数の小圧制者のために苦しむことはもう見られなくなるだろう。》
実際には成文化されただけでの予見性は不確実さを免れ得ない。そこで証拠、証明力に重きを置かれているが、そのため不具合も起りうる。
《文字どおり施行される刑法があれば、国民は自分の不正行為からくるまずい結果を正確に知り、それを避けることができる。これは国民を犯罪から遠ざけるために有用なことである。こうして人々は一身と財産の安全を享受する。これは正しいことである。なぜなら人類が社会に結合する目的はここにあるからである。》
警告的意味は説明を要しない。
《また、このことから国民が自由と独立の精神をかちとることもたしかだ。彼らはもう支配者の気まぐれのまにまにただ盲目的に服従する弱さを徳と呼ぶような連中のドレイではない。しかしそれはすこしも、彼らが法と神聖な裁判官に服従しないということではないのである。》
日本の雇用環境においても最も厄介なのが「支配者の気まぐれ」となる。経済記事などで、明るい社員がいる会社が特集として取上げられるくらいである。高度成長期においては、経営陣の存在を脅かすような存在のある会社員も多かった。(辞めてほしいが、あいつがおらんようになったら会社は回らない)という存在である。今は会社の赤字等を社員の給与減を超えて搾取、借り入れ(合意取り引きもあるが、返済できずの金銭トラブルとなる)で埋め合わせている経営陣も増えている。
また、「請負」契約もまた見直されつつあるが、雇用観念に引きずられている例が多い。なかなか「自由と独立の精神」で働く、働かせるというのは当たり前ではない。
《刑事裁判官は刑罰法規を解釈する権限をもたない。それは彼が立法者でないというその同じ理由にもとづく。裁判官は法律を、われわれの祖先から家族的な因習として、あるいは子孫が実行しなければならない遺言として受けとったのではない。生きて存続している社会、あるいはその社会の現実の意思の合法的に委託された者でありその代表者である立法者から、受け取っているのである。》
これを懲戒処分のために読みかえると、立法者は会社となり、また裁判官も会社となるものだが、それには「その社会の現実の意思」の委託という点に基くというところが肝要である。それぞれの処分が組織秩序に関して合理的なものであるかどうかということになる。
《法律の合法性は、古代の契約を実行する義務にもとづいて存在するのではない。古代の契約は無効である。なぜなら、古代の契約はその当時存在していなかった意思を拘束することはできないから。》
これについてはベッカリーアの註がわかりやすい。
《あなたががもし何か義務をはたすことを要求するばあい、あなたがたがその義務がどんなものであるかを知っていなくてはならないはずである。》
つまり、ここでいう「古代」とは時代観念のことではなく、「与り知らない契約義務」と解釈すればよいだろう。日常的なトラブルの大半の原因ともいえる。かつての長期雇用の秩序ならびに企業間安定取引下においては「あんうんの呼吸」でスピーディーかつ満足感が得られた一方で、代替わり等する度や経済環境変動により「与り知らない契約義務」がトラブルの原因として浮上してきたのはその成り行きである。近年では仕事の仕方の説明を巡って顕著になってきたといえる。「マニュアル」というツールがそういう背景で登場してきたものだが、それで網羅できるものでもなく、人材教育がうまくいかないことがきっかけとなってハラスメントや解雇問題というかたちに発展することが多い。
《裁判官は一種の完全な三段論法によらなければならない。まず大前提として、一般法に適用する法。小前提は合法または違法の行為である。そして結論は被告の無罪放免か刑罰である。》
「一般法」というのは民法や労働関係諸法令と、小前提は自社の懲戒規定に照らしてどうか、そしてその処断の判定という対応でよいと思われる。
《法律が成文としてはっきり規定されており、司法官の役目は、ただ国民の行為を審査し、その行為が違法であるか適法であるかを法律の条文にてらして判断することだけになれば、そしてまた、無知な者であろうと、有識者であろうとそのすべての行動を指導する正と不正の規範が、議論の余地のないものであり、単純な事実問題でしかないことになれば、そのときは国民が無数の小圧制者のために苦しむことはもう見られなくなるだろう。》
実際には成文化されただけでの予見性は不確実さを免れ得ない。そこで証拠、証明力に重きを置かれているが、そのため不具合も起りうる。
《文字どおり施行される刑法があれば、国民は自分の不正行為からくるまずい結果を正確に知り、それを避けることができる。これは国民を犯罪から遠ざけるために有用なことである。こうして人々は一身と財産の安全を享受する。これは正しいことである。なぜなら人類が社会に結合する目的はここにあるからである。》
警告的意味は説明を要しない。
《また、このことから国民が自由と独立の精神をかちとることもたしかだ。彼らはもう支配者の気まぐれのまにまにただ盲目的に服従する弱さを徳と呼ぶような連中のドレイではない。しかしそれはすこしも、彼らが法と神聖な裁判官に服従しないということではないのである。》
日本の雇用環境においても最も厄介なのが「支配者の気まぐれ」となる。経済記事などで、明るい社員がいる会社が特集として取上げられるくらいである。高度成長期においては、経営陣の存在を脅かすような存在のある会社員も多かった。(辞めてほしいが、あいつがおらんようになったら会社は回らない)という存在である。今は会社の赤字等を社員の給与減を超えて搾取、借り入れ(合意取り引きもあるが、返済できずの金銭トラブルとなる)で埋め合わせている経営陣も増えている。
また、「請負」契約もまた見直されつつあるが、雇用観念に引きずられている例が多い。なかなか「自由と独立の精神」で働く、働かせるというのは当たり前ではない。
15年05月01日
懲戒処分の研究 〔古典編〕
『2 刑罰の起源と刑罰権の基礎に関する原理』
《政治上のモラルは、それが人間の不滅の感情に基礎をおいたものでないかぎり、社会に対してなんの永続的な利益も与えることができない。
この人間の不滅の感情という基礎におかれていない法律はすべてつねに抵抗にあい、ついには打ちまかされなければならない運命にある。》
《そこでこれから、刑罰の起源と刑罰権の真の基礎とを発見するために考察をすすめていくにさいして、私はつねに人間の心情というものを考え合わせながらいきたいと思う。》
社会の永続性と人間の不滅の心情を基礎に置いたところが重要である。社会性の観点と合理性の観点とがまず出されている。
ここから所謂「原始自然状況」的なイメージが叙述されていく。ここはそのままだと会社秩序の説明にはならないので、労働者は個人的な自由の一部を会社に渡す契約を個々に行い、その管理を会社に行わせる。実際には、契約をはじめ就業規則制定権は会社にあるので「行わせる」とまで表現できないが、いったん契約および就業規則が成立すると、会社はそれらにつき優位する権利がある分だけの義務があるとするもので、それは秩序維持する権利と義務という合わせ鏡をもつ。
《各人にその自由の割り前をさし出させるように強制するものは、ただ一つその必要性だけである。》
証拠としては契約、就業規則であるが、その前提として「必要性」がある。それらの規定が会社秩序維持に際しての必要性の認定問題である。それが、懲戒権の基礎とする。
《この基礎を逸脱する刑罰権の行使は、すべて濫用であり、不正である。それは事実上の権力であっても、法にもとづいた権利ではない。》
『3 前章の原理からの帰結』
《右で述べた原理から次のように帰結される。
第一。法律だけがおのおのの犯罪に対する刑罰を規定することができる。》
裁判官は法律の規定により刑を科し、法律で規定されているより厳しい刑を科すことはできない。また、裁判官はいかなる理由からであっても既に宣告された刑を加重することはできない。これを「罪刑法定主義」という。二重処罰の禁止にも触れられている。懲戒処分についてはそのまま適用されている。ここでいう裁判官は無論、会社の懲罰指令責任者のことである。(なお、ベッカリーアによれば、我々が裁判官とするものは「司法官」としてまた別にあるようだ。)
第二については、その司法官のことで、司法官は懲戒事由についての争いに裁定を下すものであるが、「彼はただ純すいに犯罪があったかなかったかを宣告するべき」とある。懲戒処分事案については会社の社会的信用に触れてあることも少なくなく、それは双方から提出された疎明資料からみても社会的信用失墜の証明自体法的に認定するのは困難である。しかし、懲戒事由とする以上主張等はされなければなるまい。心証事案ともいえる。
第三は「ざんぎゃくな刑罰」について触れてあり、それは社会的に不必要という理由だけでただ不正であるとしている。読み替えるとするならば、標準的な就業規則に則らない契約上の懲戒事項というものが巷にある。ノルマ未達成ならば〇〇、クレーム起したら〇〇などの類であり、労働条件通知書とは別に、誓約書というかたちで提出を入社時に求められるという類である。これらは必要でない不正なもので過剰な措置でしかない。日本的雇用は基本的に個人的な自由の享有と会社の秩序とが人生設計においてそれなりに組み合わせられているものであり、40年トータルで平準化されるという構想の下で成り立っていた。したがって、法定労働時間という規定はあまり意味をなさなかったといえ、またその分無理も効いた。それなりに個々に会社との関係において「貸し」「借り」の計算をしていたわけである。しかし現代労働事情はまた大正期の女工哀史の頃に戻ったかのような相談も多い。昭和式が否定されれば大正式、平成は何もできなかったのか。紛争解決はできるようになっているが、平成式というものがない。
《政治上のモラルは、それが人間の不滅の感情に基礎をおいたものでないかぎり、社会に対してなんの永続的な利益も与えることができない。
この人間の不滅の感情という基礎におかれていない法律はすべてつねに抵抗にあい、ついには打ちまかされなければならない運命にある。》
《そこでこれから、刑罰の起源と刑罰権の真の基礎とを発見するために考察をすすめていくにさいして、私はつねに人間の心情というものを考え合わせながらいきたいと思う。》
社会の永続性と人間の不滅の心情を基礎に置いたところが重要である。社会性の観点と合理性の観点とがまず出されている。
ここから所謂「原始自然状況」的なイメージが叙述されていく。ここはそのままだと会社秩序の説明にはならないので、労働者は個人的な自由の一部を会社に渡す契約を個々に行い、その管理を会社に行わせる。実際には、契約をはじめ就業規則制定権は会社にあるので「行わせる」とまで表現できないが、いったん契約および就業規則が成立すると、会社はそれらにつき優位する権利がある分だけの義務があるとするもので、それは秩序維持する権利と義務という合わせ鏡をもつ。
《各人にその自由の割り前をさし出させるように強制するものは、ただ一つその必要性だけである。》
証拠としては契約、就業規則であるが、その前提として「必要性」がある。それらの規定が会社秩序維持に際しての必要性の認定問題である。それが、懲戒権の基礎とする。
《この基礎を逸脱する刑罰権の行使は、すべて濫用であり、不正である。それは事実上の権力であっても、法にもとづいた権利ではない。》
『3 前章の原理からの帰結』
《右で述べた原理から次のように帰結される。
第一。法律だけがおのおのの犯罪に対する刑罰を規定することができる。》
裁判官は法律の規定により刑を科し、法律で規定されているより厳しい刑を科すことはできない。また、裁判官はいかなる理由からであっても既に宣告された刑を加重することはできない。これを「罪刑法定主義」という。二重処罰の禁止にも触れられている。懲戒処分についてはそのまま適用されている。ここでいう裁判官は無論、会社の懲罰指令責任者のことである。(なお、ベッカリーアによれば、我々が裁判官とするものは「司法官」としてまた別にあるようだ。)
第二については、その司法官のことで、司法官は懲戒事由についての争いに裁定を下すものであるが、「彼はただ純すいに犯罪があったかなかったかを宣告するべき」とある。懲戒処分事案については会社の社会的信用に触れてあることも少なくなく、それは双方から提出された疎明資料からみても社会的信用失墜の証明自体法的に認定するのは困難である。しかし、懲戒事由とする以上主張等はされなければなるまい。心証事案ともいえる。
第三は「ざんぎゃくな刑罰」について触れてあり、それは社会的に不必要という理由だけでただ不正であるとしている。読み替えるとするならば、標準的な就業規則に則らない契約上の懲戒事項というものが巷にある。ノルマ未達成ならば〇〇、クレーム起したら〇〇などの類であり、労働条件通知書とは別に、誓約書というかたちで提出を入社時に求められるという類である。これらは必要でない不正なもので過剰な措置でしかない。日本的雇用は基本的に個人的な自由の享有と会社の秩序とが人生設計においてそれなりに組み合わせられているものであり、40年トータルで平準化されるという構想の下で成り立っていた。したがって、法定労働時間という規定はあまり意味をなさなかったといえ、またその分無理も効いた。それなりに個々に会社との関係において「貸し」「借り」の計算をしていたわけである。しかし現代労働事情はまた大正期の女工哀史の頃に戻ったかのような相談も多い。昭和式が否定されれば大正式、平成は何もできなかったのか。紛争解決はできるようになっているが、平成式というものがない。