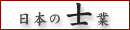13年09月13日
ドイツの解雇紛争処理実務 のコラムで
ドイツの解雇紛争処理実務に想う
JIL研究員 山本 陽大
《今年の7月に現地調査のためドイツへ出張した際、時間が空いたので、現地の弁護士に勧められ、労働裁判を傍聴しに行ってみた。》
《ドイツでは、労働裁判所法61a条という規定により、解雇事件については訴訟提起から2週間以内に和解手続(Güteverhandlung)を実施すべきこととされている。「ドイツにおける解雇事件は、その9割が裁判所での和解により終了している。」というのは日本でもよく知られた話であるが、現場はどうなっているのか、解雇法制の日独比較を研究対象としている筆者としては、大いに興味があった。》
《どの事件においても、裁判官(比較的若い、女性の裁判官であった。)が簡単に事実関係を確認したうえで、すぐに補償金(和解金)の支払いによる解決を当事者達に提案する。ここでの補償金額の算定について、法律上のルールはないが、実務では当該労働者の勤続年数×月給額×一定の係数(0.5~2.0、係数値は本人の年齢により変化する。)という算定式が確立しており、これに従って裁判官が電卓を叩き、金額を算出する。当事者達は、そのようにして算出された金額を前に、和解に応じるかどうかの話し合いを行うが、筆者が傍聴した6件中、1件を除いては、裁判官が提示した金額により和解が成立した(1件だけは、和解が成立せず判決手続へ移行したが、これは韓国系企業と韓国人労働者の間の解雇事件であった。)。短いものでは、1件の和解手続に15分もかかっていなかっただろう。》
《もっとも、このようなドイツにおける解雇紛争処理の実態は、法律のルールとはかなりかけ離れたものと映る。ドイツでは法律上、正当な理由の無い解雇は無効となり、労働者は原職復帰するのが原則とされ(解雇制限法1条)、極めて例外的な事案に限り金銭解決が可能とされている(同法9条および10条)(注1)。にもかかわらず、その実態は金銭解決による雇用の終了が、むしろ主流となっているのである。その点では、ドイツの解雇をめぐる「法の世界」と「事実の世界」は、乖離してしまっているともいえるだろう。》
《しかし、筆者は次のようにも考えた。確かに、「法の世界」と「事実の世界」は乖離しているけれども、法律のなかには、年齢が高い、あるいは勤続年数の長い労働者ほど、解雇から保護されるべきとの考え方に基づく規定が随所に登場する(例えば、解雇制限法1条5項、1a条および10条2項)。そして、このような法律のルールがあるからこそ、勤続年数と年齢を考慮要素に据えた補償金の算定式が、合理的で当事者らの納得も得られやすいものとして、和解実務上確立した地位を占めているのではないだろうか。言い換えれば、ドイツの解雇をめぐる「法の世界」には、「事実の世界」が一定程度安定的かつ合理的なものに落ち着くよう、下支えをしている側面があるのではないだろうか。》
《このように考えると、日本の問題点が浮かび上がってくる。日本では、労働契約法16条により解雇規制が行われているが、「それは、どのような労働者のどのような利益を守るためのものなのか?」、この点がいまひとつハッキリしていない。日本でもドイツと同様に、労契法16条自体は、違法解雇の法律効果を無効と定めているが、実務上解雇紛争の多くは、労働審判や紛争調整委員会のあっせんを通じて金銭解決により終了している(注2)。しかし、そこではドイツのような統一的な算定式などは存在せず、解決金額にもバラつきが見られるようである(注3)。日本でも、解雇の金銭解決制度の立法化が折に触れて話題となっているが、同制度を構想する際には、「そもそも解雇規制は、どのような労働者のどのような利益を守るためのものなのか?」という問題に立ち戻って検討する必要があるのではないだろうか…。》
ほぼ全文引用してしまうほど、この報告と感想は大事なポイントを突いていると思われた。
核心は、「法律のなかには、年齢が高い、あるいは勤続年数の長い労働者ほど、解雇から保護されるべきとの考え方に基づく規定が随所に登場する(例えば、解雇制限法1条5項、1a条および10条2項)。そして、このような法律のルールがあるからこそ、勤続年数と年齢を考慮要素に据えた補償金の算定式が、合理的で当事者らの納得も得られやすいものとして、和解実務上確立した地位を占めているのではないだろうか。」とする部分である。これはドイツ社会が共有する労働法の底に流れる思想と紛争処理形態との一致に気付いたというもので、文化思想的には「軍隊生活」について、かつて山本七平氏が指摘されたことと同じである。日本では、本当にあるべき制度形態が実行されているのかどうか。意見対立に止まる段階を超えて、本質的にあるべき形態を実現されうるのか。
尤も、そのドイツの法処理がドイツ国民の大多数に支持されているのか、それとも過半数をかろうじて超えている程度かを知る必要がある。隣の芝は青い類かの要確認。
JIL研究員 山本 陽大
《今年の7月に現地調査のためドイツへ出張した際、時間が空いたので、現地の弁護士に勧められ、労働裁判を傍聴しに行ってみた。》
《ドイツでは、労働裁判所法61a条という規定により、解雇事件については訴訟提起から2週間以内に和解手続(Güteverhandlung)を実施すべきこととされている。「ドイツにおける解雇事件は、その9割が裁判所での和解により終了している。」というのは日本でもよく知られた話であるが、現場はどうなっているのか、解雇法制の日独比較を研究対象としている筆者としては、大いに興味があった。》
《どの事件においても、裁判官(比較的若い、女性の裁判官であった。)が簡単に事実関係を確認したうえで、すぐに補償金(和解金)の支払いによる解決を当事者達に提案する。ここでの補償金額の算定について、法律上のルールはないが、実務では当該労働者の勤続年数×月給額×一定の係数(0.5~2.0、係数値は本人の年齢により変化する。)という算定式が確立しており、これに従って裁判官が電卓を叩き、金額を算出する。当事者達は、そのようにして算出された金額を前に、和解に応じるかどうかの話し合いを行うが、筆者が傍聴した6件中、1件を除いては、裁判官が提示した金額により和解が成立した(1件だけは、和解が成立せず判決手続へ移行したが、これは韓国系企業と韓国人労働者の間の解雇事件であった。)。短いものでは、1件の和解手続に15分もかかっていなかっただろう。》
《もっとも、このようなドイツにおける解雇紛争処理の実態は、法律のルールとはかなりかけ離れたものと映る。ドイツでは法律上、正当な理由の無い解雇は無効となり、労働者は原職復帰するのが原則とされ(解雇制限法1条)、極めて例外的な事案に限り金銭解決が可能とされている(同法9条および10条)(注1)。にもかかわらず、その実態は金銭解決による雇用の終了が、むしろ主流となっているのである。その点では、ドイツの解雇をめぐる「法の世界」と「事実の世界」は、乖離してしまっているともいえるだろう。》
《しかし、筆者は次のようにも考えた。確かに、「法の世界」と「事実の世界」は乖離しているけれども、法律のなかには、年齢が高い、あるいは勤続年数の長い労働者ほど、解雇から保護されるべきとの考え方に基づく規定が随所に登場する(例えば、解雇制限法1条5項、1a条および10条2項)。そして、このような法律のルールがあるからこそ、勤続年数と年齢を考慮要素に据えた補償金の算定式が、合理的で当事者らの納得も得られやすいものとして、和解実務上確立した地位を占めているのではないだろうか。言い換えれば、ドイツの解雇をめぐる「法の世界」には、「事実の世界」が一定程度安定的かつ合理的なものに落ち着くよう、下支えをしている側面があるのではないだろうか。》
《このように考えると、日本の問題点が浮かび上がってくる。日本では、労働契約法16条により解雇規制が行われているが、「それは、どのような労働者のどのような利益を守るためのものなのか?」、この点がいまひとつハッキリしていない。日本でもドイツと同様に、労契法16条自体は、違法解雇の法律効果を無効と定めているが、実務上解雇紛争の多くは、労働審判や紛争調整委員会のあっせんを通じて金銭解決により終了している(注2)。しかし、そこではドイツのような統一的な算定式などは存在せず、解決金額にもバラつきが見られるようである(注3)。日本でも、解雇の金銭解決制度の立法化が折に触れて話題となっているが、同制度を構想する際には、「そもそも解雇規制は、どのような労働者のどのような利益を守るためのものなのか?」という問題に立ち戻って検討する必要があるのではないだろうか…。》
ほぼ全文引用してしまうほど、この報告と感想は大事なポイントを突いていると思われた。
核心は、「法律のなかには、年齢が高い、あるいは勤続年数の長い労働者ほど、解雇から保護されるべきとの考え方に基づく規定が随所に登場する(例えば、解雇制限法1条5項、1a条および10条2項)。そして、このような法律のルールがあるからこそ、勤続年数と年齢を考慮要素に据えた補償金の算定式が、合理的で当事者らの納得も得られやすいものとして、和解実務上確立した地位を占めているのではないだろうか。」とする部分である。これはドイツ社会が共有する労働法の底に流れる思想と紛争処理形態との一致に気付いたというもので、文化思想的には「軍隊生活」について、かつて山本七平氏が指摘されたことと同じである。日本では、本当にあるべき制度形態が実行されているのかどうか。意見対立に止まる段階を超えて、本質的にあるべき形態を実現されうるのか。
尤も、そのドイツの法処理がドイツ国民の大多数に支持されているのか、それとも過半数をかろうじて超えている程度かを知る必要がある。隣の芝は青い類かの要確認。
13年08月14日
退職の仕方
労働契約法では退職の仕方について規定されていないので、従来どおり民法による。
《民法第627条
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。》
第1項がほとんど適用される。
第2項は「完全月給制」に適用されるそうである。この2項について詳しく書かれたものは未だ読んだことは無く、また争われることにより判決に明快に書かれたことも無いみたいなので、継続で調べることとしておく。
第3項は「年俸制」に適用されると解説されている。この「年俸制」についても、実態としてみた場合、争われる可能性はあるだろうと思う。
さて、期間の定めのある契約は当然その期間に重点を置いた契約であるから、その期間につき労使は縛られるものであるが、実情は、単に更新の機会を設けているだけというものが多く、期間の定めの無い契約同様、使用者はいつでも解約(解雇)するという認識が強い。したがって、判例の多くは、雇い止め法理でなく、解雇権濫用法理に基いてなされる。どちらもさほど違いは無いといえばそう言えるほど、「期間」に実際は重点が置かれていないというものであり、むしろ純粋な期間契約がイメージできないのが普通である。
それはそれとして、
期間の定めのない契約は、上記の627条による。長らく、といってももはや2世代程度であった「終身雇用制」神話に隠れていた条項であるが、それも崩れ落ち、各企業において、箍が外れたように、退職転職解雇が乱発されている。
そこで辞め方なのであるが、
たいてい就業規則等において、退職の日の〇日前に届け出ること、とされているのであるが、その通りいけばそれで終わる。円満退職である。引継ぎ有休消化の関係で、日にちにつき別途合意することも多い。
ただ、円満でないこともあるわけで、そのときに上記627条1項の適用となる。この適用で重要なことは、強行規定とされていることである。したがって、使用者の一方的な解除権行使である解雇の逆で、労働者から一方的に行うものとされる。なお、それから2週間は労働義務がある。使用者の理解が到底得られそうも無いときは、日にちの保全のため、内容証明配達証明付き退職届を送ることまで必要である。
また、医師の診断書により安静を要する状態であれば、使用者はそれを冒してまで労働を要求する権利はない。ほとんど適用がなくなっている強制労働規定をわざわざ眠りから起こすこともあるまい。
しかしいくら退職転職解雇が高水準(少し言い過ぎとも思いながら…)にあるといえ、長く居た人物や役職者が2週間でいなくなるというのはキツイ話である。2週間で代りが見つかるのが雇用契約、労働者というもの、とそこまで表現してはいないが、現行法ではそういうことになる。特に当規定について改正要求も聞かない。
《民法第627条
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。》
第1項がほとんど適用される。
第2項は「完全月給制」に適用されるそうである。この2項について詳しく書かれたものは未だ読んだことは無く、また争われることにより判決に明快に書かれたことも無いみたいなので、継続で調べることとしておく。
第3項は「年俸制」に適用されると解説されている。この「年俸制」についても、実態としてみた場合、争われる可能性はあるだろうと思う。
さて、期間の定めのある契約は当然その期間に重点を置いた契約であるから、その期間につき労使は縛られるものであるが、実情は、単に更新の機会を設けているだけというものが多く、期間の定めの無い契約同様、使用者はいつでも解約(解雇)するという認識が強い。したがって、判例の多くは、雇い止め法理でなく、解雇権濫用法理に基いてなされる。どちらもさほど違いは無いといえばそう言えるほど、「期間」に実際は重点が置かれていないというものであり、むしろ純粋な期間契約がイメージできないのが普通である。
それはそれとして、
期間の定めのない契約は、上記の627条による。長らく、といってももはや2世代程度であった「終身雇用制」神話に隠れていた条項であるが、それも崩れ落ち、各企業において、箍が外れたように、退職転職解雇が乱発されている。
そこで辞め方なのであるが、
たいてい就業規則等において、退職の日の〇日前に届け出ること、とされているのであるが、その通りいけばそれで終わる。円満退職である。引継ぎ有休消化の関係で、日にちにつき別途合意することも多い。
ただ、円満でないこともあるわけで、そのときに上記627条1項の適用となる。この適用で重要なことは、強行規定とされていることである。したがって、使用者の一方的な解除権行使である解雇の逆で、労働者から一方的に行うものとされる。なお、それから2週間は労働義務がある。使用者の理解が到底得られそうも無いときは、日にちの保全のため、内容証明配達証明付き退職届を送ることまで必要である。
また、医師の診断書により安静を要する状態であれば、使用者はそれを冒してまで労働を要求する権利はない。ほとんど適用がなくなっている強制労働規定をわざわざ眠りから起こすこともあるまい。
しかしいくら退職転職解雇が高水準(少し言い過ぎとも思いながら…)にあるといえ、長く居た人物や役職者が2週間でいなくなるというのはキツイ話である。2週間で代りが見つかるのが雇用契約、労働者というもの、とそこまで表現してはいないが、現行法ではそういうことになる。特に当規定について改正要求も聞かない。
13年07月01日
労働社会諸法令、労務管理、紛争解決
会社で有望な資格として「社会保険労務士」は依然として人気があるが、なかなかプロになることは難しい資格でもある。そのため、専門学校での社会保険労務士講座はトラブルが多い。
まず範囲が広いということ、おまけに各項目にわたって細かな行政取扱があること、次に実務的な正確さ(そこにも細かな取扱いがある)が問われること、そして常に諸法の改正について研修しておく必要があること。したがって、一コマ〔一科目ではない〕に1人、講師を配置するような必要があるのだが、当然ながら、学校としてはそこまで手配する余裕がないし、社会保険労務士講座だけ特別視もできないと。
私の受験の頃なら、合格が目標で、わからにくい所には時間を割かないで「捨てる」ということでやっていたものが、最近の学生は、全部にわたって正確な知識を要求するというお門違いが当たり前のようになっていて、昔なら「捨てる」所の質問をして、講師を困らせ、答えられなければクレームに発展する。
自分のための勉強だが、自分で調べるという発想もなく、ただわからない所を聞き、答えられなければ失格者の印を押すという本末転倒が起っている。独立資格に挑戦する姿勢ではなく、鵜飼いの鵜のような立場として自己認識しているという最初の構えがまちがっているのである。こうしたものは自然、講師が教えるもとなっているが、本来は開講する学校で教えるべきものである。
そんなわけで、私は講師というものは、「調べ方」であるとか、学生が自分自身で情報を得たり加工したりする自己判断能力を身につけさせるよう努力するだけに集中し、内容そのものは触れる必要のないものと考える。学生自身のそれぞれの科目等についての知識欲などを刺激させれば足りると。
こうなるのはそれぞれの学生が、労働社会諸法令、労務管理、紛争解決に対して、どれくらい自分としての欲を持っているか、の「欲」がないからなのである。自分の欲がないから、講師批判で溜飲を下げる。しかして、自分の力に何もなっていない。講師が語った以上に、自分で調べたか、必要のないところまで手を伸ばしたのか。今の社労士の業務においては、民法のこと、裁判のこと、取締役のことに始まり、相当広くて適確妥当な情報が必要であるが、そうしたことも想像できず、ただ講師が言ったことだけで済ませていないか。
社労士はやればやるほど大変で、なかなか一人前になるには難しい資格なのである。最初からオールラウンドは無理であることは勿論で、マイナーなことを一つ一つ経験していつの間にかオールラウンドになっていたというのが理想。
弁護士からは必ず「社労士さんは勉強熱心ですねぇ」と言われるのであるが、そうならざるを得ない資格だということである。退屈はしないが、しんどい資格の一つであることの事実。何でもそれぞれ特色というものがある。紛争を手がけることとなり、従来からしている手続きも単なる事務的な意味はなくなっており、契約関係の清算の話もよく聞えてきている。したがって、社会に対して社労士の「欲」が出やすくなっている環境にある。だからこそ、社労士を目指そうとする者に、「欲」をもっていないという者がほとんどいないということに、ちょっとどうなのかなと思う次第である。無論、その状態ではまず受かる試験ではないのだけれど。
まず範囲が広いということ、おまけに各項目にわたって細かな行政取扱があること、次に実務的な正確さ(そこにも細かな取扱いがある)が問われること、そして常に諸法の改正について研修しておく必要があること。したがって、一コマ〔一科目ではない〕に1人、講師を配置するような必要があるのだが、当然ながら、学校としてはそこまで手配する余裕がないし、社会保険労務士講座だけ特別視もできないと。
私の受験の頃なら、合格が目標で、わからにくい所には時間を割かないで「捨てる」ということでやっていたものが、最近の学生は、全部にわたって正確な知識を要求するというお門違いが当たり前のようになっていて、昔なら「捨てる」所の質問をして、講師を困らせ、答えられなければクレームに発展する。
自分のための勉強だが、自分で調べるという発想もなく、ただわからない所を聞き、答えられなければ失格者の印を押すという本末転倒が起っている。独立資格に挑戦する姿勢ではなく、鵜飼いの鵜のような立場として自己認識しているという最初の構えがまちがっているのである。こうしたものは自然、講師が教えるもとなっているが、本来は開講する学校で教えるべきものである。
そんなわけで、私は講師というものは、「調べ方」であるとか、学生が自分自身で情報を得たり加工したりする自己判断能力を身につけさせるよう努力するだけに集中し、内容そのものは触れる必要のないものと考える。学生自身のそれぞれの科目等についての知識欲などを刺激させれば足りると。
こうなるのはそれぞれの学生が、労働社会諸法令、労務管理、紛争解決に対して、どれくらい自分としての欲を持っているか、の「欲」がないからなのである。自分の欲がないから、講師批判で溜飲を下げる。しかして、自分の力に何もなっていない。講師が語った以上に、自分で調べたか、必要のないところまで手を伸ばしたのか。今の社労士の業務においては、民法のこと、裁判のこと、取締役のことに始まり、相当広くて適確妥当な情報が必要であるが、そうしたことも想像できず、ただ講師が言ったことだけで済ませていないか。
社労士はやればやるほど大変で、なかなか一人前になるには難しい資格なのである。最初からオールラウンドは無理であることは勿論で、マイナーなことを一つ一つ経験していつの間にかオールラウンドになっていたというのが理想。
弁護士からは必ず「社労士さんは勉強熱心ですねぇ」と言われるのであるが、そうならざるを得ない資格だということである。退屈はしないが、しんどい資格の一つであることの事実。何でもそれぞれ特色というものがある。紛争を手がけることとなり、従来からしている手続きも単なる事務的な意味はなくなっており、契約関係の清算の話もよく聞えてきている。したがって、社会に対して社労士の「欲」が出やすくなっている環境にある。だからこそ、社労士を目指そうとする者に、「欲」をもっていないという者がほとんどいないということに、ちょっとどうなのかなと思う次第である。無論、その状態ではまず受かる試験ではないのだけれど。
13年06月15日
ダイヤモンド・オンラインから雇用制度改革議論
いまなぜ解雇規制の緩和なのか その背景&論点を整理する
ヤフーの記事もある程度まとまったものを載せるようになった。
《「正社員」とは仕事内容を限定しない、期間の定めのない雇用契約で働いている社員、「非正規社員」は仕事内容を限定した契約社員や、パートタイマー・アルバイト・派遣社員などのように期間を定めた雇用契約で働いている社員を指す。言い換えれば、安定的な雇用と相対的な高賃金を代償に、転勤・残業もいとわない無限定な労働を強いられるのが正社員で、正社員ほど無限定な労働は強いられないものの、雇用は不安定で賃金は低いというのが非正規社員と言えるだろう。》
労働問題はなかなか簡単ではない。企業規模が違えば、大資本なら大資本の問題があるし、小資本は小資本の問題がある。また、業種が違えば、それぞれ固有の問題を抱える。さらに会社や支店、部署の色合い、上司そして同僚と部下、取引先などの人間関係があり、労働法やその関連法規だけではカバーされておらず、労働契約法と民法一般原則まで総動員してこなければならず、そしてその範囲は入社の経緯から始まり事件化するまでに至る過程がある。また、そうした事実の認定は、意識下に置くまでの間、なおざりであるのが普通で、証拠がなければ(こうなるんであったら…)、証拠があれば(初めからそのつもりだったのか、もはや信用できない)といった体になる。
上の記述においても、パートは時間管理による賃金計算と結びついているだけに時間外労働や有休の支払は履行される傾向があるが、正社員の基本給は時間管理とは直接的な性質ではないためということである。法的にそれは理由にならず、「名ばかり管理職」などその違法性は認識されたが、さりとて人事管理手法の改良にまで及んだといえる状態ではなさそうである。
《非正規社員は一般的には正社員よりも短い時間で働くことが多い一方で、待遇面で正社員と大きな格差がある。例えば、給与が少ない(退職金、ボーナスがない)、雇用が不安定、キャリアアップがしづらい、といった点だ。》
パート労働法がたまに話題になるものの、法体系において中心的な存在とはまだいえない。日本史において、「男性社会」を崩さずに「女性労働者」を使う蜜月があったが、家庭における大黒柱である中高年齢層のリストラ、若年者の就職難、女性の社会進出、少子高齢化により、また均等法の推進で、ここにきて既に六割以上程度は労働の現場は崩れたといっていいと思われる。団塊の世代も去る今日、すべてにおいて不安定な環境しか見えていないだろう。言い換えれば、もう終身雇用制を経験したことのない(知らない)世代が多数を占めつつあり、その職場は不安定以外何ものでもなく、痴話喧嘩のような騒ぎで事件化するのがオチである。したがって、アベノミクスの雇用対策はまだ玄関先での話に過ぎない。どちらかといえば、目下の議題では法対象を特定のものに限定するのがよいと思うほどだ。なお歴史の観点では整理が必要な時期に入っているものと感ずる。
《「整理解雇の4要件」(人員整理の必要性、解雇回避努力義務の履行、対象者の人選の合理性、手続きの妥当性)から、その妥当性が判断されることになっている。》
整理解雇が認められた判例から、「限定正社員」ということなのだが、これまた果たして法による認定作業を免れるとも思えない。「地域や職種、労働時間を限定して採用した場合、その仕事がなくなれば解雇できるという契約」を予定しているが、そうした人事権を制限した契約がそれほど必要かどうか。「その仕事がなくなれば」という要件もまたすこぶるクリアすることが難しく思われる。結局、権利の濫用法理を使わざるを得ないのではないか。無論、適用がピタッと嵌るものもあるだろうが、割合として実際のところ少ない
と思われる。特定の業種に偏るのであれば、まずは法対象を限定あるいは特定するのが手順としてふさわしい。
《政府は参院選を意識してか、最も大きなこの問題を正面から取り上げず、金銭による解雇、限定社員という個別論から入ろうとしている。》
うん?私が以前見た記事では、金銭解決解雇は選挙を考慮して外したものであった。なお、金銭解決解雇は労働側では歓迎する向きもあり、その法制化を今度は使用者側が嫌い始めたようにも思われる。
結論として、もはや「三種の神器」の時代を知らぬ経営者も労働者も多く存在するようになり、それぞれ目前の事しか視界に入っていない。それぞれの倫理観も薄れている。『美しい国』―未読なので言葉のイメージだけ―を書いた首相なだけに、グランドビジョンを望む。
ヤフーの記事もある程度まとまったものを載せるようになった。
《「正社員」とは仕事内容を限定しない、期間の定めのない雇用契約で働いている社員、「非正規社員」は仕事内容を限定した契約社員や、パートタイマー・アルバイト・派遣社員などのように期間を定めた雇用契約で働いている社員を指す。言い換えれば、安定的な雇用と相対的な高賃金を代償に、転勤・残業もいとわない無限定な労働を強いられるのが正社員で、正社員ほど無限定な労働は強いられないものの、雇用は不安定で賃金は低いというのが非正規社員と言えるだろう。》
労働問題はなかなか簡単ではない。企業規模が違えば、大資本なら大資本の問題があるし、小資本は小資本の問題がある。また、業種が違えば、それぞれ固有の問題を抱える。さらに会社や支店、部署の色合い、上司そして同僚と部下、取引先などの人間関係があり、労働法やその関連法規だけではカバーされておらず、労働契約法と民法一般原則まで総動員してこなければならず、そしてその範囲は入社の経緯から始まり事件化するまでに至る過程がある。また、そうした事実の認定は、意識下に置くまでの間、なおざりであるのが普通で、証拠がなければ(こうなるんであったら…)、証拠があれば(初めからそのつもりだったのか、もはや信用できない)といった体になる。
上の記述においても、パートは時間管理による賃金計算と結びついているだけに時間外労働や有休の支払は履行される傾向があるが、正社員の基本給は時間管理とは直接的な性質ではないためということである。法的にそれは理由にならず、「名ばかり管理職」などその違法性は認識されたが、さりとて人事管理手法の改良にまで及んだといえる状態ではなさそうである。
《非正規社員は一般的には正社員よりも短い時間で働くことが多い一方で、待遇面で正社員と大きな格差がある。例えば、給与が少ない(退職金、ボーナスがない)、雇用が不安定、キャリアアップがしづらい、といった点だ。》
パート労働法がたまに話題になるものの、法体系において中心的な存在とはまだいえない。日本史において、「男性社会」を崩さずに「女性労働者」を使う蜜月があったが、家庭における大黒柱である中高年齢層のリストラ、若年者の就職難、女性の社会進出、少子高齢化により、また均等法の推進で、ここにきて既に六割以上程度は労働の現場は崩れたといっていいと思われる。団塊の世代も去る今日、すべてにおいて不安定な環境しか見えていないだろう。言い換えれば、もう終身雇用制を経験したことのない(知らない)世代が多数を占めつつあり、その職場は不安定以外何ものでもなく、痴話喧嘩のような騒ぎで事件化するのがオチである。したがって、アベノミクスの雇用対策はまだ玄関先での話に過ぎない。どちらかといえば、目下の議題では法対象を特定のものに限定するのがよいと思うほどだ。なお歴史の観点では整理が必要な時期に入っているものと感ずる。
《「整理解雇の4要件」(人員整理の必要性、解雇回避努力義務の履行、対象者の人選の合理性、手続きの妥当性)から、その妥当性が判断されることになっている。》
整理解雇が認められた判例から、「限定正社員」ということなのだが、これまた果たして法による認定作業を免れるとも思えない。「地域や職種、労働時間を限定して採用した場合、その仕事がなくなれば解雇できるという契約」を予定しているが、そうした人事権を制限した契約がそれほど必要かどうか。「その仕事がなくなれば」という要件もまたすこぶるクリアすることが難しく思われる。結局、権利の濫用法理を使わざるを得ないのではないか。無論、適用がピタッと嵌るものもあるだろうが、割合として実際のところ少ない
と思われる。特定の業種に偏るのであれば、まずは法対象を限定あるいは特定するのが手順としてふさわしい。
《政府は参院選を意識してか、最も大きなこの問題を正面から取り上げず、金銭による解雇、限定社員という個別論から入ろうとしている。》
うん?私が以前見た記事では、金銭解決解雇は選挙を考慮して外したものであった。なお、金銭解決解雇は労働側では歓迎する向きもあり、その法制化を今度は使用者側が嫌い始めたようにも思われる。
結論として、もはや「三種の神器」の時代を知らぬ経営者も労働者も多く存在するようになり、それぞれ目前の事しか視界に入っていない。それぞれの倫理観も薄れている。『美しい国』―未読なので言葉のイメージだけ―を書いた首相なだけに、グランドビジョンを望む。
13年05月29日
経団連の提言
経団連は四月一六日、提言『労働者の活躍と企業の成長を促す労働法制』
《提言では、雇用の維持・創出を図るには、労働者保護の政策だけでなく、企業の事業活
動の柔軟性確保や多様な就業機会の創出の観点を重視し、バランスのとれた政策としていくことが不可欠だと強調。そのうえで、労働者が働きやすく、透明性の高い労働法制に向けた具体策として、①労使自治を重視した労働時間法制改革、②勤務地・職種限定契約に
対する雇用保障責任ルールの透明化、③労使自治を重視した労働条件の変更ルールの透明化――を求めている。》
《提言では、現在の雇用問題を解決するためには、企業活動の活性化に支えられた経済全体の成長が必要だと主張。企業が将来にわたり国内事業を継続できる環境をより確かなものとするため、労働規制の見直しを一気に実施する必要があるとしている。》
内容に関してはめいめいで読んでもらうことにして、全国一律の国家法制への提言であるからそろそろ使用者の連合としての統制についても触れてもらいたいものだと思った次第である。労組団体ほか有識者連中が危惧している部分についてまったく触れておらず、それについてどういう考えであり、どういう対処を行うのかまでが、そろそろ必要な話ではなかろうか。無論、そうした法的権限はないが、内部統制は可能であり、その部分が自己で解決されてない限り、提言としての説得力に欠けてしまっている。言いっ放しでいいのならともかく。もう少し中で詰めておいてもらってから、である。
ページ移動
前へ
1,2, ... ,10,11,12, ... ,36,37
次へ
Page 11 of 37
《提言では、雇用の維持・創出を図るには、労働者保護の政策だけでなく、企業の事業活
動の柔軟性確保や多様な就業機会の創出の観点を重視し、バランスのとれた政策としていくことが不可欠だと強調。そのうえで、労働者が働きやすく、透明性の高い労働法制に向けた具体策として、①労使自治を重視した労働時間法制改革、②勤務地・職種限定契約に
対する雇用保障責任ルールの透明化、③労使自治を重視した労働条件の変更ルールの透明化――を求めている。》
《提言では、現在の雇用問題を解決するためには、企業活動の活性化に支えられた経済全体の成長が必要だと主張。企業が将来にわたり国内事業を継続できる環境をより確かなものとするため、労働規制の見直しを一気に実施する必要があるとしている。》
内容に関してはめいめいで読んでもらうことにして、全国一律の国家法制への提言であるからそろそろ使用者の連合としての統制についても触れてもらいたいものだと思った次第である。労組団体ほか有識者連中が危惧している部分についてまったく触れておらず、それについてどういう考えであり、どういう対処を行うのかまでが、そろそろ必要な話ではなかろうか。無論、そうした法的権限はないが、内部統制は可能であり、その部分が自己で解決されてない限り、提言としての説得力に欠けてしまっている。言いっ放しでいいのならともかく。もう少し中で詰めておいてもらってから、である。