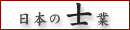07年12月28日
遺留分
1 遺留分は、被相続人が死亡して、相続が開始したときに、それまでたとえ
被相続人が自分の財産を既に処分していたとしても、相続財産の最小限度
だけは一定の近親者に確保しておくべきであるという要請により、一定範囲
の相続人に留保された相続財産の一定割合をいう。
2 遺留分を有する相続人は、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、配偶者、
子、直系尊属である。
そして、遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続
人の財産の3分の1であり、その他の場合には、被相続人の財産の2分の1
である。
3 遺留分規定に反する相続分の指定や包括遺贈の効力はどうなるか。
これについては、遺留分を侵害する行為も、当然には無効とはならず、減
殺請求(遺留分を保留するため、これを侵害する贈与や遺贈を否認すること)
ができるだけであると解されています。
したがって、遺留分規定に反する相続分の指定や包括遺贈も、一応効果は
生じ、減殺請求がされたときは、遺留分を侵害する範囲でその効果が失われ
ることになります。
4 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができません。
また、贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してします。
そして、減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、
遺留分権利者にその価額を弁償しなければなりません。
受贈者・受遺者は、常に目的物を返還しなければならないのではなく、減殺
を受けるべき限度において、贈与・遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償
して、返還の義務を免れることができます。
5 減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈が
あったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
相続開始のときから10年を経過したときも同様です。
6 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに
限り、その効力を生じます。相続の放棄は、相続開始後でなければ認められな
いのと異なります。
共同相続人の一人がした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影
響を及ぼしません。したがって、配偶者と子供2人が相続人であった場合におい
て、子供の一人が遺留分を放棄したとき、配偶者の遺留分は4分の1、遺留分を
放棄しなかった子供のそれは8分の1であり、4分の1になるのではありません。
被相続人が自分の財産を既に処分していたとしても、相続財産の最小限度
だけは一定の近親者に確保しておくべきであるという要請により、一定範囲
の相続人に留保された相続財産の一定割合をいう。
2 遺留分を有する相続人は、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち、配偶者、
子、直系尊属である。
そして、遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続
人の財産の3分の1であり、その他の場合には、被相続人の財産の2分の1
である。
3 遺留分規定に反する相続分の指定や包括遺贈の効力はどうなるか。
これについては、遺留分を侵害する行為も、当然には無効とはならず、減
殺請求(遺留分を保留するため、これを侵害する贈与や遺贈を否認すること)
ができるだけであると解されています。
したがって、遺留分規定に反する相続分の指定や包括遺贈も、一応効果は
生じ、減殺請求がされたときは、遺留分を侵害する範囲でその効果が失われ
ることになります。
4 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができません。
また、贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してします。
そして、減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、
遺留分権利者にその価額を弁償しなければなりません。
受贈者・受遺者は、常に目的物を返還しなければならないのではなく、減殺
を受けるべき限度において、贈与・遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償
して、返還の義務を免れることができます。
5 減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈が
あったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
相続開始のときから10年を経過したときも同様です。
6 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに
限り、その効力を生じます。相続の放棄は、相続開始後でなければ認められな
いのと異なります。
共同相続人の一人がした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影
響を及ぼしません。したがって、配偶者と子供2人が相続人であった場合におい
て、子供の一人が遺留分を放棄したとき、配偶者の遺留分は4分の1、遺留分を
放棄しなかった子供のそれは8分の1であり、4分の1になるのではありません。
07年12月27日
遺言の撤回
1 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部
を撤回することができます。
ただ、撤回される遺言と撤回後の遺言は同一の方式であることを要しな
いので、例えば、公正証書でされた遺言を自筆証書遺言をもって撤回す
ることも可能です。
また、前の遺言と後の遺言が抵触するときは、その抵触する部分につい
ては、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。遺言者の最終
意思を実現するために撤回を擬制するわけです。
さらに遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分につい
ては、遺言を撤回したものとみなされます。
2 遺言が撤回されると、遺言は初めからなかったと同様の結果になる。
では、撤回行為がさらに撤回され、またはそれが効力を失った場合には、
先に撤回された遺言が復活するかが問題となります。
この点、民法は、復活しないという主義を採用しています。通常の場合の
遺言者の意思に適するであろうし、反対の効果を望む者には改めて遺言の
作成を要求した方が、遺言者の真意を明確にするからです。
ただし、第1の遺言を第2の遺言によって撤回した遺言者が、さらに第3の
遺言によって第2の遺言を撤回した場合に、第3の遺言書の記載に照らし、
遺言者の意思が第1の遺言の復活を希望することが明らかなときは、遺言
者の真意を尊重して、第1の遺言の効力の復活を認める判例があることに
注意を要します。
3 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができません。遺言は
遺言者の最終の意思を実現しようとするものであるから、遺言は自由に撤回
できるものとしておかなければならないからです。
したがって、仮に、推定相続人との間で遺言の撤回をしない旨を約束したと
しても、それに拘束されることなく、遺言者は遺言を撤回することができます。
を撤回することができます。
ただ、撤回される遺言と撤回後の遺言は同一の方式であることを要しな
いので、例えば、公正証書でされた遺言を自筆証書遺言をもって撤回す
ることも可能です。
また、前の遺言と後の遺言が抵触するときは、その抵触する部分につい
ては、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。遺言者の最終
意思を実現するために撤回を擬制するわけです。
さらに遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分につい
ては、遺言を撤回したものとみなされます。
2 遺言が撤回されると、遺言は初めからなかったと同様の結果になる。
では、撤回行為がさらに撤回され、またはそれが効力を失った場合には、
先に撤回された遺言が復活するかが問題となります。
この点、民法は、復活しないという主義を採用しています。通常の場合の
遺言者の意思に適するであろうし、反対の効果を望む者には改めて遺言の
作成を要求した方が、遺言者の真意を明確にするからです。
ただし、第1の遺言を第2の遺言によって撤回した遺言者が、さらに第3の
遺言によって第2の遺言を撤回した場合に、第3の遺言書の記載に照らし、
遺言者の意思が第1の遺言の復活を希望することが明らかなときは、遺言
者の真意を尊重して、第1の遺言の効力の復活を認める判例があることに
注意を要します。
3 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができません。遺言は
遺言者の最終の意思を実現しようとするものであるから、遺言は自由に撤回
できるものとしておかなければならないからです。
したがって、仮に、推定相続人との間で遺言の撤回をしない旨を約束したと
しても、それに拘束されることなく、遺言者は遺言を撤回することができます。
07年12月26日
遺言の執行
1 遺言書の保管者は、公正証書遺言以外については相続の開始を
知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」を受け
なければなりません。
検認は、遺言書の形式その他の状態を調査確認し、その保存を
確実にするための一種の形式的な検証手続ないし証拠保全手続
であって、実質的な遺言内容の真否や効力の有無を判定するもの
ではありません。したがって、検認を受けなければ遺言が効力を生
じないということはなく、また逆に検認の手続を経た遺言書であって
も、後にその効力の有無を裁判で争うことができます。
2 また封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその
代理人の立会いがなければ、開封することができません。
3 検認を経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で開封をした者
は、5万円以下の過料に処せられます。
4 遺言者は、遺言で、遺言執行者を指定することができます。もっとも、
未成年者と破産者は、遺言執行者となることができません。
(1)遺言執行者は、民法では相続人の代理人とみなしているが、これで
は相続人廃除のような遺言の執行を説明することができない。かといっ
て 死亡により法人格を失っている遺言者の代理人であるとするのも形
式的には困難である。論理的には、遺言者の人格の残影を代表するも
のと見ざるを得ないと思われます。
(2)遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の
行為をする権利義務を有します。そのため、遺言執行者がある場合に
は、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるような行為
をすることができません。
したがって、遺言執行者がある場合、相続人が相続財産につきした処
分行為は、絶対無効となります。例えば、遺言執行者がある場合に、相
続人が遺贈の目的不動産を第三者に譲渡し、またはこれに第三者のた
めに抵当権を設定して登記をしたとしても、相続人の当該行為は無効で
あり、受遺者は、遺贈による目的不動産の所有権取得を登記なくして、
当該処分行為の相手方たる第三者に対抗することができます。
知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」を受け
なければなりません。
検認は、遺言書の形式その他の状態を調査確認し、その保存を
確実にするための一種の形式的な検証手続ないし証拠保全手続
であって、実質的な遺言内容の真否や効力の有無を判定するもの
ではありません。したがって、検認を受けなければ遺言が効力を生
じないということはなく、また逆に検認の手続を経た遺言書であって
も、後にその効力の有無を裁判で争うことができます。
2 また封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその
代理人の立会いがなければ、開封することができません。
3 検認を経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で開封をした者
は、5万円以下の過料に処せられます。
4 遺言者は、遺言で、遺言執行者を指定することができます。もっとも、
未成年者と破産者は、遺言執行者となることができません。
(1)遺言執行者は、民法では相続人の代理人とみなしているが、これで
は相続人廃除のような遺言の執行を説明することができない。かといっ
て 死亡により法人格を失っている遺言者の代理人であるとするのも形
式的には困難である。論理的には、遺言者の人格の残影を代表するも
のと見ざるを得ないと思われます。
(2)遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の
行為をする権利義務を有します。そのため、遺言執行者がある場合に
は、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるような行為
をすることができません。
したがって、遺言執行者がある場合、相続人が相続財産につきした処
分行為は、絶対無効となります。例えば、遺言執行者がある場合に、相
続人が遺贈の目的不動産を第三者に譲渡し、またはこれに第三者のた
めに抵当権を設定して登記をしたとしても、相続人の当該行為は無効で
あり、受遺者は、遺贈による目的不動産の所有権取得を登記なくして、
当該処分行為の相手方たる第三者に対抗することができます。
07年12月25日
遺言の効力
1 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じます。
もっとも、遺言に停止条件を付した場合には、遺言者死亡後に条件が
成就した時に生じます。
2 遺言による財産の無償譲与である遺贈には、特定遺贈と包括遺贈と
がある。前者は、特定の具体的な財産的利益の遺贈であり、後者は、
積極・消極の財産を包括する相続財産の全部またはその分数的割合
による遺贈である。
両者はその効力において全く異なるので、注意が必要です。
(1)共通点は、自然人だけでなく、法人も受遺者(遺贈を受ける者とし
て遺言中に指定されている者)になれるし、また遺言者の相続人も
受遺者になれるところです。
ただ、受遺者は遺言が効力を生じた時、つまり遺言者が死亡した時
に生存していなければなりません。遺言者の死亡以前に受遺者が死
亡した場合には、受遺者たる地位の承継は認められませんから、遺贈
は効力を生じません。したがって、受遺者の相続人に承継させるために
は、遺言中に特に受遺者の相続人に承継を認める旨を表示する必要が
あります(補充遺贈)。
(2)特定遺贈においては、受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放
棄をすることができます。しかし、包括遺贈では、包括受遺者は相続人と
同一の権利義務を有するものとされるため、受遺者が自己のために遺贈
のあったことを知った時から3箇月以内に限って放棄することができます。
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するといっても、相続人に
なるのではありません。したがって、遺留分を有しないし、前述のように受
遺者が相続開始以前に死亡した場合には、代襲相続が認められる相続と
異なり、原則として、遺贈が失効するのです。
もっとも、遺言に停止条件を付した場合には、遺言者死亡後に条件が
成就した時に生じます。
2 遺言による財産の無償譲与である遺贈には、特定遺贈と包括遺贈と
がある。前者は、特定の具体的な財産的利益の遺贈であり、後者は、
積極・消極の財産を包括する相続財産の全部またはその分数的割合
による遺贈である。
両者はその効力において全く異なるので、注意が必要です。
(1)共通点は、自然人だけでなく、法人も受遺者(遺贈を受ける者とし
て遺言中に指定されている者)になれるし、また遺言者の相続人も
受遺者になれるところです。
ただ、受遺者は遺言が効力を生じた時、つまり遺言者が死亡した時
に生存していなければなりません。遺言者の死亡以前に受遺者が死
亡した場合には、受遺者たる地位の承継は認められませんから、遺贈
は効力を生じません。したがって、受遺者の相続人に承継させるために
は、遺言中に特に受遺者の相続人に承継を認める旨を表示する必要が
あります(補充遺贈)。
(2)特定遺贈においては、受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放
棄をすることができます。しかし、包括遺贈では、包括受遺者は相続人と
同一の権利義務を有するものとされるため、受遺者が自己のために遺贈
のあったことを知った時から3箇月以内に限って放棄することができます。
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するといっても、相続人に
なるのではありません。したがって、遺留分を有しないし、前述のように受
遺者が相続開始以前に死亡した場合には、代襲相続が認められる相続と
異なり、原則として、遺贈が失効するのです。
07年12月21日
秘密証書遺言
1 自筆証書遺言と公正証書遺言の功罪は順次述べてきたが、その中間
を行くものとして秘密証書遺言があります。すなわち、秘密証書遺言は、
遺言書の存在は明確にしながら、その内容を秘密にし、その滅失・改変
を防ぐことができます。
2 その方式は、以下のようになります。
(1)遺言者が遺言書を作り、その証書に署名し、印を押すこと。
自筆である必要はなく、パソコン等での作成もできます。
(2)遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章でこれに封印をすること。
(3)遺言者が公証人1人と証人2人以上の面前に封書を提出して、それが
自分の遺言書である旨及びそれを書いた者の氏名と住所を述べること。
(4)公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封書に記載し
た後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
なお、上記の要件を充たさない秘密証書遺言は無効であるが、それが自筆
証書としての方式を備えていれば、自筆証書遺言としての効力を有します。
ページ移動
1,2, ... ,4,5
次へ
Page 1 of 5
を行くものとして秘密証書遺言があります。すなわち、秘密証書遺言は、
遺言書の存在は明確にしながら、その内容を秘密にし、その滅失・改変
を防ぐことができます。
2 その方式は、以下のようになります。
(1)遺言者が遺言書を作り、その証書に署名し、印を押すこと。
自筆である必要はなく、パソコン等での作成もできます。
(2)遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章でこれに封印をすること。
(3)遺言者が公証人1人と証人2人以上の面前に封書を提出して、それが
自分の遺言書である旨及びそれを書いた者の氏名と住所を述べること。
(4)公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封書に記載し
た後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
なお、上記の要件を充たさない秘密証書遺言は無効であるが、それが自筆
証書としての方式を備えていれば、自筆証書遺言としての効力を有します。