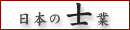08年01月16日
解雇に関する相談
「解雇したいがどうか」という相談はよくある。専門の者に相談するのであるから、法的にどうかという意味である。
経緯を聞くと、確かに問題のある従業員の内容が多い。しかし、裁判をするとたいてい会社が負ける。その吟味については色々分析があろうかと思うが、「日本の裁判所は解雇の判断をしない傾向が強い」とするだけでは労務管理の足しにはならない。今「労務管理」という言葉を出したが、課題はこの労務管理だと考える。
まず軽く法律をみてみよう。新労働契約法では、(第16条)≪解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。≫とある。これは労働基準法18条の2から移管されてきた規定である。条文は短いが、これには過去数十年かけて積み重ねられてできた判例をバックボーンとしているため、この条文だけで実務は無理である。
なお、判例と異なり、法律規定であるので公定力が働くことに留意。また努力義務とされている規定にせよ、行政機関と異なり司法機関の判断上においてはそれほど薄まるとも思えない。
さて、結論をいうと、客観的に、合理的な理由が備わり、社会通念上相当とする解雇とはどういうものかというと、「労務管理」ができている解雇かそうでない解雇かということになる。
したがって、「解雇したいがどうか」の相談において必ず確かめるべきことは、諸種の問題についてそれぞれどのような対処(処分)がされてきたかどうかという点である。それらが合理的な性質のあるものであれば解雇に至るも不自然ではない。しかし、そうでないのであれば解雇は時期尚早だということである。鍵は「労務管理」にある。
すぐさま「解雇」と連想するのは、懲戒処分(いうまでもなく労務管理の一つ)に慣れていないからである。それは戦中以降の日本の組織体制の名残りであり、そしてまだそれは強い影響を残しているとはいえ、懲戒処分を含め労務管理の再建築をしなければ労使いずれにおいても不満の火種は燻っているのである。会社は必ずといってよいほど負け、従業員間では不公平感が蔓延する。そして嫌がらせ行為が社内中にはびこると、もはや社長も会社をコントロールできなくなり、使用者責任をとらされるはめになる。いいことはない。
経緯を聞くと、確かに問題のある従業員の内容が多い。しかし、裁判をするとたいてい会社が負ける。その吟味については色々分析があろうかと思うが、「日本の裁判所は解雇の判断をしない傾向が強い」とするだけでは労務管理の足しにはならない。今「労務管理」という言葉を出したが、課題はこの労務管理だと考える。
まず軽く法律をみてみよう。新労働契約法では、(第16条)≪解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。≫とある。これは労働基準法18条の2から移管されてきた規定である。条文は短いが、これには過去数十年かけて積み重ねられてできた判例をバックボーンとしているため、この条文だけで実務は無理である。
なお、判例と異なり、法律規定であるので公定力が働くことに留意。また努力義務とされている規定にせよ、行政機関と異なり司法機関の判断上においてはそれほど薄まるとも思えない。
さて、結論をいうと、客観的に、合理的な理由が備わり、社会通念上相当とする解雇とはどういうものかというと、「労務管理」ができている解雇かそうでない解雇かということになる。
したがって、「解雇したいがどうか」の相談において必ず確かめるべきことは、諸種の問題についてそれぞれどのような対処(処分)がされてきたかどうかという点である。それらが合理的な性質のあるものであれば解雇に至るも不自然ではない。しかし、そうでないのであれば解雇は時期尚早だということである。鍵は「労務管理」にある。
すぐさま「解雇」と連想するのは、懲戒処分(いうまでもなく労務管理の一つ)に慣れていないからである。それは戦中以降の日本の組織体制の名残りであり、そしてまだそれは強い影響を残しているとはいえ、懲戒処分を含め労務管理の再建築をしなければ労使いずれにおいても不満の火種は燻っているのである。会社は必ずといってよいほど負け、従業員間では不公平感が蔓延する。そして嫌がらせ行為が社内中にはびこると、もはや社長も会社をコントロールできなくなり、使用者責任をとらされるはめになる。いいことはない。