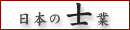09年08月25日
役員退職金の適正額の算定について
役員退職金は、
(1)退職者の過去の勤労に対する対価の後払い(費用性、賃金後払説)、
(2)退職者の在職中の功労に対する報酬(利益配分性、功労報償説)、
(3)将来の生活保障について考慮されたもの(生活保障説) 等
の性格を有するものです。
そういう内容だからこそ、役員の受け取る退職金は、所得税法上は通常の給与等とは異なり受取人にとって有利な課税体系となっており、また、法人税法上も「不相当に高額」「でなければ」、会社の損金(税務上の費用)にすることができます。
その役員退職金の適正額の決定については、通常の場合は、
(1)役員退職金規定にその支給限度額を定め(その計算方法は、平均功績倍率法(注1)が一般的です)、
(2)その限度額の範囲内で支給することを機関決定して支給することにより、
法人税法上の「不相当に高額でない水準」としているようです。
(注1)最終報酬月額×勤続年数×功績倍率により適正額を計算する方法です。最終報酬月額、勤続年数についてはあまり議論の余地がないため、「同業種・同規模の会社」をどう選定して功績倍率をいくらに決めるかが論点になってきます。
過去の判例を見ても、殆どが、平均功績倍率法等の一定の算式による退職金の適正額の算定を支持しています。一方、東京地裁の昭和46年6月29日の判決には、法人税法等の規定は「当該事案の特殊事情をすべて捨象して同業種・同規模の他の会社の給与の額を超える部分の損金算入をすべて否定しようとする趣旨に出たものではない」とあり、これは、会社の特殊事情があればそれを考慮して功績倍率を決める、または算式によらず退職金額を決めることの妥当性があることを示唆したものと思われます。
また、過去の判例を見てみると、平均功績倍率法による算定は以下の問題点、限界があると考えます。
1.最終報酬月額が所与(又は議論されていない)
平均功績倍率法を支持している判例は、最終報酬月額を所与としています(つまり、その報酬が過大かどうか深く議論されていません)。札幌地裁の平成11年12月12日の判決のように、報酬月額を退職事業年度に倍増させても、その倍増させた金額を前提に上記(注1)の算式を適用している例もあります。従って、これを逆手にとって、退職前に報酬を上げるという極端な方法も考える余地が生じます(もちろん、このブログは、そういう方法をお薦めするものではありませんが)。
2.同業種・同規模の会社の選定が難しい(個別事情が捨象されている)
筆者は、同業種・同規模の会社選定に当たって最も重要なのは、「在任期間中の純資産増加額(注2)」だと考えています。これが、最も役員(特に、代表者の場合の役員)の功績を表すものだと考えるからです。しかし、判例を見ると、純資産額の要素を考慮せずに、同業種・同規模の会社を選定しているものも散見されます。つまり、同業種・同規模の会社の選定自体にも更に深い議論が必要かと思います。
(注2)更に言うと、その増加額に対する退任役員の貢献度。たとえば、純資産増加額×(その役員報酬額/全人件費)で算出可能と考えます。
3.同業種・同規模の会社の「過去の実績」を基にしている。今後の実績は不問
当然、同業種・同規模として選定された会社の数値は、過去の実績です。退任する役員が今後も永続するようなビジネスモデルを作りそれがその後も有効である、等特別の場合は、その将来に亘っての貢献度を考慮する必要があると考えます。
上記より、平均功績倍率法による適正額の算定は、有効ではありますが、退任役員の功績が大きい(他社に比較して、純資産増加額が明らかに突出している等)の場合は、そういう事情を考慮して適正額を算定することも、十分に検討の価値があることだと思います。

↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。

↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。

(1)退職者の過去の勤労に対する対価の後払い(費用性、賃金後払説)、
(2)退職者の在職中の功労に対する報酬(利益配分性、功労報償説)、
(3)将来の生活保障について考慮されたもの(生活保障説) 等
の性格を有するものです。
そういう内容だからこそ、役員の受け取る退職金は、所得税法上は通常の給与等とは異なり受取人にとって有利な課税体系となっており、また、法人税法上も「不相当に高額」「でなければ」、会社の損金(税務上の費用)にすることができます。
その役員退職金の適正額の決定については、通常の場合は、
(1)役員退職金規定にその支給限度額を定め(その計算方法は、平均功績倍率法(注1)が一般的です)、
(2)その限度額の範囲内で支給することを機関決定して支給することにより、
法人税法上の「不相当に高額でない水準」としているようです。
(注1)最終報酬月額×勤続年数×功績倍率により適正額を計算する方法です。最終報酬月額、勤続年数についてはあまり議論の余地がないため、「同業種・同規模の会社」をどう選定して功績倍率をいくらに決めるかが論点になってきます。
過去の判例を見ても、殆どが、平均功績倍率法等の一定の算式による退職金の適正額の算定を支持しています。一方、東京地裁の昭和46年6月29日の判決には、法人税法等の規定は「当該事案の特殊事情をすべて捨象して同業種・同規模の他の会社の給与の額を超える部分の損金算入をすべて否定しようとする趣旨に出たものではない」とあり、これは、会社の特殊事情があればそれを考慮して功績倍率を決める、または算式によらず退職金額を決めることの妥当性があることを示唆したものと思われます。
また、過去の判例を見てみると、平均功績倍率法による算定は以下の問題点、限界があると考えます。
1.最終報酬月額が所与(又は議論されていない)
平均功績倍率法を支持している判例は、最終報酬月額を所与としています(つまり、その報酬が過大かどうか深く議論されていません)。札幌地裁の平成11年12月12日の判決のように、報酬月額を退職事業年度に倍増させても、その倍増させた金額を前提に上記(注1)の算式を適用している例もあります。従って、これを逆手にとって、退職前に報酬を上げるという極端な方法も考える余地が生じます(もちろん、このブログは、そういう方法をお薦めするものではありませんが)。
2.同業種・同規模の会社の選定が難しい(個別事情が捨象されている)
筆者は、同業種・同規模の会社選定に当たって最も重要なのは、「在任期間中の純資産増加額(注2)」だと考えています。これが、最も役員(特に、代表者の場合の役員)の功績を表すものだと考えるからです。しかし、判例を見ると、純資産額の要素を考慮せずに、同業種・同規模の会社を選定しているものも散見されます。つまり、同業種・同規模の会社の選定自体にも更に深い議論が必要かと思います。
(注2)更に言うと、その増加額に対する退任役員の貢献度。たとえば、純資産増加額×(その役員報酬額/全人件費)で算出可能と考えます。
3.同業種・同規模の会社の「過去の実績」を基にしている。今後の実績は不問
当然、同業種・同規模として選定された会社の数値は、過去の実績です。退任する役員が今後も永続するようなビジネスモデルを作りそれがその後も有効である、等特別の場合は、その将来に亘っての貢献度を考慮する必要があると考えます。
上記より、平均功績倍率法による適正額の算定は、有効ではありますが、退任役員の功績が大きい(他社に比較して、純資産増加額が明らかに突出している等)の場合は、そういう事情を考慮して適正額を算定することも、十分に検討の価値があることだと思います。
文責:事業承継部
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。