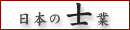14年05月25日
「残業代ゼロ絶対反対!」
しのびよる残業代ゼロ 労働に新制度案
毎日新聞 2014年05月23日 東京夕刊【江畑佳明】
《「残業代ゼロ絶対反対!」。安倍晋三首相があいさつをしようとするなり、そんな怒号が会場から飛んだ。自民党の首相として13年ぶりにメーデー中央大会(連合主催)に出席した4月26日のことだ。安倍首相はこの4日前、関係閣僚に「時間でなく、成果で評価される新たな労働時間制度の仕組みを検討してほしい」と指示。以来「残業代がなくなる」と労働者に不安が広がりつつあるのだ。》
『過労死防止法案』が衆議院を通過するなか、真逆の流れも起している。首相の頭ではこの二つは噛み合わないものとしているところが、残念である。
《問題の発端は4月22日。経済財政諮問会議と産業競争力会議の合同会議で、民間議員の長谷川閑史(やすちか)氏(経済同友会代表幹事)から「新たな労働時間制度の創設」が提案された。そして会議の終盤、首相は即、検討するよう命じた。
この提案には、基本的な考え方として「多様で柔軟な働き方を可能にするために」「労働時間と報酬のリンクを外す」と書かれている。
そもそも労基法は法定労働時間を「週40時間、1日8時間」と定め、役員や一部の管理職を除いて残業や休日勤務に割増賃金(いわゆる残業代)を支払うことを会社に義務付けている。しかし、長谷川氏の案では(1)高収入・ハイパフォーマー型社員(2)労働時間上限要件型社員−−について、労働時間規制の対象外とするよう提案している。
資料によると、(1)は主に年収1000万円以上で「高度な職業能力を有する」社員が対象。労働時間配分や職務遂行方法が本人の裁量で決められる。これは第1次安倍政権時代の2007年、「ホワイトカラー・エグゼンプション(除外)」制度として導入が検討された内容とほぼ同じだ。ちなみに当時は、経団連が対象社員を「年収400万円以上」とするよう求め、「一般労働者に拡大する」と批判が殺到。法案提出を断念した。》
まったく素人の浅はかな考えである。
「労働時間」という概念を出しているが、事実上これは報酬そのものよりも、時間外手当の計算などに用いるものであり、「報酬」そのものは各企業の基本設定によるものでしかない。基本給を時間で設定するのは時給、日給者の類である。ちゃんとした経営業務を執行している者による発想ではなく、単なる経営者政治団体で自分の実績を残したいだけの者の発想に近いものがある。
また、自社賃金規定において「時間」あたり幾らという設定をこの長谷川氏の所属する会社はしているとして、その「時間」を外すとすれば、何をもって報酬を設定するのだろうか。「成果」の評価は、裁判に耐えられるものかどうか。客観的と考えられている「時間」でさえも紛争は絶え間なく存在するが、「成果」紛争はさらに数倍の紛争量が期待できるだろう。
そして、「成果と報酬」について国家が介入する以上、国家が公定の報酬認定するところまで踏み込むべきである。かつての社会主義的統制国家体制におけるヤミマーケットが成立するであろうが、それだけの労働政策になる意義がある。公定報酬に違反した企業の経営人事の更迭等を国家が厚生労働省なり何なりに命じるなど必要になってくる。そこまで誰も追及しないのは何故かはわからないが、岸元革新官僚の親族だけに、国家に必要と考えられることは実現しようとするだろう。ただ、素人の持ってくる話には適確に判断処理できるためのシンクタンクぐらいは確保すべきだろう。岸氏は実験できる環境があったことを考えると、長谷川氏の所属する企業を国の特殊用途として提供してもらい、実験体としてデータ収集するのもよい。無論、素人考え通り誰もが満足できるものであればいいが、素人ほど怖いものは無いと昔からよく言うし………。
毎日新聞 2014年05月23日 東京夕刊【江畑佳明】
《「残業代ゼロ絶対反対!」。安倍晋三首相があいさつをしようとするなり、そんな怒号が会場から飛んだ。自民党の首相として13年ぶりにメーデー中央大会(連合主催)に出席した4月26日のことだ。安倍首相はこの4日前、関係閣僚に「時間でなく、成果で評価される新たな労働時間制度の仕組みを検討してほしい」と指示。以来「残業代がなくなる」と労働者に不安が広がりつつあるのだ。》
『過労死防止法案』が衆議院を通過するなか、真逆の流れも起している。首相の頭ではこの二つは噛み合わないものとしているところが、残念である。
《問題の発端は4月22日。経済財政諮問会議と産業競争力会議の合同会議で、民間議員の長谷川閑史(やすちか)氏(経済同友会代表幹事)から「新たな労働時間制度の創設」が提案された。そして会議の終盤、首相は即、検討するよう命じた。
この提案には、基本的な考え方として「多様で柔軟な働き方を可能にするために」「労働時間と報酬のリンクを外す」と書かれている。
そもそも労基法は法定労働時間を「週40時間、1日8時間」と定め、役員や一部の管理職を除いて残業や休日勤務に割増賃金(いわゆる残業代)を支払うことを会社に義務付けている。しかし、長谷川氏の案では(1)高収入・ハイパフォーマー型社員(2)労働時間上限要件型社員−−について、労働時間規制の対象外とするよう提案している。
資料によると、(1)は主に年収1000万円以上で「高度な職業能力を有する」社員が対象。労働時間配分や職務遂行方法が本人の裁量で決められる。これは第1次安倍政権時代の2007年、「ホワイトカラー・エグゼンプション(除外)」制度として導入が検討された内容とほぼ同じだ。ちなみに当時は、経団連が対象社員を「年収400万円以上」とするよう求め、「一般労働者に拡大する」と批判が殺到。法案提出を断念した。》
まったく素人の浅はかな考えである。
「労働時間」という概念を出しているが、事実上これは報酬そのものよりも、時間外手当の計算などに用いるものであり、「報酬」そのものは各企業の基本設定によるものでしかない。基本給を時間で設定するのは時給、日給者の類である。ちゃんとした経営業務を執行している者による発想ではなく、単なる経営者政治団体で自分の実績を残したいだけの者の発想に近いものがある。
また、自社賃金規定において「時間」あたり幾らという設定をこの長谷川氏の所属する会社はしているとして、その「時間」を外すとすれば、何をもって報酬を設定するのだろうか。「成果」の評価は、裁判に耐えられるものかどうか。客観的と考えられている「時間」でさえも紛争は絶え間なく存在するが、「成果」紛争はさらに数倍の紛争量が期待できるだろう。
そして、「成果と報酬」について国家が介入する以上、国家が公定の報酬認定するところまで踏み込むべきである。かつての社会主義的統制国家体制におけるヤミマーケットが成立するであろうが、それだけの労働政策になる意義がある。公定報酬に違反した企業の経営人事の更迭等を国家が厚生労働省なり何なりに命じるなど必要になってくる。そこまで誰も追及しないのは何故かはわからないが、岸元革新官僚の親族だけに、国家に必要と考えられることは実現しようとするだろう。ただ、素人の持ってくる話には適確に判断処理できるためのシンクタンクぐらいは確保すべきだろう。岸氏は実験できる環境があったことを考えると、長谷川氏の所属する企業を国の特殊用途として提供してもらい、実験体としてデータ収集するのもよい。無論、素人考え通り誰もが満足できるものであればいいが、素人ほど怖いものは無いと昔からよく言うし………。
14年05月14日
経営の欲望説-特に労働時間法制
「労働時間」法制については、工場法つまり機械等稼働時間に応じた労働での枠組みとして有効である。
長時間労働でイメージとして一般的に思い浮かべるのは、産業革命期のイギリスの状況ではあるまいか。12時間労働、幼少労働者と。
日本ではそれとともに『女工哀史』によって語られたものは、健康障害と寄宿舎(搾取等)問題と有期労働問題と親がする労働契約問題と職業紹介問題と、現行の労基法等に色濃く残っている。
工場労働でなければ、上記に関わる問題はほとんど関係が無いと考えてしまうところであり、事実、現代のサービス産業においてはそれら工場法制的な規定はそぐわないと考えてしまっている素人が多い。
工場での労働でない場合、経営者としては機械等の稼動にかかる時間に配慮しなくていいことによって、無限に働かせようとするのが欲望の常なのである。したがって、工場労働もそれ以外の労働も、経営者の欲望の前には何ら変りはない。
そこにやはり一般的ルールが必要で、それによって経営者の欲望を落ち着かせるのが生理上の観点として必要なのである。
ただほんの僅かの例ではあるが、同じ労働時間で換算しても月額100万を超える給与をもらっている労働者もいる。最賃がどうのこうのという世界とは無縁の人である。おそらく法律上の「管理監督者」もしくは「裁量労働」対象者であろう。また、厚生年金の最高等級を超える者であれば、もう少し多い。これは同族経営である場合が多いだろう。確かに、これらの者については「労働時間」はほとんど意味がなくなっているはずである。労働においてより主体的であるから、保護される立場ではないということである。
なお「労働者」性についても、一概に判断できなくなってきたことは確かである。「請負」と比べれば、就業規則の厳守の有無に終着するわけであるが、難しいのはもともと就業規則あるいは会社による労務管理が弱い状況下での判断である。杜撰さと動きやすさと紙一重のところで、信頼関係というか細い糸の上で成り立っている労使関係あるいは取引関係も少なくない。
長時間労働でイメージとして一般的に思い浮かべるのは、産業革命期のイギリスの状況ではあるまいか。12時間労働、幼少労働者と。
日本ではそれとともに『女工哀史』によって語られたものは、健康障害と寄宿舎(搾取等)問題と有期労働問題と親がする労働契約問題と職業紹介問題と、現行の労基法等に色濃く残っている。
工場労働でなければ、上記に関わる問題はほとんど関係が無いと考えてしまうところであり、事実、現代のサービス産業においてはそれら工場法制的な規定はそぐわないと考えてしまっている素人が多い。
工場での労働でない場合、経営者としては機械等の稼動にかかる時間に配慮しなくていいことによって、無限に働かせようとするのが欲望の常なのである。したがって、工場労働もそれ以外の労働も、経営者の欲望の前には何ら変りはない。
そこにやはり一般的ルールが必要で、それによって経営者の欲望を落ち着かせるのが生理上の観点として必要なのである。
ただほんの僅かの例ではあるが、同じ労働時間で換算しても月額100万を超える給与をもらっている労働者もいる。最賃がどうのこうのという世界とは無縁の人である。おそらく法律上の「管理監督者」もしくは「裁量労働」対象者であろう。また、厚生年金の最高等級を超える者であれば、もう少し多い。これは同族経営である場合が多いだろう。確かに、これらの者については「労働時間」はほとんど意味がなくなっているはずである。労働においてより主体的であるから、保護される立場ではないということである。
なお「労働者」性についても、一概に判断できなくなってきたことは確かである。「請負」と比べれば、就業規則の厳守の有無に終着するわけであるが、難しいのはもともと就業規則あるいは会社による労務管理が弱い状況下での判断である。杜撰さと動きやすさと紙一重のところで、信頼関係というか細い糸の上で成り立っている労使関係あるいは取引関係も少なくない。
14年05月09日
裁判所は遠い
憲法で裁判を受ける権利が明記されているが、だいたいその段階で終わっている。
まず裁判所と国民を結びつける弁護士に疎い。次に、訴訟手続きに疎い。
結局身近な行政窓口に相談しに行くというのが国民の当然の行動となる。それがスタートでなくゴールだと勝手に決めつけて行く国民も多く、行政窓口はクレームの巣窟となる。
無論、行政が裁量で行うものに関しては正しい行動であるが、問題は司法的判断を国民が求めるという案件である。当然ながら、行政では窓口はおろか長においても権限外である。
そこで最終的には(あるいはクレーム時間の初段階においても)、裁判所での問題解決を教示するわけであるが、
・それは自分でしなければならない。
・費用は印紙代、特別郵便代。
・弁護士と代理人契約したほうがよい。ただし、多忙であるとか、利益面から引き受けてもらえない可能性も高い。しかし、少なくとも相談だけはすべき。時間は金なりで、知りたいことだけを聞くよう整理しときましょう。
ということになる。
行政側で無料でやってくれるものと思い込んでいた国民は、泣きっ面に蜂になる。
裁判を受ける権利は絵に書いた餅とまで言わないにしろ、紛争解決の方法について国民は無知である。近頃は内容証明を自分で出すようになってきたので、変わりつつはある。自分でやるということを想定して憲法は作られているといえる。ただそれを義務教育の段階で教えていないため、そのまま一生を誤解したまま終えることになる。それはそれで幸せだが、紛争に捲き込まれると、丸投げしてしまい、思う通りいかないと、行政はおろか関係者や裁判所にまで怒りの矛先を向けるという末路を辿ってしまう。
しかも訴訟手続きが要めで、これをわかっていないと方向を誤る。当事者による解決ではなく、第三者に事実確認をしてもらい、判断を下してもらうという要求なのであるから、それがスムーズに行われるように提示できなければならない。理屈と証拠の世界である。裁判官は実際には何も事情を知らない事案について判断を下すため、またある程度の虚偽や誇張も含まれるということを前提として、当事者の言い分を聞いていきながら、心証を作っていく。あるいは早い段階で既に作っていることも少なくなかろう。判決文で回りくどい言い方をしてある場合がこれにあたるとみる。
以上が国民における司法事情である。
まず裁判所と国民を結びつける弁護士に疎い。次に、訴訟手続きに疎い。
結局身近な行政窓口に相談しに行くというのが国民の当然の行動となる。それがスタートでなくゴールだと勝手に決めつけて行く国民も多く、行政窓口はクレームの巣窟となる。
無論、行政が裁量で行うものに関しては正しい行動であるが、問題は司法的判断を国民が求めるという案件である。当然ながら、行政では窓口はおろか長においても権限外である。
そこで最終的には(あるいはクレーム時間の初段階においても)、裁判所での問題解決を教示するわけであるが、
・それは自分でしなければならない。
・費用は印紙代、特別郵便代。
・弁護士と代理人契約したほうがよい。ただし、多忙であるとか、利益面から引き受けてもらえない可能性も高い。しかし、少なくとも相談だけはすべき。時間は金なりで、知りたいことだけを聞くよう整理しときましょう。
ということになる。
行政側で無料でやってくれるものと思い込んでいた国民は、泣きっ面に蜂になる。
裁判を受ける権利は絵に書いた餅とまで言わないにしろ、紛争解決の方法について国民は無知である。近頃は内容証明を自分で出すようになってきたので、変わりつつはある。自分でやるということを想定して憲法は作られているといえる。ただそれを義務教育の段階で教えていないため、そのまま一生を誤解したまま終えることになる。それはそれで幸せだが、紛争に捲き込まれると、丸投げしてしまい、思う通りいかないと、行政はおろか関係者や裁判所にまで怒りの矛先を向けるという末路を辿ってしまう。
しかも訴訟手続きが要めで、これをわかっていないと方向を誤る。当事者による解決ではなく、第三者に事実確認をしてもらい、判断を下してもらうという要求なのであるから、それがスムーズに行われるように提示できなければならない。理屈と証拠の世界である。裁判官は実際には何も事情を知らない事案について判断を下すため、またある程度の虚偽や誇張も含まれるということを前提として、当事者の言い分を聞いていきながら、心証を作っていく。あるいは早い段階で既に作っていることも少なくなかろう。判決文で回りくどい言い方をしてある場合がこれにあたるとみる。
以上が国民における司法事情である。
14年05月06日
残業なし労働制度
残業代ゼロ検討指示 首相「時間でなく成果で評価」
《安倍晋三首相は二十二日、政府の経済財政諮問会議と産業競争力会議との合同会議で「時間ではなく成果で評価される働き方にふさわしい、新たな労働時間制度の仕組みを検討してほしい」と労働時間規制の緩和を検討するよう指示した。》
《産業競争力会議の民間議員は、国が年間労働時間の上限を示し、従業員の健康への配慮措置を設けた上で労使合意により対象職種を決める方式と、年収が一千万円以上で高度な職業能力を持つなど「高収入・ハイパフォーマー型」の労働者を対象とする方式の二種類を示した。》
ずいぶん前に、年収一千万という基準で議論されていたところ、それに加えて労使合意のタイプが議論に上っている。やはり議論をしている者にとって後者が本命だったんだなと思う。
正社員からパート、オルバイト、派遣といった非正規労働の活用もほぼ天井とみて、次なるコスト削減策とみる。昭和の労働分配率はかなり高かったが、今やおよそその半分くらいか。
「時間ではなく成果で評価される働き方にふさわしい」という表現をまともに首相は受け止めているような感じなので、国内情報収集体制の劣悪さがみえてしまっている。その貧弱な情報能力で国を動かそうとするのは迷惑である。周りにいいように扱われている首相としか思えない内容ばかりなのでそうでなくなってほしい。
・多くの者がすぐに反対表明したように、現在労使関係において信頼関係は薄くなった。したがって、昭和時代のような一家状態にはない。よって「契約」が今の労使関係のすべてであり、政治的な措置で操作できうる状況ではない。
・成果での評価をどうするかは能力主義賃金において誰も解決できていない課題であるが、それを見過ごして進めようとする思考の欠陥。
・時間外賃金不払いは現在大きく占める労働問題であり、それを解決してからでなければ前に進むべきではなく、不払い制度を作って解消させようとするのは道理ではない。
一家主義の昭和時代、労働問題は方便がすべてであった。現在労使間の信頼関係崩れ、方便は否定され、私法での解決が進んでいる。司法的な考え方が職場や斯界に根付いてきつつつあるところなのだが、それに抵抗する者の運動という図式がここにあるようだ。
労働問題は、「成果」の評価の課題からいっても、政治的な問題ではありえず、職場の関係の問題に終始する。立法で決められる対象ではなく、それが政治の限界である。
《安倍晋三首相は二十二日、政府の経済財政諮問会議と産業競争力会議との合同会議で「時間ではなく成果で評価される働き方にふさわしい、新たな労働時間制度の仕組みを検討してほしい」と労働時間規制の緩和を検討するよう指示した。》
《産業競争力会議の民間議員は、国が年間労働時間の上限を示し、従業員の健康への配慮措置を設けた上で労使合意により対象職種を決める方式と、年収が一千万円以上で高度な職業能力を持つなど「高収入・ハイパフォーマー型」の労働者を対象とする方式の二種類を示した。》
ずいぶん前に、年収一千万という基準で議論されていたところ、それに加えて労使合意のタイプが議論に上っている。やはり議論をしている者にとって後者が本命だったんだなと思う。
正社員からパート、オルバイト、派遣といった非正規労働の活用もほぼ天井とみて、次なるコスト削減策とみる。昭和の労働分配率はかなり高かったが、今やおよそその半分くらいか。
「時間ではなく成果で評価される働き方にふさわしい」という表現をまともに首相は受け止めているような感じなので、国内情報収集体制の劣悪さがみえてしまっている。その貧弱な情報能力で国を動かそうとするのは迷惑である。周りにいいように扱われている首相としか思えない内容ばかりなのでそうでなくなってほしい。
・多くの者がすぐに反対表明したように、現在労使関係において信頼関係は薄くなった。したがって、昭和時代のような一家状態にはない。よって「契約」が今の労使関係のすべてであり、政治的な措置で操作できうる状況ではない。
・成果での評価をどうするかは能力主義賃金において誰も解決できていない課題であるが、それを見過ごして進めようとする思考の欠陥。
・時間外賃金不払いは現在大きく占める労働問題であり、それを解決してからでなければ前に進むべきではなく、不払い制度を作って解消させようとするのは道理ではない。
一家主義の昭和時代、労働問題は方便がすべてであった。現在労使間の信頼関係崩れ、方便は否定され、私法での解決が進んでいる。司法的な考え方が職場や斯界に根付いてきつつつあるところなのだが、それに抵抗する者の運動という図式がここにあるようだ。
労働問題は、「成果」の評価の課題からいっても、政治的な問題ではありえず、職場の関係の問題に終始する。立法で決められる対象ではなく、それが政治の限界である。
14年04月29日
弁護士と特定社労士
労働事件をよくする弁護士と社労士の交流が繁くなっていることは前に述べたとおりである。愚痴を聞かされるのには閉口するが、紛争手続きの実務や情勢について聞くのは新鮮な事柄が多い。弁護士にとっては垢のついた内容ではあろうが、労務管理の限界などと繋げれば辻褄が大体合ってくるものである。
この両者が交わることによって感じたことがある。
1、弁護士が労使どちら側でもない職務に従事する社労士をみて羨ましがっている点。
尤も、弁護士でも社労士として登録すればそのようにすぐなれるのであるが、それはそれとして、この見方について社労士からは、どちら側でもないが、経験が浅ければ会社の言いなりになってしまう者が多いという点がある。だからこそ、紛争解決を経験することによって、私法解決の考えをみっちり身に着ける必要に迫られているのである。
なお、弁護士は裁判官がいない日常での解決にはあまり関心が向いていない。若干、和解に積極的な者もいるが、たいていそこまでの余力も限られているようである。
2、紛争事案における弁護士と社労士の住み分けについて。
弁護士の多くが誤解しているのは、社労士に公的な紛争処理の実力があると考えていることである。無論、関与先に生じた紛争はたいてい解決できるが、それは法を基にしたものではない。労使間の信頼の貸し借りのような解決となる。したがって、あっせんの次以降の裁判所を利用した制度については弁護士にスイッチするという住み分け。
しかしこの考えは否定されている。否定されたのは思考の経路である。
まず、社労士法において、あっせん代理業務から個別紛争解決業務に改正された。そして特定社会保険労務士は労働相談技術の習得が必修とされた。その上で、特定社会保険労務士としてできることとできないことの研修を受け、訴訟代理を含め法律事務の制約を受けているのである。したがって、法律事務は無論知っておかねばならない。しかし、できない業務であるから、そこでスムーズに交流のある弁護士を紹介するのである。
そもそも労働相談をまともにできない社労士に、弁護士を紹介してもらうことはほとんど無い。信頼関係が傷ついているからである。その程度の社労士が紹介する弁護士に対しても無論眉唾モノでの初対面となり、後々依頼人トラブルへと発展しかねない要素をもつ。
社労士に自己の営業の先鋒を頼む考えを抱く弁護士がいないとは思えないが、半分以上は、それぞれ独立する経営体であり、同業者という関係でしかないのである。しかも弁護士法では弁護士が他者と貸し借りをもつ関係をよしとしていないのである。
よって、特定社会保険労務士は労働相談技術を身につけ、相談者に信用を得た後に、できない業務については弁護士を紹介するということになる。解決手順、解決手段の見極めなどろくに労働相談ができない社労士が多すぎるので、述べたまでである。もちろん、それはなかなか身につくものではないが、相談においてどのような債務を負っているかを認識すべきである。
(なお、こうしたことが言えるようになったのは既に上記の課題をある程度クリアもしくはクリアする体制が備わってきたいう見解だからである。誤解無きよう。)
ページ移動
前へ
1,2, ... ,8,9,10, ... ,36,37
次へ
Page 9 of 37
この両者が交わることによって感じたことがある。
1、弁護士が労使どちら側でもない職務に従事する社労士をみて羨ましがっている点。
尤も、弁護士でも社労士として登録すればそのようにすぐなれるのであるが、それはそれとして、この見方について社労士からは、どちら側でもないが、経験が浅ければ会社の言いなりになってしまう者が多いという点がある。だからこそ、紛争解決を経験することによって、私法解決の考えをみっちり身に着ける必要に迫られているのである。
なお、弁護士は裁判官がいない日常での解決にはあまり関心が向いていない。若干、和解に積極的な者もいるが、たいていそこまでの余力も限られているようである。
2、紛争事案における弁護士と社労士の住み分けについて。
弁護士の多くが誤解しているのは、社労士に公的な紛争処理の実力があると考えていることである。無論、関与先に生じた紛争はたいてい解決できるが、それは法を基にしたものではない。労使間の信頼の貸し借りのような解決となる。したがって、あっせんの次以降の裁判所を利用した制度については弁護士にスイッチするという住み分け。
しかしこの考えは否定されている。否定されたのは思考の経路である。
まず、社労士法において、あっせん代理業務から個別紛争解決業務に改正された。そして特定社会保険労務士は労働相談技術の習得が必修とされた。その上で、特定社会保険労務士としてできることとできないことの研修を受け、訴訟代理を含め法律事務の制約を受けているのである。したがって、法律事務は無論知っておかねばならない。しかし、できない業務であるから、そこでスムーズに交流のある弁護士を紹介するのである。
そもそも労働相談をまともにできない社労士に、弁護士を紹介してもらうことはほとんど無い。信頼関係が傷ついているからである。その程度の社労士が紹介する弁護士に対しても無論眉唾モノでの初対面となり、後々依頼人トラブルへと発展しかねない要素をもつ。
社労士に自己の営業の先鋒を頼む考えを抱く弁護士がいないとは思えないが、半分以上は、それぞれ独立する経営体であり、同業者という関係でしかないのである。しかも弁護士法では弁護士が他者と貸し借りをもつ関係をよしとしていないのである。
よって、特定社会保険労務士は労働相談技術を身につけ、相談者に信用を得た後に、できない業務については弁護士を紹介するということになる。解決手順、解決手段の見極めなどろくに労働相談ができない社労士が多すぎるので、述べたまでである。もちろん、それはなかなか身につくものではないが、相談においてどのような債務を負っているかを認識すべきである。
(なお、こうしたことが言えるようになったのは既に上記の課題をある程度クリアもしくはクリアする体制が備わってきたいう見解だからである。誤解無きよう。)