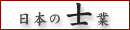09年08月31日
住宅取得等資金贈与の500万円の非課税特例
贈与税といえば、『1年間に110万円までの贈与は非課税』ということは多くの方が知っていらっしゃることと思います。
この度、経済の回復のために住宅取得等資金贈与の500万円の非課税が創設されています。
1.平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に
2.20歳以上の方が
3.その方の父母や祖父母などの直系尊属から
4.自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築・取得・増改築に充てるための金銭を贈与により取得し
5.贈与を受けた年の翌年3月15日までにその金銭の全額を充てて一定の要件を満たす家屋の新築・取得・増改築を行い、
6.贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であることと見込まれる方が、
7.贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の期限内申告書を提出しなければなりません。
なお、親族の工務店に新築・増改築を依頼する場合や親族から家屋を取得する場合にはこの非課税制度の適用はありません。
また、直系尊属から金銭ではなく、住宅用家屋そのものを贈与された場合にもこの非課税制度の適用はありません。
祖父と父から500万円ずつ、計1,000万円贈与された場合には、あくまでももらった方1人につき500万円が限度であるため、1,000万すべてが非課税になるわけではありませんのでご注意ください。
この非課税制度は他の控除額との併用が可能です。非課税制度(500万円)適用後の残額には、暦年課税にあっては基礎控除額(110万円)、相続時精算課税にあっては特別控除額(2,500万円)及び特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る特別控除額(1,000万円)が適用できます。なお、相続時精算課税に係る特別控除額(2,500万円)及び特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る特別控除額(1,000万円)の適用は、原則として、父母からの贈与の場合に限られます。
一定の要件につきましては、詳しくは、お近くの税務署や専門家にお尋ねください。

↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。

↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。

この度、経済の回復のために住宅取得等資金贈与の500万円の非課税が創設されています。
1.平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に
2.20歳以上の方が
3.その方の父母や祖父母などの直系尊属から
4.自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築・取得・増改築に充てるための金銭を贈与により取得し
5.贈与を受けた年の翌年3月15日までにその金銭の全額を充てて一定の要件を満たす家屋の新築・取得・増改築を行い、
6.贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であることと見込まれる方が、
7.贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の期限内申告書を提出しなければなりません。
なお、親族の工務店に新築・増改築を依頼する場合や親族から家屋を取得する場合にはこの非課税制度の適用はありません。
また、直系尊属から金銭ではなく、住宅用家屋そのものを贈与された場合にもこの非課税制度の適用はありません。
祖父と父から500万円ずつ、計1,000万円贈与された場合には、あくまでももらった方1人につき500万円が限度であるため、1,000万すべてが非課税になるわけではありませんのでご注意ください。
この非課税制度は他の控除額との併用が可能です。非課税制度(500万円)適用後の残額には、暦年課税にあっては基礎控除額(110万円)、相続時精算課税にあっては特別控除額(2,500万円)及び特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る特別控除額(1,000万円)が適用できます。なお、相続時精算課税に係る特別控除額(2,500万円)及び特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る特別控除額(1,000万円)の適用は、原則として、父母からの贈与の場合に限られます。
一定の要件につきましては、詳しくは、お近くの税務署や専門家にお尋ねください。
文責:資産税部
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。
09年08月27日
〜短期前払費用の取扱いについて〜
今回は、短期前払費用の取扱いについて検討をくわえることとする。
まず、法人税法基本通達2-2-14(短期前払費用)を確認することとする。
(短期の前払費用)
2−2−14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2−2−14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2−8「七」により追加、昭61年直法2−12「二」により改正)
(注)例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。
次に、国税庁の質疑応答事例について確認する。
【照会要旨】
当事者間の契約により、年1回3月決算の法人が次のような支払を継続的に行うこととしているものについては、法人税基本通達2−2−14((短期の前払費用))を適用し、その支払額の全額をその支払った日の属する事業年度において損金の額に算入して差し支えありませんか。
事例1:期間40年の土地賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の地代月額1,000,000円を支払う。
事例2:期間20年の土地賃借に係る賃料について、毎年、地代年額(4月から翌年3月)241,620円を3月末に前払により支払う。
事例3:期間2年(延長可能)のオフィスビルフロアの賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の家賃月額611,417円を支払う。
事例4:期間4年のシステム装置のリース料について、12ケ月分(4月から翌年3月)379,425円を3月下旬に支払う。
事例5:期間10年の建物賃借に係る賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月)1,000,000円を2月に前払により支払う。
【回答要旨】
・ 事例1から事例4までについては、照会意見のとおりで差し支えありません。
・ 事例5については、法人税基本通達2−2−14の適用が認められません。
(理由)
(1) 本通達の趣旨について
本通達は、1年以内の短期前払費用について、収益との厳密な期間対応による繰延経理をすることなく、その支払時点で損金算入を認めるというものであり、企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるというものです。
(2) 照会に対する考え方について
事例1から事例4までについては、基本的には、これを認めることが相当と考えられますが、一方では、利益が出たから今期だけまとめて1年分支払うというような利益操作のための支出や収益との対応期間のズレを放置すると課税上の弊害が生ずると認められるものについては、これを排除していく必要があります。
このため、継続的な支払を前提条件とすることや収入との直接的な見合関係にある費用については本通達の適用対象外とするということは、従来と同様、当然に本通達の適用に当たって必要とされるのですが、これに加え、役務の受入れの開始前にその対価の支払が行われ、その支払時から1年を超える期間を対価支払の対象期間とするようなものは、何らかの歯止めを置いた上で本通達の適用を認めることが相当と考えられます。
【関係法令通達】
法人税基本通達2−2−14
注記
平成20年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるというものであるが、重要性についての裁決を国税不服審判所の裁決事例より抜粋した。
当該事業年度末に約束手形で支給された翌事業年度の年俸制に係る役員報酬及び従業員給与については、当該事業年度内に具体的な役務提供がされておらず、また、会計上重要性の乏しい費用とは認められないから、当該事業年度の損金の額に算入できないとした事例
▼ 裁決事例集 No.65 - 343頁
請求人は、臨時株主総会又は従業員との間の合意による役員報酬又は従業員給与の年俸額(以下「本件役員報酬等」という。)に係る損金算入につき、本件役員報酬等を12で除した月割額から社会保険料等を控除した金額を券面額とする12枚の約束手形を振り出し、当該各事業年度内に支払っているから、その債務は当該事業年度の終了の日までに確定しており、仮にそうでないとしても、本件役員報酬等は支払いの日から1年以内に役務提供を受ける短期前払費用であり、法人税法基本通達2−2−14の後段の取扱い(以下「本件取扱い」という。)が適用されるから、たとえそれがその翌事業年度の業務執行等の役務に対応するものであっても、それは当該事業年度の損金の額に算入される旨主張する。
しかしながら、本件役員報酬等については、その具体的な給付をなすべき原因である役員の職務執行又は従業員の役務提供が当該事業年度の終了の日までになされていないから、その債務が確定しているとは認められず、また、本件役員報酬等は、請求人の財務内容に占める割合などからして、重要性の乏しい費用とは認められないため、本件役員報酬等には本件取扱いの適用がなく、したがって、それを当該事業年度の損金の額に算入することはできない。
平成15年2月20日裁決
(平15.2.20裁決、裁決事例集No.65 343頁)
《裁決書(抄)》
1 事実
(1)事案の概要
本件は、写真製版業及び出版業を営む同族会社である審査請求人(以下「請求人」という。)が、翌事業年度に対応する役員報酬等を事業年度終了の日までに一括して支払ったことについて、当該役員報酬等をいつの事業年度の損金の額に算入すべきであるかが争われた事案である。
(2)審査請求に至る経緯
イ 請求人は、平成9年5月1日から平成10年4月30日まで、平成10年5月1日から平成11年4月30日まで及び平成11年5月1日から平成12年4月30日までの各事業年度(以下、順次「平成10年4月期」、「平成11年4月期」及び「平成12年4月期」といい、これらを併せて「本件各事業年度」という。)の法人税について、青色の確定申告書に別表1の「確定申告」欄のとおり記載して、いずれも法定申告期限までに申告した。
ロ 原処分庁は、これに対し、平成13年5月21日付で、別表1の「更正処分等」欄のとおりの各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)をした。
ハ 請求人は、原処分を不服として、平成13年7月17日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、同年10月15日付で、平成10年4月期及び平成11年4月期の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分に対する異議申立てをいずれも棄却し、平成12年4月期の更正処分に対する異議申立てを却下する異議決定をした。
ニ 請求人は、異議決定を経た後の原処分に不服があるとして、平成13年11月14日に審査請求をした。
(3)関係法令等
イ 法人税法(平成12年法律第97号による改正前のもの。以下同じ。)第22条《各事業年度の所得の金額の計算》
法人税法第22条第3項第2号は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額として、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(以下「費用等」という。)の額を掲げるとともに、その費用等の範囲について、償却費以外の費用の場合には、当該事業年度終了の日までに債務の確定しているものとする旨規定している。
ロ 法人税基本通達2−2−12《債務の確定の判定》(以下「本件債務通達」という。)
本件債務通達は、上記イの「当該事業年度終了の日までに債務の確定しているもの」とは、別に定めるものを除き、当該事業年度終了の日までに、〔1〕当該費用に係る債務が成立していること(以下「債務成立要件」という。)、〔2〕当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること(以下「給付原因発生要件」という。)及び〔3〕その金額を合理的に算定することができるものであること(以下「合理的算定要件」といい、債務成立要件及び給付原因発生要件と併せて「確定債務3要件」という。)の3つの要件をすべて満たしている場合をいう旨定めている。
ハ 法人税基本通達2−2−14《短期の前払費用》(以下「本件前払通達」という。)
本件前払通達は、その前段において、前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていないものをいう。以下同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないとの原則を定めるとともに、その後段において、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める旨の取扱い(以下「後段の取扱い」という。)を定めている。
(4)基礎事実
以下の事実は、請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所が調査したところによっても、その事実が認められる。
イ 役員報酬
(イ)請求人の平成9年4月25日付の臨時株主総会議事録には、役員報酬について、要旨次のとおり決議された旨の記載がある。
A 取締役の平成9年4月26日から平成10年4月25日までの年俸額(以下「9年4月役員報酬」という。)は、Gが18,000,000円、Hが7,750,800円。
B 当該取締役が、上記Aの期間中に辞任するか解任された場合は、原則として、年俸額を日数按分する。
(ロ)請求人の平成10年4月24日付の臨時株主総会議事録には、役員報酬について、要旨次のとおり決議された旨の記載がある。
A 取締役の平成10年4月26日から平成11年4月25日までの年俸額(以下「10年4月役員報酬」という。)は、Gが18,000,000円、Hが7,750,800円。
B 当該取締役が、上記Aの期間中に辞任するか解任された場合は、原則として、年俸額を日数按分する。
(ハ)請求人の平成11年4月23日付の臨時株主総会議事録には、役員報酬について、要旨次のとおり決議された旨の記載がある。
A 取締役の平成11年4月26日から平成12年4月25日までの年俸額(以下「11年4月役員報酬」という。)は、Gが18,000,000円、Hが8,110,800円。
B 当該取締役が、上記Aの期間中に辞任するか解任された場合は、原則として、年俸額を日数按分する。
(ニ)請求人の平成12年4月25日付の臨時株主総会議事録には、役員報酬について、要旨次のとおり決議された旨の記載がある。
A 取締役の平成12年4月26日から平成13年4月25日までの年俸額(以下「12年4月役員報酬」といい、「10年4月役員報酬」及び「11年4月役員報酬」と併せて「本件各役員報酬」という。)は、Gが18,000,000円、Hが8,110,800円。
B 当該取締役が、上記Aの期間中に辞任するか解任された場合は、原則として、年俸額を日数按分する。
(ホ)請求人は、9年4月役員報酬の合計金額25,750,800円、10年4月役員報酬の合計金額25,750,800円、11年4月役員報酬の合計金額26,110,800円及び12年4月役員報酬の合計金額26,110,800円を、それぞれ平成8年5月1日から平成9年4月30日までの事業年度(以下「平成9年4月期」という。)、平成10年4月期、平成11年4月期及び平成12年4月期の損金の額に算入した。
(ヘ)請求人は、上記(ホ)の各金額を、それぞれ平成9年4月25日、平成10年4月25日、平成11年4月25日及び平成12年4月25日に、社会保険料等として控除する金額を差し引いた残額の12分の1を額面金額とする12枚の約束手形を振り出して支給した。
なお、約束手形の決済期日は、各年5月25日以降の各月の25日である。
ロ 従業員給与
(イ)年俸制に関する合意書
請求人が、従業員(以下「本件従業員」という。)との間で締結した平成10年4月24日付、平成11年4月26日付及び平成12年4月25日付の年俸制に関する各合意書(以下「本件各合意書」という。)には、要旨別表2及び次のAないしCのとおりの内容が記載されている(以下、本件各合意書の各日付に従い、本件各合意書記載の年俸を順次「10年4月給料」、「11年4月給料」及び「12年4月給料」といい、これらを併せて「本件各給料」という。)。
A 本件従業員は、請求人に対して、年俸対象期間中において、その労務を誠実に提供しなければならない。ただし、年俸対象期間中に本件従業員が退職する場合は、本件従業員は、退職後は労務を提供しないことになるので、退職月後に決済される予定の月割額を受給する権利はない(本件各合意書の第4条)。
B 請求人は、本件従業員に対し、年俸金額を12で除した額を毎月28日に支払う(本件各合意書の第3条第1項)。
C 請求人は、本件従業員に対して、年俸金額の月割額から控除すべき金額を差し引いた残額を額面金額とする約束手形で支払う(本件各合意書の第3条第2項)。
(ロ)請求人は、10年4月給料の合計金額14,983,200円、11年4月給料の合計金額21,392,400円及び12年4月給料の合計金額18,177,600円を、それぞれ平成10年4月期、平成11年4月期及び平成12年4月期の損金の額に算入した。
(ハ)請求人は、本件各合意書の内容(上記(イ)のB及びC)に応じた約束手形を振り出した。
(ニ)承諾書
本件従業員が請求人に対して提出した平成10年4月24日付、平成11年4月26日付及び平成12年4月25日付の各承諾書(以下「本件各承諾書」という。)には、別表3の内容を承諾する旨の記載がある(以下、本件各承諾書の各日付に従い、本件各承諾書記載の賞与を順次「10年4月賞与」、「11年4月賞与」及び「12年4月賞与」といい、これらを併せて「本件各賞与」という。)。
(ホ)請求人は、10年4月賞与の合計金額1,205,000円、11年4月賞与の合計金額4,540,000円及び12年4月賞与の合計金額4,140,000円を、それぞれ平成10年4月期、平成11年4月期及び平成12年4月期の損金の額に算入した。
なお、請求人は、平成9年4月期において、平成10年4月期に対応する給料及び賞与を損金の額に算入していない。
2 主張
(1)原処分庁の主張
イ 平成12年4月期に係る更正処分
平成12年4月期に係る更正処分は、当該事業年度の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものではないから、当該更正処分に対する審査請求は不適法である。
よって、当該審査請求を却下するとの裁決を求める。
ロ 原処分のうち上記イ以外の各処分
原処分のうち上記イ以外の各処分は、次の理由により適法であるから、当該各処分に係る審査請求をいずれも棄却するとの裁決を求める。
(イ)平成10年4月期及び平成11年4月期に係る各更正処分
本件各役員報酬、本件各給料及び本件各賞与(以下、これらを併せて「本件各役員報酬等」という。)は、以下の理由により、その支払った日の属する事業年度(以下「支払事業年度」という。)の損金の額に算入すべきではなく、その翌事業年度の損金の額に算入すべきである。
A 債務の確定
費用等が法人税法第22条第3項第2号の債務の確定したものとして損金の額に算入すべき金額となるためには、本件債務通達の定める確定債務3要件を満たす必要がある。
また、役員報酬は、役員が株主からの委任を受けて業務を執行したことの対価として支払われるものであり、また、従業員給料及び賞与は、法人と使用人の雇用契約に基づいて提供した労務の対価として支払われるものであるから、役員報酬、従業員給料及び賞与(以下「役員報酬等」という。)は、時の経過に応じて自動的に費用化される性質のものではなく、役員及び従業員が、業務の執行や労務の提供(以下「労務の提供等」という。)をして、その職務等を全うすることによって初めて、役員及び従業員は役員報酬等を法人に請求することができ、法人においては、その時に支払債務が確定することになる。
そうすると、本件各役員報酬等は、その支払事業年度の翌事業年度に対応する費用であり、各支払事業年度終了の日までに、労務の提供等がされていないから、本件債務通達の給付原因発生要件を満たしているとはいえず、請求人の支払債務は確定していないことになる。
したがって、本件各役員報酬等は、各支払事業年度の損金の額に算入すべき金額とはならない。
B 本件前払通達の後段の適用
請求人は、仮に本件各役員報酬等が各支払事業年度の翌事業年度に対応する費用であるとしても、本件前払通達が定める後段の取扱いの要件を充足しているから、本件各役員報酬等を各支払事業年度の損金の額に算入することができる旨主張する。
しかしながら、本件前払通達の後段の取扱いは、前段で定められた前払費用に係る費用収益対応の原則の例外であり、この例外を認める根拠は、「重要性の原則」(企業の会計処理の基準となる原則の1つで、重要性の乏しいものについては本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることを認める旨の原則をいう。以下同じ。)に基づく会計処理を、税務においても認めたものであると解されている。
これを本件についてみると、本件各役員報酬等は、課税所得の計算上重要性が乏しいとは到底いえないから、本件前払通達の後段の取扱いの適用を受けることはできない。
したがって、請求人の主張には理由がない。
(ロ)本件各賦課決定処分
上記(イ)のとおり、平成10年4月期及び平成11年4月期に係る各更正処分は適法であり、また、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、平成10年4月期については同条第1項及び第2項の、平成11年4月期については同条第1項の規定に基づいて行った本件各賦課決定処分は、いずれも適法である。
(2)請求人の主張
原処分は、次の理由により違法であるから、その全部の取消しを求める。
イ 本件各更正処分
本件各役員報酬等は、以下の理由により、その支払事業年度の損金の額に算入すべきである。
(イ)債務の確定
A 法人税法第22条第3項の解釈及び適用
法人税法第22条第3項は、債務の確定という法人税法特有の概念を用いて、企業会計上当該事業年度の費用とされるものであっても、債務の確定がないものについては、法人税法に特段の定めがあるものを除き、法人税法上、損金として取り扱われないことを定めている。
このように、法人税法が、損金の額に算入すべき金額について、債務の確定なる概念を特に要求しているのは、費用を、単に会計的事実によってではなく、何らかの法的な債権債務関係によってとらえようとする立場を採っているからであり、法人が計上した費用が企業会計上は期間に対応していないとしても、必ずしも法人税法上の損金にならないわけではない。
B 本件における「債務の確定」
(A)原処分庁は、役員報酬等が、時の経過に応じて自動的に費用化される性質のものではなく、役員及び従業員が、労務の提供等をして、その職務を全うすることによって初めて、請求することができ、法人の支払義務もその時に確定するものである旨主張する。
(B)確かに、会社と役員及び従業員との間に法律の規定と異なる特段の取決めがない場合には、原処分庁が主張するように取り扱うべきである。
しかしながら、本件については、臨時株主総会議事録、本件各合意書及び本件各承諾書における特段の取決め(以下「本件取決め」という。)があることによって、本件各役員報酬等の支払対象である役員(以下「本件役員」という。)及び本件従業員は、その職務等を全うする前に、上記の特段の取決めを根拠に、本件各役員報酬等の支払を求めることができ、また、請求人は、当該求めに応じて支払う義務を負い、請求人は、実際に当該支払義務に基づいて、本件役員及び本件従業員に対して手形を振り出しているのである。
したがって、請求人の債務は確定したものであるといえる。
C これに対して、原処分庁は、本件各役員報酬等に係る債務について、当該事業年度終了の日までに本件債務通達の給付原因発生要件を満たしているとはいえず、請求人の支払債務は確定していないと主張する。
しかしながら、上記Bの(B)のとおり、本件各役員報酬等は、本件取決めによって、各支払事業年度終了の日までにその債務が確定し、本件債務通達を充足しているにもかかわらず、翌事業年度に対応する費用であるという理由だけでその事実を否定するのは、私的自治という私法取引の大原則を無視した重大な誤りであり、違法なものである。
D 以上のとおりであり、本件各役員報酬等は、それが翌事業年度に対応する費用かどうかに関係なく、各支払事業年度において、本件取決めによる支払義務があるから、上記のとおり法人税法に内在する「法的な債権債務関係」に基づき、各支払事業年度の損金とすべきである。
(ロ)本件前払通達の後段の適用
仮に、本件各役員報酬等が支払事業年度の翌事業年度に対応する費用であるとしても、本件各役員報酬等は、本件前払通達の後段の取扱いが定める費用等に該当するから、各支払事業年度の損金の額に算入すべきである。
A 本件前払通達の後段は、期間対応していない費用であっても、〔1〕支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係る前払費用であること、〔2〕支払った額に相当する金額を継続してその支払事業年度の損金の額に算入していること、この2つの要件を満たすものについては、支払事業年度の損金の額に算入することを認める旨定めているところ、原処分庁は、当該後段の取扱いについては、重要性の原則から逸脱しない限度でその適用が認められるものである旨主張する。
B しかし、本件前払通達の後段の取扱いには、「重要性の乏しいものを対象にする。」あるいは「重要性の高いものは除外する。」などという文言はないのに、課税当局が、恣意的に「重要性の有無」という尺度で適用対象を判断することになると、納税者の税額確定における予測可能性が担保されないことになる。
このような公権力による恣意的な課税は、日本国憲法の要請する租税法律主義に反することとなり、違憲である。
C また、仮に、本件前払通達の後段の取扱いが重要性の原則に基づくものであるとしても、次のとおり、本件各役員報酬等について適用がないとする理由が不明確である。
(A)原処分庁は、請求人が、支払事業年度の翌事業年度に係る前払家賃を、その支払った日の属する各事業年度の損金の額に算入しているにもかかわらず、本件各更正処分の対象とはしていない。
(B)また、原処分庁は、本件各役員報酬等について、役務提供の内容が翌事業年度に対応するものであるからという理由で、その各支払事業年度の損金の額への算入を認めない。
(C)原処分庁が、このように矛盾した取扱いをし、その主張する「重要性の原則」についての具体的な適用基準を明確にしないまま、本件前払通達の後段の取扱いを適用するか否かの判断をしていることは、原処分庁が通達を単なる課税の道具としかとらえていないことを示しており、租税法規の補完である通達の性格に反し、租税法律主義にも違反しているから、違法である。
(ハ)以上のとおり、本件各更正処分は、法人税法第22条第3項及び本件前払通達の解釈から不適法であり、取り消すべきである。
ロ 本件各賦課決定処分
上記イのとおり、本件各更正処分は違法であるから、本件各賦課決定処分は、いずれもその全部を取り消すべきである。
3 判断
(1)平成12年4月期に係る更正処分
平成12年4月期については、別表1のとおり、原処分庁が行った上記の更正処分によっても、請求人が納付すべき税額が増加しないことから、当該更正処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益が認められない。
したがって、当該更正処分に対する審査請求は、不適法であり、却下するのが相当である。
(2)平成10年4月期及び平成11年4月期に係る更正処分
イ 債務の確定
(イ)法人税法第22条第3項第2号は、上記1の(3)のイのとおり、内国法人の各事業年度の損金の額に算入すべき金額について、費用等の額で、かつ、償却費以外の費用の場合には当該事業年度終了の日までに債務の確定しているものとする旨規定している。
そして、この「債務の確定しているもの」に係る判定については、本件債務通達が、上記1の(3)のロのとおり、別に定めるものを除き、当該事業年度終了の日までに確定債務3要件のすべてに該当することをもって、「債務の確定しているもの」と判定する旨定めているところ、当審判所においても、課税の公平を図り、所得計算は可能な限り客観的に覚知し得る事実関係に基づいて行われるべきであるという観点から、本件債務通達の取扱いを相当と認める。
そうすると、費用等を損金の額に算入するためには、当該費用等を損金の額に算入しようとする事業年度終了の日までに、単に債務が成立しているということだけでは足りず、確定債務3要件のうちの他の2要件である給付原因発生要件及び合理的算定要件をも充足することにより、債務が確定することが必要である。
(ロ)本件における債務の確定
A 請求人は、本件各役員報酬等について、法人とその役員及び従業員との間に法律の規定と異なる特段の取決めがない場合には、原処分庁が主張するように取り扱うべきであるが、本件取決めによって、各支払事業年度終了の日までにその債務が確定しているのであるから、当該各支払事業年度の損金に算入すべきである旨主張する。
B 確かに、請求人が主張するように、本件取決めによって、請求人と本件役員及び本件従業員との間において、請求人がいう法的な債務が成立し、本件各役員報酬等が具体的に支払われていることが認められる。
しかしながら、本件各役員報酬等が、法人税法上いずれの事業年度の損金の額に算入されるべきかを判断するに当たっては、本件取決めの有無、内容及び法的性格等を考慮しつつも、あくまでも上記1の(3)のイないしハの法人税に関する法令等の規定に従って、上記(イ)のとおり、法人税法が要件としている債務が確定しているかどうかを検討すべきである。
C そうすると、請求人が本件各役員報酬等をその支払事業年度である本件各事業年度の損金の額に算入するためには、本件各事業年度終了の日までに確定債務3要件すべてを充足しなければならないところ、上記1の(4)のとおり、本件取決めによっても、辞任や退職等によって労務の提供等がされない場合には、役員報酬等の支払義務が生じないことと定められていることからしても、後記Dの金額を除いた本件各役員報酬等は、それぞれ本件各事業年度の翌事業年度において役務の提供等を受けることを具体的な給付をすべき原因として支出されたものであるから、給付原因発生要件を充足しているとは認められない。
したがって、請求人が平成10年4月期及び平成11年4月期の損金の額に算入した本件各役員報酬等の金額は、後記Dの金額を除いて、それぞれ平成10年4月期及び平成11年4月期の各事業年度終了の日までに、当該事業年度の損金の額に算入すべき債務が確定しているものとは認められないので、具体的に役務の提供等を受けた事業年度の損金の額に算入すべきである。
D 他方、10年4月役員報酬及び11年4月役員報酬のうち別表4の1及び2の各「〔2〕」欄に記載された金額は、上記1の(4)のとおり、平成10年4月期及び平成11年4月期に対応する費用等の金額であり、確定債務3要件を充足していると認められることから、それぞれの金額を各事業年度の損金の額に算入することが相当である。
ロ 本件前払通達
(イ)本件前払通達の後段の取扱い
A 前払費用は、企業会計上、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合において、いまだ提供されていない役務に対して支払われる対価で、時間の経過とともに次期以降の費用となるものをいう。また、前払費用のうち、重要性の乏しいものについては、重要性の原則から、これを経過勘定項目として処理しないことができるとされ、その代表的なものは、未経過保険料、未経過利息、前払賃借料等で、時の経過に応じて自動的、合理的に費用化されるものである。
B そして、前払費用は、本来、その支出事業年度の損金に算入されないのが原則であるが、本件前払通達は、上記Aのような企業会計の趣旨から、法人税法第22条第4項に規定する一般に公正妥当と認められる会計処理の基準といえる重要性の原則に沿う限りにおいて、後段の取扱いを例外として適用する旨定めているものと解される。
C そうすると、本件前払通達の後段の取扱いは、重要性の原則の範囲内においてその適用が認められるべきものであり、同原則の範囲内か否かの判断に当たっては、前払費用の金額だけではなく、当該法人の財務内容に占める割合や影響等も含めて総合的に考慮する必要があると考えるべきである。
D これに対して、請求人は、〔1〕本件前払通達の後段の取扱いには「重要性の乏しいものを対象にする。」などの文言はなく、「重要性の有無」で適用対象を判断すると納税者の予測可能性が担保されなくなること、〔2〕本件前払通達の後段の取扱いを具体的な適用基準を明確にしないまま適用するのは、租税法規の補完という通達の性格に反することを理由として、租税法律主義に反する旨主張する。
しかしながら、このような重要性の原則は、企業会計上の明確な原則であり、その適用範囲も合理的に判断できるものであるから、本件前払通達の後段の取扱いが重要性の原則に基づくことやその判断基準が本件前払通達に明示されていないからといって、租税法律主義に反するとはいえない。
(ロ)本件各役員報酬等に対する本件前払通達の後段の取扱いの適用
上記(イ)のCの基準に照らして、本件前払通達の後段の取扱いが、本件各役員報酬等に適用されるか否かについて、以下検討する。
A 請求人は、本件各役員報酬等が、本件前払通達の後段の取扱いの各要件に該当するので、後段の取扱いが適用され、本件各事業年度の損金の額へ算入すべきである旨主張する。
B しかしながら、本件各役員報酬は請求人の業務を執行したことに対する対価として、本件各給料及び本件各賞与は請求人の指揮命令の下に労務を提供したことに対する対価として、それぞれ支払われるものであって、このような人件費は、企業が営利活動を行う上で必要なものであり、企業活動の根幹に係る行為に対する対価であることからすると、会計科目としての重要性を有するといえる。
また、請求人の本件各事業年度の申告所得金額に対する人件費(請求人が決算書に記載している「給与」金額をいい、以下同じ。)の割合は、おおむね314.3ないし853.2%、売上金額に対する人件費の割合は、おおむね52.5ないし56.3%で、本件各事業年度に係る人件費のうちに本件各役員報酬等の金額が占める割合も、おおむね31.0ないし40.7%と、高率かつ可変的であり、金額的にみても重要性を有するといえる。
そうすると、本件各役員報酬等は、時の経過に応じて自動的、合理的に費用化されるような重要性の乏しい費用とは本質的にその性質を異にするものであると認められ、本件各役員報酬等に対して、本件前払通達の後段の取扱いを適用することはできないと解するのが相当である。
したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。
ハ 以上のことから、請求人が平成10年4月期及び平成11年4月期の損金の額に算入した本件各役員報酬等の金額は、上記イの(ロ)のDの金額を除き、いずれも当該事業年度の損金の額に算入されない費用等として取り扱うのが相当である。
なお、9年4月役員報酬の合計金額のうち、別表4の3の「〔3〕」欄に記載された金額は、平成10年4月期に対応する費用等の金額であるから、同事業年度の損金の額に算入すべき費用等として取り扱うのが相当である。
(3)平成10年4月期及び平成11年4月期の所得金額及び税額
イ 平成10年4月期
(イ)請求人の平成10年4月期の所得金額は、別表5の1のとおり、更正処分前の請求人の平成10年4月期の所得金額である別表1の「確定申告」欄の○○○○円に、平成11年4月期に対応する費用等の金額に当たる〔1〕10年4月役員報酬の合計金額のうち別表4の1の「〔3〕」欄の金額25,398,050円、〔2〕10年4月給料の合計金額14,983,200円及び〔3〕10年4月賞与の合計金額1,205,000円を加算し、平成10年4月期に対応する費用等の金額に当たる、9年4月役員報酬の合計金額のうち別表4の3の「〔3〕」欄の金額25,398,050円を減算した、○○○○円となる。
(ロ)そして、上記(イ)の所得金額に対する請求人の納付すべき法人税額(差引合計税額)は、11,583,000円となる。
なお、原処分庁は、法人税法第67条《同族会社の特別税率》の適用に当たり、平成10年4月期に留保した金額から9年4月役員報酬の合計金額を減算していないが、9年4月役員報酬の合計金額のうち平成10年4月期の損金の額に算入される金額25,398,050円は、平成10年4月期の留保金額を算定する上で、同期に留保した金額から控除されるべきである。
(ハ)そうすると、請求人の納付すべき法人税額は、平成10年4月期に係る更正処分の額を下回るから、平成10年4月期に係る更正処分は、その一部を取り消すべきである。
ロ 平成11年4月期
(イ)請求人の平成11年4月期の所得金額は、別表5の2のとおり、更正処分前の請求人の平成11年4月期の所得金額である別表1の「確定申告」欄の○○○○円に、平成12年4月期に対応する費用等の金額に当たる〔1〕11年4月役員報酬の合計金額のうち別表4の2の「〔3〕」欄の金額25,754,096円、〔2〕11年4月給料の合計金額21,392,400円及び〔3〕11年4月賞与の合計金額4,540,000円を加算し、平成11年4月期に対応する費用等の金額に当たる〔4〕10年4月役員報酬の合計金額のうち別表4の1の「〔3〕」欄の金額25,398,050円、〔5〕10年4月給料の合計金額14,983,200円、〔6〕10年4月賞与の合計金額1,205,000円及び〔7〕上記イで認定した所得に基づいて、新たに平成10年4月期の損金の額に算入される事業税の金額1,942,600円を減算した、○○○○円となる。
(ロ)そして、上記(イ)の所得金額に対する請求人の納付すべき法人税額(差引合計税額)は、8,478,300円となる。
(ハ)そうすると、請求人の納付すべき法人税額は平成11年4月期に係る更正処分の額を下回るから、平成11年4月期に係る更正処分はその一部を取り消すべきである。
ハ 本件各賦課決定処分
平成10年4月期及び平成11年4月期に係る更正処分は、上記イの(ハ)及びロの(ハ)のとおり、いずれもその一部を取り消すべきであり、過少申告加算税の賦課決定処分の基礎となる税額は、平成10年4月期が6,400,000円、平成11年4月期が2,940,000円となる。
また、この税額の計算の基礎となった事実については、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。
したがって、請求人の過少申告加算税の額は、平成10年4月期が701,000円、平成11年4月期が294,000円となる。
そうすると、平成10年4月期については、賦課決定処分の額を下回ることから、平成10年4月期の過少申告加算税の賦課決定処分は、その一部を取り消すべきである。
他方、平成11年4月期については、賦課決定処分の額と同額であるから、平成11年4月期の過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。
(4)その他
原処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。
上記、裁決事例より、重要性についての見解を窺うことができるものである。

↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。

↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。

まず、法人税法基本通達2-2-14(短期前払費用)を確認することとする。
(短期の前払費用)
2−2−14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2−2−14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2−8「七」により追加、昭61年直法2−12「二」により改正)
(注)例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。
次に、国税庁の質疑応答事例について確認する。
【照会要旨】
当事者間の契約により、年1回3月決算の法人が次のような支払を継続的に行うこととしているものについては、法人税基本通達2−2−14((短期の前払費用))を適用し、その支払額の全額をその支払った日の属する事業年度において損金の額に算入して差し支えありませんか。
事例1:期間40年の土地賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の地代月額1,000,000円を支払う。
事例2:期間20年の土地賃借に係る賃料について、毎年、地代年額(4月から翌年3月)241,620円を3月末に前払により支払う。
事例3:期間2年(延長可能)のオフィスビルフロアの賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の家賃月額611,417円を支払う。
事例4:期間4年のシステム装置のリース料について、12ケ月分(4月から翌年3月)379,425円を3月下旬に支払う。
事例5:期間10年の建物賃借に係る賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月)1,000,000円を2月に前払により支払う。
【回答要旨】
・ 事例1から事例4までについては、照会意見のとおりで差し支えありません。
・ 事例5については、法人税基本通達2−2−14の適用が認められません。
(理由)
(1) 本通達の趣旨について
本通達は、1年以内の短期前払費用について、収益との厳密な期間対応による繰延経理をすることなく、その支払時点で損金算入を認めるというものであり、企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるというものです。
(2) 照会に対する考え方について
事例1から事例4までについては、基本的には、これを認めることが相当と考えられますが、一方では、利益が出たから今期だけまとめて1年分支払うというような利益操作のための支出や収益との対応期間のズレを放置すると課税上の弊害が生ずると認められるものについては、これを排除していく必要があります。
このため、継続的な支払を前提条件とすることや収入との直接的な見合関係にある費用については本通達の適用対象外とするということは、従来と同様、当然に本通達の適用に当たって必要とされるのですが、これに加え、役務の受入れの開始前にその対価の支払が行われ、その支払時から1年を超える期間を対価支払の対象期間とするようなものは、何らかの歯止めを置いた上で本通達の適用を認めることが相当と考えられます。
【関係法令通達】
法人税基本通達2−2−14
注記
平成20年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるというものであるが、重要性についての裁決を国税不服審判所の裁決事例より抜粋した。
当該事業年度末に約束手形で支給された翌事業年度の年俸制に係る役員報酬及び従業員給与については、当該事業年度内に具体的な役務提供がされておらず、また、会計上重要性の乏しい費用とは認められないから、当該事業年度の損金の額に算入できないとした事例
▼ 裁決事例集 No.65 - 343頁
請求人は、臨時株主総会又は従業員との間の合意による役員報酬又は従業員給与の年俸額(以下「本件役員報酬等」という。)に係る損金算入につき、本件役員報酬等を12で除した月割額から社会保険料等を控除した金額を券面額とする12枚の約束手形を振り出し、当該各事業年度内に支払っているから、その債務は当該事業年度の終了の日までに確定しており、仮にそうでないとしても、本件役員報酬等は支払いの日から1年以内に役務提供を受ける短期前払費用であり、法人税法基本通達2−2−14の後段の取扱い(以下「本件取扱い」という。)が適用されるから、たとえそれがその翌事業年度の業務執行等の役務に対応するものであっても、それは当該事業年度の損金の額に算入される旨主張する。
しかしながら、本件役員報酬等については、その具体的な給付をなすべき原因である役員の職務執行又は従業員の役務提供が当該事業年度の終了の日までになされていないから、その債務が確定しているとは認められず、また、本件役員報酬等は、請求人の財務内容に占める割合などからして、重要性の乏しい費用とは認められないため、本件役員報酬等には本件取扱いの適用がなく、したがって、それを当該事業年度の損金の額に算入することはできない。
平成15年2月20日裁決
(平15.2.20裁決、裁決事例集No.65 343頁)
《裁決書(抄)》
1 事実
(1)事案の概要
本件は、写真製版業及び出版業を営む同族会社である審査請求人(以下「請求人」という。)が、翌事業年度に対応する役員報酬等を事業年度終了の日までに一括して支払ったことについて、当該役員報酬等をいつの事業年度の損金の額に算入すべきであるかが争われた事案である。
(2)審査請求に至る経緯
イ 請求人は、平成9年5月1日から平成10年4月30日まで、平成10年5月1日から平成11年4月30日まで及び平成11年5月1日から平成12年4月30日までの各事業年度(以下、順次「平成10年4月期」、「平成11年4月期」及び「平成12年4月期」といい、これらを併せて「本件各事業年度」という。)の法人税について、青色の確定申告書に別表1の「確定申告」欄のとおり記載して、いずれも法定申告期限までに申告した。
ロ 原処分庁は、これに対し、平成13年5月21日付で、別表1の「更正処分等」欄のとおりの各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)をした。
ハ 請求人は、原処分を不服として、平成13年7月17日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、同年10月15日付で、平成10年4月期及び平成11年4月期の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分に対する異議申立てをいずれも棄却し、平成12年4月期の更正処分に対する異議申立てを却下する異議決定をした。
ニ 請求人は、異議決定を経た後の原処分に不服があるとして、平成13年11月14日に審査請求をした。
(3)関係法令等
イ 法人税法(平成12年法律第97号による改正前のもの。以下同じ。)第22条《各事業年度の所得の金額の計算》
法人税法第22条第3項第2号は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額として、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(以下「費用等」という。)の額を掲げるとともに、その費用等の範囲について、償却費以外の費用の場合には、当該事業年度終了の日までに債務の確定しているものとする旨規定している。
ロ 法人税基本通達2−2−12《債務の確定の判定》(以下「本件債務通達」という。)
本件債務通達は、上記イの「当該事業年度終了の日までに債務の確定しているもの」とは、別に定めるものを除き、当該事業年度終了の日までに、〔1〕当該費用に係る債務が成立していること(以下「債務成立要件」という。)、〔2〕当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること(以下「給付原因発生要件」という。)及び〔3〕その金額を合理的に算定することができるものであること(以下「合理的算定要件」といい、債務成立要件及び給付原因発生要件と併せて「確定債務3要件」という。)の3つの要件をすべて満たしている場合をいう旨定めている。
ハ 法人税基本通達2−2−14《短期の前払費用》(以下「本件前払通達」という。)
本件前払通達は、その前段において、前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていないものをいう。以下同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないとの原則を定めるとともに、その後段において、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める旨の取扱い(以下「後段の取扱い」という。)を定めている。
(4)基礎事実
以下の事実は、請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所が調査したところによっても、その事実が認められる。
イ 役員報酬
(イ)請求人の平成9年4月25日付の臨時株主総会議事録には、役員報酬について、要旨次のとおり決議された旨の記載がある。
A 取締役の平成9年4月26日から平成10年4月25日までの年俸額(以下「9年4月役員報酬」という。)は、Gが18,000,000円、Hが7,750,800円。
B 当該取締役が、上記Aの期間中に辞任するか解任された場合は、原則として、年俸額を日数按分する。
(ロ)請求人の平成10年4月24日付の臨時株主総会議事録には、役員報酬について、要旨次のとおり決議された旨の記載がある。
A 取締役の平成10年4月26日から平成11年4月25日までの年俸額(以下「10年4月役員報酬」という。)は、Gが18,000,000円、Hが7,750,800円。
B 当該取締役が、上記Aの期間中に辞任するか解任された場合は、原則として、年俸額を日数按分する。
(ハ)請求人の平成11年4月23日付の臨時株主総会議事録には、役員報酬について、要旨次のとおり決議された旨の記載がある。
A 取締役の平成11年4月26日から平成12年4月25日までの年俸額(以下「11年4月役員報酬」という。)は、Gが18,000,000円、Hが8,110,800円。
B 当該取締役が、上記Aの期間中に辞任するか解任された場合は、原則として、年俸額を日数按分する。
(ニ)請求人の平成12年4月25日付の臨時株主総会議事録には、役員報酬について、要旨次のとおり決議された旨の記載がある。
A 取締役の平成12年4月26日から平成13年4月25日までの年俸額(以下「12年4月役員報酬」といい、「10年4月役員報酬」及び「11年4月役員報酬」と併せて「本件各役員報酬」という。)は、Gが18,000,000円、Hが8,110,800円。
B 当該取締役が、上記Aの期間中に辞任するか解任された場合は、原則として、年俸額を日数按分する。
(ホ)請求人は、9年4月役員報酬の合計金額25,750,800円、10年4月役員報酬の合計金額25,750,800円、11年4月役員報酬の合計金額26,110,800円及び12年4月役員報酬の合計金額26,110,800円を、それぞれ平成8年5月1日から平成9年4月30日までの事業年度(以下「平成9年4月期」という。)、平成10年4月期、平成11年4月期及び平成12年4月期の損金の額に算入した。
(ヘ)請求人は、上記(ホ)の各金額を、それぞれ平成9年4月25日、平成10年4月25日、平成11年4月25日及び平成12年4月25日に、社会保険料等として控除する金額を差し引いた残額の12分の1を額面金額とする12枚の約束手形を振り出して支給した。
なお、約束手形の決済期日は、各年5月25日以降の各月の25日である。
ロ 従業員給与
(イ)年俸制に関する合意書
請求人が、従業員(以下「本件従業員」という。)との間で締結した平成10年4月24日付、平成11年4月26日付及び平成12年4月25日付の年俸制に関する各合意書(以下「本件各合意書」という。)には、要旨別表2及び次のAないしCのとおりの内容が記載されている(以下、本件各合意書の各日付に従い、本件各合意書記載の年俸を順次「10年4月給料」、「11年4月給料」及び「12年4月給料」といい、これらを併せて「本件各給料」という。)。
A 本件従業員は、請求人に対して、年俸対象期間中において、その労務を誠実に提供しなければならない。ただし、年俸対象期間中に本件従業員が退職する場合は、本件従業員は、退職後は労務を提供しないことになるので、退職月後に決済される予定の月割額を受給する権利はない(本件各合意書の第4条)。
B 請求人は、本件従業員に対し、年俸金額を12で除した額を毎月28日に支払う(本件各合意書の第3条第1項)。
C 請求人は、本件従業員に対して、年俸金額の月割額から控除すべき金額を差し引いた残額を額面金額とする約束手形で支払う(本件各合意書の第3条第2項)。
(ロ)請求人は、10年4月給料の合計金額14,983,200円、11年4月給料の合計金額21,392,400円及び12年4月給料の合計金額18,177,600円を、それぞれ平成10年4月期、平成11年4月期及び平成12年4月期の損金の額に算入した。
(ハ)請求人は、本件各合意書の内容(上記(イ)のB及びC)に応じた約束手形を振り出した。
(ニ)承諾書
本件従業員が請求人に対して提出した平成10年4月24日付、平成11年4月26日付及び平成12年4月25日付の各承諾書(以下「本件各承諾書」という。)には、別表3の内容を承諾する旨の記載がある(以下、本件各承諾書の各日付に従い、本件各承諾書記載の賞与を順次「10年4月賞与」、「11年4月賞与」及び「12年4月賞与」といい、これらを併せて「本件各賞与」という。)。
(ホ)請求人は、10年4月賞与の合計金額1,205,000円、11年4月賞与の合計金額4,540,000円及び12年4月賞与の合計金額4,140,000円を、それぞれ平成10年4月期、平成11年4月期及び平成12年4月期の損金の額に算入した。
なお、請求人は、平成9年4月期において、平成10年4月期に対応する給料及び賞与を損金の額に算入していない。
2 主張
(1)原処分庁の主張
イ 平成12年4月期に係る更正処分
平成12年4月期に係る更正処分は、当該事業年度の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものではないから、当該更正処分に対する審査請求は不適法である。
よって、当該審査請求を却下するとの裁決を求める。
ロ 原処分のうち上記イ以外の各処分
原処分のうち上記イ以外の各処分は、次の理由により適法であるから、当該各処分に係る審査請求をいずれも棄却するとの裁決を求める。
(イ)平成10年4月期及び平成11年4月期に係る各更正処分
本件各役員報酬、本件各給料及び本件各賞与(以下、これらを併せて「本件各役員報酬等」という。)は、以下の理由により、その支払った日の属する事業年度(以下「支払事業年度」という。)の損金の額に算入すべきではなく、その翌事業年度の損金の額に算入すべきである。
A 債務の確定
費用等が法人税法第22条第3項第2号の債務の確定したものとして損金の額に算入すべき金額となるためには、本件債務通達の定める確定債務3要件を満たす必要がある。
また、役員報酬は、役員が株主からの委任を受けて業務を執行したことの対価として支払われるものであり、また、従業員給料及び賞与は、法人と使用人の雇用契約に基づいて提供した労務の対価として支払われるものであるから、役員報酬、従業員給料及び賞与(以下「役員報酬等」という。)は、時の経過に応じて自動的に費用化される性質のものではなく、役員及び従業員が、業務の執行や労務の提供(以下「労務の提供等」という。)をして、その職務等を全うすることによって初めて、役員及び従業員は役員報酬等を法人に請求することができ、法人においては、その時に支払債務が確定することになる。
そうすると、本件各役員報酬等は、その支払事業年度の翌事業年度に対応する費用であり、各支払事業年度終了の日までに、労務の提供等がされていないから、本件債務通達の給付原因発生要件を満たしているとはいえず、請求人の支払債務は確定していないことになる。
したがって、本件各役員報酬等は、各支払事業年度の損金の額に算入すべき金額とはならない。
B 本件前払通達の後段の適用
請求人は、仮に本件各役員報酬等が各支払事業年度の翌事業年度に対応する費用であるとしても、本件前払通達が定める後段の取扱いの要件を充足しているから、本件各役員報酬等を各支払事業年度の損金の額に算入することができる旨主張する。
しかしながら、本件前払通達の後段の取扱いは、前段で定められた前払費用に係る費用収益対応の原則の例外であり、この例外を認める根拠は、「重要性の原則」(企業の会計処理の基準となる原則の1つで、重要性の乏しいものについては本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることを認める旨の原則をいう。以下同じ。)に基づく会計処理を、税務においても認めたものであると解されている。
これを本件についてみると、本件各役員報酬等は、課税所得の計算上重要性が乏しいとは到底いえないから、本件前払通達の後段の取扱いの適用を受けることはできない。
したがって、請求人の主張には理由がない。
(ロ)本件各賦課決定処分
上記(イ)のとおり、平成10年4月期及び平成11年4月期に係る各更正処分は適法であり、また、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、平成10年4月期については同条第1項及び第2項の、平成11年4月期については同条第1項の規定に基づいて行った本件各賦課決定処分は、いずれも適法である。
(2)請求人の主張
原処分は、次の理由により違法であるから、その全部の取消しを求める。
イ 本件各更正処分
本件各役員報酬等は、以下の理由により、その支払事業年度の損金の額に算入すべきである。
(イ)債務の確定
A 法人税法第22条第3項の解釈及び適用
法人税法第22条第3項は、債務の確定という法人税法特有の概念を用いて、企業会計上当該事業年度の費用とされるものであっても、債務の確定がないものについては、法人税法に特段の定めがあるものを除き、法人税法上、損金として取り扱われないことを定めている。
このように、法人税法が、損金の額に算入すべき金額について、債務の確定なる概念を特に要求しているのは、費用を、単に会計的事実によってではなく、何らかの法的な債権債務関係によってとらえようとする立場を採っているからであり、法人が計上した費用が企業会計上は期間に対応していないとしても、必ずしも法人税法上の損金にならないわけではない。
B 本件における「債務の確定」
(A)原処分庁は、役員報酬等が、時の経過に応じて自動的に費用化される性質のものではなく、役員及び従業員が、労務の提供等をして、その職務を全うすることによって初めて、請求することができ、法人の支払義務もその時に確定するものである旨主張する。
(B)確かに、会社と役員及び従業員との間に法律の規定と異なる特段の取決めがない場合には、原処分庁が主張するように取り扱うべきである。
しかしながら、本件については、臨時株主総会議事録、本件各合意書及び本件各承諾書における特段の取決め(以下「本件取決め」という。)があることによって、本件各役員報酬等の支払対象である役員(以下「本件役員」という。)及び本件従業員は、その職務等を全うする前に、上記の特段の取決めを根拠に、本件各役員報酬等の支払を求めることができ、また、請求人は、当該求めに応じて支払う義務を負い、請求人は、実際に当該支払義務に基づいて、本件役員及び本件従業員に対して手形を振り出しているのである。
したがって、請求人の債務は確定したものであるといえる。
C これに対して、原処分庁は、本件各役員報酬等に係る債務について、当該事業年度終了の日までに本件債務通達の給付原因発生要件を満たしているとはいえず、請求人の支払債務は確定していないと主張する。
しかしながら、上記Bの(B)のとおり、本件各役員報酬等は、本件取決めによって、各支払事業年度終了の日までにその債務が確定し、本件債務通達を充足しているにもかかわらず、翌事業年度に対応する費用であるという理由だけでその事実を否定するのは、私的自治という私法取引の大原則を無視した重大な誤りであり、違法なものである。
D 以上のとおりであり、本件各役員報酬等は、それが翌事業年度に対応する費用かどうかに関係なく、各支払事業年度において、本件取決めによる支払義務があるから、上記のとおり法人税法に内在する「法的な債権債務関係」に基づき、各支払事業年度の損金とすべきである。
(ロ)本件前払通達の後段の適用
仮に、本件各役員報酬等が支払事業年度の翌事業年度に対応する費用であるとしても、本件各役員報酬等は、本件前払通達の後段の取扱いが定める費用等に該当するから、各支払事業年度の損金の額に算入すべきである。
A 本件前払通達の後段は、期間対応していない費用であっても、〔1〕支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係る前払費用であること、〔2〕支払った額に相当する金額を継続してその支払事業年度の損金の額に算入していること、この2つの要件を満たすものについては、支払事業年度の損金の額に算入することを認める旨定めているところ、原処分庁は、当該後段の取扱いについては、重要性の原則から逸脱しない限度でその適用が認められるものである旨主張する。
B しかし、本件前払通達の後段の取扱いには、「重要性の乏しいものを対象にする。」あるいは「重要性の高いものは除外する。」などという文言はないのに、課税当局が、恣意的に「重要性の有無」という尺度で適用対象を判断することになると、納税者の税額確定における予測可能性が担保されないことになる。
このような公権力による恣意的な課税は、日本国憲法の要請する租税法律主義に反することとなり、違憲である。
C また、仮に、本件前払通達の後段の取扱いが重要性の原則に基づくものであるとしても、次のとおり、本件各役員報酬等について適用がないとする理由が不明確である。
(A)原処分庁は、請求人が、支払事業年度の翌事業年度に係る前払家賃を、その支払った日の属する各事業年度の損金の額に算入しているにもかかわらず、本件各更正処分の対象とはしていない。
(B)また、原処分庁は、本件各役員報酬等について、役務提供の内容が翌事業年度に対応するものであるからという理由で、その各支払事業年度の損金の額への算入を認めない。
(C)原処分庁が、このように矛盾した取扱いをし、その主張する「重要性の原則」についての具体的な適用基準を明確にしないまま、本件前払通達の後段の取扱いを適用するか否かの判断をしていることは、原処分庁が通達を単なる課税の道具としかとらえていないことを示しており、租税法規の補完である通達の性格に反し、租税法律主義にも違反しているから、違法である。
(ハ)以上のとおり、本件各更正処分は、法人税法第22条第3項及び本件前払通達の解釈から不適法であり、取り消すべきである。
ロ 本件各賦課決定処分
上記イのとおり、本件各更正処分は違法であるから、本件各賦課決定処分は、いずれもその全部を取り消すべきである。
3 判断
(1)平成12年4月期に係る更正処分
平成12年4月期については、別表1のとおり、原処分庁が行った上記の更正処分によっても、請求人が納付すべき税額が増加しないことから、当該更正処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益が認められない。
したがって、当該更正処分に対する審査請求は、不適法であり、却下するのが相当である。
(2)平成10年4月期及び平成11年4月期に係る更正処分
イ 債務の確定
(イ)法人税法第22条第3項第2号は、上記1の(3)のイのとおり、内国法人の各事業年度の損金の額に算入すべき金額について、費用等の額で、かつ、償却費以外の費用の場合には当該事業年度終了の日までに債務の確定しているものとする旨規定している。
そして、この「債務の確定しているもの」に係る判定については、本件債務通達が、上記1の(3)のロのとおり、別に定めるものを除き、当該事業年度終了の日までに確定債務3要件のすべてに該当することをもって、「債務の確定しているもの」と判定する旨定めているところ、当審判所においても、課税の公平を図り、所得計算は可能な限り客観的に覚知し得る事実関係に基づいて行われるべきであるという観点から、本件債務通達の取扱いを相当と認める。
そうすると、費用等を損金の額に算入するためには、当該費用等を損金の額に算入しようとする事業年度終了の日までに、単に債務が成立しているということだけでは足りず、確定債務3要件のうちの他の2要件である給付原因発生要件及び合理的算定要件をも充足することにより、債務が確定することが必要である。
(ロ)本件における債務の確定
A 請求人は、本件各役員報酬等について、法人とその役員及び従業員との間に法律の規定と異なる特段の取決めがない場合には、原処分庁が主張するように取り扱うべきであるが、本件取決めによって、各支払事業年度終了の日までにその債務が確定しているのであるから、当該各支払事業年度の損金に算入すべきである旨主張する。
B 確かに、請求人が主張するように、本件取決めによって、請求人と本件役員及び本件従業員との間において、請求人がいう法的な債務が成立し、本件各役員報酬等が具体的に支払われていることが認められる。
しかしながら、本件各役員報酬等が、法人税法上いずれの事業年度の損金の額に算入されるべきかを判断するに当たっては、本件取決めの有無、内容及び法的性格等を考慮しつつも、あくまでも上記1の(3)のイないしハの法人税に関する法令等の規定に従って、上記(イ)のとおり、法人税法が要件としている債務が確定しているかどうかを検討すべきである。
C そうすると、請求人が本件各役員報酬等をその支払事業年度である本件各事業年度の損金の額に算入するためには、本件各事業年度終了の日までに確定債務3要件すべてを充足しなければならないところ、上記1の(4)のとおり、本件取決めによっても、辞任や退職等によって労務の提供等がされない場合には、役員報酬等の支払義務が生じないことと定められていることからしても、後記Dの金額を除いた本件各役員報酬等は、それぞれ本件各事業年度の翌事業年度において役務の提供等を受けることを具体的な給付をすべき原因として支出されたものであるから、給付原因発生要件を充足しているとは認められない。
したがって、請求人が平成10年4月期及び平成11年4月期の損金の額に算入した本件各役員報酬等の金額は、後記Dの金額を除いて、それぞれ平成10年4月期及び平成11年4月期の各事業年度終了の日までに、当該事業年度の損金の額に算入すべき債務が確定しているものとは認められないので、具体的に役務の提供等を受けた事業年度の損金の額に算入すべきである。
D 他方、10年4月役員報酬及び11年4月役員報酬のうち別表4の1及び2の各「〔2〕」欄に記載された金額は、上記1の(4)のとおり、平成10年4月期及び平成11年4月期に対応する費用等の金額であり、確定債務3要件を充足していると認められることから、それぞれの金額を各事業年度の損金の額に算入することが相当である。
ロ 本件前払通達
(イ)本件前払通達の後段の取扱い
A 前払費用は、企業会計上、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合において、いまだ提供されていない役務に対して支払われる対価で、時間の経過とともに次期以降の費用となるものをいう。また、前払費用のうち、重要性の乏しいものについては、重要性の原則から、これを経過勘定項目として処理しないことができるとされ、その代表的なものは、未経過保険料、未経過利息、前払賃借料等で、時の経過に応じて自動的、合理的に費用化されるものである。
B そして、前払費用は、本来、その支出事業年度の損金に算入されないのが原則であるが、本件前払通達は、上記Aのような企業会計の趣旨から、法人税法第22条第4項に規定する一般に公正妥当と認められる会計処理の基準といえる重要性の原則に沿う限りにおいて、後段の取扱いを例外として適用する旨定めているものと解される。
C そうすると、本件前払通達の後段の取扱いは、重要性の原則の範囲内においてその適用が認められるべきものであり、同原則の範囲内か否かの判断に当たっては、前払費用の金額だけではなく、当該法人の財務内容に占める割合や影響等も含めて総合的に考慮する必要があると考えるべきである。
D これに対して、請求人は、〔1〕本件前払通達の後段の取扱いには「重要性の乏しいものを対象にする。」などの文言はなく、「重要性の有無」で適用対象を判断すると納税者の予測可能性が担保されなくなること、〔2〕本件前払通達の後段の取扱いを具体的な適用基準を明確にしないまま適用するのは、租税法規の補完という通達の性格に反することを理由として、租税法律主義に反する旨主張する。
しかしながら、このような重要性の原則は、企業会計上の明確な原則であり、その適用範囲も合理的に判断できるものであるから、本件前払通達の後段の取扱いが重要性の原則に基づくことやその判断基準が本件前払通達に明示されていないからといって、租税法律主義に反するとはいえない。
(ロ)本件各役員報酬等に対する本件前払通達の後段の取扱いの適用
上記(イ)のCの基準に照らして、本件前払通達の後段の取扱いが、本件各役員報酬等に適用されるか否かについて、以下検討する。
A 請求人は、本件各役員報酬等が、本件前払通達の後段の取扱いの各要件に該当するので、後段の取扱いが適用され、本件各事業年度の損金の額へ算入すべきである旨主張する。
B しかしながら、本件各役員報酬は請求人の業務を執行したことに対する対価として、本件各給料及び本件各賞与は請求人の指揮命令の下に労務を提供したことに対する対価として、それぞれ支払われるものであって、このような人件費は、企業が営利活動を行う上で必要なものであり、企業活動の根幹に係る行為に対する対価であることからすると、会計科目としての重要性を有するといえる。
また、請求人の本件各事業年度の申告所得金額に対する人件費(請求人が決算書に記載している「給与」金額をいい、以下同じ。)の割合は、おおむね314.3ないし853.2%、売上金額に対する人件費の割合は、おおむね52.5ないし56.3%で、本件各事業年度に係る人件費のうちに本件各役員報酬等の金額が占める割合も、おおむね31.0ないし40.7%と、高率かつ可変的であり、金額的にみても重要性を有するといえる。
そうすると、本件各役員報酬等は、時の経過に応じて自動的、合理的に費用化されるような重要性の乏しい費用とは本質的にその性質を異にするものであると認められ、本件各役員報酬等に対して、本件前払通達の後段の取扱いを適用することはできないと解するのが相当である。
したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。
ハ 以上のことから、請求人が平成10年4月期及び平成11年4月期の損金の額に算入した本件各役員報酬等の金額は、上記イの(ロ)のDの金額を除き、いずれも当該事業年度の損金の額に算入されない費用等として取り扱うのが相当である。
なお、9年4月役員報酬の合計金額のうち、別表4の3の「〔3〕」欄に記載された金額は、平成10年4月期に対応する費用等の金額であるから、同事業年度の損金の額に算入すべき費用等として取り扱うのが相当である。
(3)平成10年4月期及び平成11年4月期の所得金額及び税額
イ 平成10年4月期
(イ)請求人の平成10年4月期の所得金額は、別表5の1のとおり、更正処分前の請求人の平成10年4月期の所得金額である別表1の「確定申告」欄の○○○○円に、平成11年4月期に対応する費用等の金額に当たる〔1〕10年4月役員報酬の合計金額のうち別表4の1の「〔3〕」欄の金額25,398,050円、〔2〕10年4月給料の合計金額14,983,200円及び〔3〕10年4月賞与の合計金額1,205,000円を加算し、平成10年4月期に対応する費用等の金額に当たる、9年4月役員報酬の合計金額のうち別表4の3の「〔3〕」欄の金額25,398,050円を減算した、○○○○円となる。
(ロ)そして、上記(イ)の所得金額に対する請求人の納付すべき法人税額(差引合計税額)は、11,583,000円となる。
なお、原処分庁は、法人税法第67条《同族会社の特別税率》の適用に当たり、平成10年4月期に留保した金額から9年4月役員報酬の合計金額を減算していないが、9年4月役員報酬の合計金額のうち平成10年4月期の損金の額に算入される金額25,398,050円は、平成10年4月期の留保金額を算定する上で、同期に留保した金額から控除されるべきである。
(ハ)そうすると、請求人の納付すべき法人税額は、平成10年4月期に係る更正処分の額を下回るから、平成10年4月期に係る更正処分は、その一部を取り消すべきである。
ロ 平成11年4月期
(イ)請求人の平成11年4月期の所得金額は、別表5の2のとおり、更正処分前の請求人の平成11年4月期の所得金額である別表1の「確定申告」欄の○○○○円に、平成12年4月期に対応する費用等の金額に当たる〔1〕11年4月役員報酬の合計金額のうち別表4の2の「〔3〕」欄の金額25,754,096円、〔2〕11年4月給料の合計金額21,392,400円及び〔3〕11年4月賞与の合計金額4,540,000円を加算し、平成11年4月期に対応する費用等の金額に当たる〔4〕10年4月役員報酬の合計金額のうち別表4の1の「〔3〕」欄の金額25,398,050円、〔5〕10年4月給料の合計金額14,983,200円、〔6〕10年4月賞与の合計金額1,205,000円及び〔7〕上記イで認定した所得に基づいて、新たに平成10年4月期の損金の額に算入される事業税の金額1,942,600円を減算した、○○○○円となる。
(ロ)そして、上記(イ)の所得金額に対する請求人の納付すべき法人税額(差引合計税額)は、8,478,300円となる。
(ハ)そうすると、請求人の納付すべき法人税額は平成11年4月期に係る更正処分の額を下回るから、平成11年4月期に係る更正処分はその一部を取り消すべきである。
ハ 本件各賦課決定処分
平成10年4月期及び平成11年4月期に係る更正処分は、上記イの(ハ)及びロの(ハ)のとおり、いずれもその一部を取り消すべきであり、過少申告加算税の賦課決定処分の基礎となる税額は、平成10年4月期が6,400,000円、平成11年4月期が2,940,000円となる。
また、この税額の計算の基礎となった事実については、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。
したがって、請求人の過少申告加算税の額は、平成10年4月期が701,000円、平成11年4月期が294,000円となる。
そうすると、平成10年4月期については、賦課決定処分の額を下回ることから、平成10年4月期の過少申告加算税の賦課決定処分は、その一部を取り消すべきである。
他方、平成11年4月期については、賦課決定処分の額と同額であるから、平成11年4月期の過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。
(4)その他
原処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。
上記、裁決事例より、重要性についての見解を窺うことができるものである。
文責:法人ソリューション部
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。
09年08月25日
役員退職金の適正額の算定について
役員退職金は、
(1)退職者の過去の勤労に対する対価の後払い(費用性、賃金後払説)、
(2)退職者の在職中の功労に対する報酬(利益配分性、功労報償説)、
(3)将来の生活保障について考慮されたもの(生活保障説) 等
の性格を有するものです。
そういう内容だからこそ、役員の受け取る退職金は、所得税法上は通常の給与等とは異なり受取人にとって有利な課税体系となっており、また、法人税法上も「不相当に高額」「でなければ」、会社の損金(税務上の費用)にすることができます。
その役員退職金の適正額の決定については、通常の場合は、
(1)役員退職金規定にその支給限度額を定め(その計算方法は、平均功績倍率法(注1)が一般的です)、
(2)その限度額の範囲内で支給することを機関決定して支給することにより、
法人税法上の「不相当に高額でない水準」としているようです。
(注1)最終報酬月額×勤続年数×功績倍率により適正額を計算する方法です。最終報酬月額、勤続年数についてはあまり議論の余地がないため、「同業種・同規模の会社」をどう選定して功績倍率をいくらに決めるかが論点になってきます。
過去の判例を見ても、殆どが、平均功績倍率法等の一定の算式による退職金の適正額の算定を支持しています。一方、東京地裁の昭和46年6月29日の判決には、法人税法等の規定は「当該事案の特殊事情をすべて捨象して同業種・同規模の他の会社の給与の額を超える部分の損金算入をすべて否定しようとする趣旨に出たものではない」とあり、これは、会社の特殊事情があればそれを考慮して功績倍率を決める、または算式によらず退職金額を決めることの妥当性があることを示唆したものと思われます。
また、過去の判例を見てみると、平均功績倍率法による算定は以下の問題点、限界があると考えます。
1.最終報酬月額が所与(又は議論されていない)
平均功績倍率法を支持している判例は、最終報酬月額を所与としています(つまり、その報酬が過大かどうか深く議論されていません)。札幌地裁の平成11年12月12日の判決のように、報酬月額を退職事業年度に倍増させても、その倍増させた金額を前提に上記(注1)の算式を適用している例もあります。従って、これを逆手にとって、退職前に報酬を上げるという極端な方法も考える余地が生じます(もちろん、このブログは、そういう方法をお薦めするものではありませんが)。
2.同業種・同規模の会社の選定が難しい(個別事情が捨象されている)
筆者は、同業種・同規模の会社選定に当たって最も重要なのは、「在任期間中の純資産増加額(注2)」だと考えています。これが、最も役員(特に、代表者の場合の役員)の功績を表すものだと考えるからです。しかし、判例を見ると、純資産額の要素を考慮せずに、同業種・同規模の会社を選定しているものも散見されます。つまり、同業種・同規模の会社の選定自体にも更に深い議論が必要かと思います。
(注2)更に言うと、その増加額に対する退任役員の貢献度。たとえば、純資産増加額×(その役員報酬額/全人件費)で算出可能と考えます。
3.同業種・同規模の会社の「過去の実績」を基にしている。今後の実績は不問
当然、同業種・同規模として選定された会社の数値は、過去の実績です。退任する役員が今後も永続するようなビジネスモデルを作りそれがその後も有効である、等特別の場合は、その将来に亘っての貢献度を考慮する必要があると考えます。
上記より、平均功績倍率法による適正額の算定は、有効ではありますが、退任役員の功績が大きい(他社に比較して、純資産増加額が明らかに突出している等)の場合は、そういう事情を考慮して適正額を算定することも、十分に検討の価値があることだと思います。

↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。

↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。

(1)退職者の過去の勤労に対する対価の後払い(費用性、賃金後払説)、
(2)退職者の在職中の功労に対する報酬(利益配分性、功労報償説)、
(3)将来の生活保障について考慮されたもの(生活保障説) 等
の性格を有するものです。
そういう内容だからこそ、役員の受け取る退職金は、所得税法上は通常の給与等とは異なり受取人にとって有利な課税体系となっており、また、法人税法上も「不相当に高額」「でなければ」、会社の損金(税務上の費用)にすることができます。
その役員退職金の適正額の決定については、通常の場合は、
(1)役員退職金規定にその支給限度額を定め(その計算方法は、平均功績倍率法(注1)が一般的です)、
(2)その限度額の範囲内で支給することを機関決定して支給することにより、
法人税法上の「不相当に高額でない水準」としているようです。
(注1)最終報酬月額×勤続年数×功績倍率により適正額を計算する方法です。最終報酬月額、勤続年数についてはあまり議論の余地がないため、「同業種・同規模の会社」をどう選定して功績倍率をいくらに決めるかが論点になってきます。
過去の判例を見ても、殆どが、平均功績倍率法等の一定の算式による退職金の適正額の算定を支持しています。一方、東京地裁の昭和46年6月29日の判決には、法人税法等の規定は「当該事案の特殊事情をすべて捨象して同業種・同規模の他の会社の給与の額を超える部分の損金算入をすべて否定しようとする趣旨に出たものではない」とあり、これは、会社の特殊事情があればそれを考慮して功績倍率を決める、または算式によらず退職金額を決めることの妥当性があることを示唆したものと思われます。
また、過去の判例を見てみると、平均功績倍率法による算定は以下の問題点、限界があると考えます。
1.最終報酬月額が所与(又は議論されていない)
平均功績倍率法を支持している判例は、最終報酬月額を所与としています(つまり、その報酬が過大かどうか深く議論されていません)。札幌地裁の平成11年12月12日の判決のように、報酬月額を退職事業年度に倍増させても、その倍増させた金額を前提に上記(注1)の算式を適用している例もあります。従って、これを逆手にとって、退職前に報酬を上げるという極端な方法も考える余地が生じます(もちろん、このブログは、そういう方法をお薦めするものではありませんが)。
2.同業種・同規模の会社の選定が難しい(個別事情が捨象されている)
筆者は、同業種・同規模の会社選定に当たって最も重要なのは、「在任期間中の純資産増加額(注2)」だと考えています。これが、最も役員(特に、代表者の場合の役員)の功績を表すものだと考えるからです。しかし、判例を見ると、純資産額の要素を考慮せずに、同業種・同規模の会社を選定しているものも散見されます。つまり、同業種・同規模の会社の選定自体にも更に深い議論が必要かと思います。
(注2)更に言うと、その増加額に対する退任役員の貢献度。たとえば、純資産増加額×(その役員報酬額/全人件費)で算出可能と考えます。
3.同業種・同規模の会社の「過去の実績」を基にしている。今後の実績は不問
当然、同業種・同規模として選定された会社の数値は、過去の実績です。退任する役員が今後も永続するようなビジネスモデルを作りそれがその後も有効である、等特別の場合は、その将来に亘っての貢献度を考慮する必要があると考えます。
上記より、平均功績倍率法による適正額の算定は、有効ではありますが、退任役員の功績が大きい(他社に比較して、純資産増加額が明らかに突出している等)の場合は、そういう事情を考慮して適正額を算定することも、十分に検討の価値があることだと思います。
文責:事業承継部
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。
09年08月20日
支出金額(時) ≠ 経費(損金)について
数多い関与先の中に、今でも「支出額(時)」=「経費」と思われている社長様がいらっしゃいます。「発生主義」の観点から支出額=経費ではありません。
現在の日本では「発生主義」が原則とされています。「発生主義」とは、費用を現金支出の事実ではなく発生の事実に基づいて認識するものです。つまり、品物を購入した事実のみで「経費」となるのです。
例えば、「掛け」で品物を購入し、代金支払は翌月の取引があったとします。この場合、「購入した月」に「経費」となり、「翌(代金を支払った)月」に「現金支出」となるのです。売上に関しても同様です。
支出金額(時) ≠ 経費(損金)の最も解りやすい例が「固定(減価償却)資産の購入」です。
建物・機械装置・工具器具・備品・車輌等の購入は基本的に支払った時の経費とはなりません。法定耐用年数により何年かに分けて徐々に経費(減価償却費)となります。現金支出時(支出事業年度)の全額がその時の経費ではなく、支出がない時(支出事業年度以外)も経費となるということです。
お金の流れを表したものを「キャッシュフロー計算書」といい、「損益計算書」とは全く別のものとなります。この「キャッシュフロー計算書」は「現在の利益額」と「現在の現預金」との差額を知ることができます。現預金は少ないのに利益額は思いのほか多いという経験をした社長様は少なくないと思います。そんな場合は「キャッシュフロー計算書」を作成してみるとよいでしょう。
借入金の返済額も「経費」ではないのか?との声も聞いたことがありますが、残念ながら「経費」ではありません。勿論、借入時の入金額(借入額)も収入ではありません。

↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。

↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。

現在の日本では「発生主義」が原則とされています。「発生主義」とは、費用を現金支出の事実ではなく発生の事実に基づいて認識するものです。つまり、品物を購入した事実のみで「経費」となるのです。
例えば、「掛け」で品物を購入し、代金支払は翌月の取引があったとします。この場合、「購入した月」に「経費」となり、「翌(代金を支払った)月」に「現金支出」となるのです。売上に関しても同様です。
支出金額(時) ≠ 経費(損金)の最も解りやすい例が「固定(減価償却)資産の購入」です。
建物・機械装置・工具器具・備品・車輌等の購入は基本的に支払った時の経費とはなりません。法定耐用年数により何年かに分けて徐々に経費(減価償却費)となります。現金支出時(支出事業年度)の全額がその時の経費ではなく、支出がない時(支出事業年度以外)も経費となるということです。
お金の流れを表したものを「キャッシュフロー計算書」といい、「損益計算書」とは全く別のものとなります。この「キャッシュフロー計算書」は「現在の利益額」と「現在の現預金」との差額を知ることができます。現預金は少ないのに利益額は思いのほか多いという経験をした社長様は少なくないと思います。そんな場合は「キャッシュフロー計算書」を作成してみるとよいでしょう。
借入金の返済額も「経費」ではないのか?との声も聞いたことがありますが、残念ながら「経費」ではありません。勿論、借入時の入金額(借入額)も収入ではありません。
文責:北九州支店
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。
09年08月17日
第二会社方式による中小企業再生−改正産業活力再生特別措置法の施行−
事業再生支援を主眼とした「改正産業活力再生特別措置法」(以下、「改正産活法」。)が平成21年6月22日に施行されました。
同法では、1つの目玉として、「第二会社方式」により事業の存続を図るための各種の支援策が創設されました。
経営悪化に苦しむ中小企業は多いと思いますが、この法律の施行により事業再生が可能となる会社もかなりの数になるのではないかと思います。
以下、簡単にですが内容をご紹介したいと思います。
1.「第二会社方式」とは
収益性のある優良事業部門を別法人(第二会社)に分割等して事業の存続を図るとともに、負債・赤字を残した旧会社を清算等する再生手法の一つです。金融機関の協力が得やすい等の理由から、抜本的な再生を図る際に活用するケースが最近増えてきています。
過剰債務を抱え、かつ、収益性のある事業を有した会社であれば検討の余地は十分にあると思います。
2.「第二会社方式」に対する支援措置
(1)営業上必要な許認可の承継
今までの会社分割等では、旧会社の許認可の引継ぎが問題となるケースが多かったのですが、これを解消するための支援措置が設けられました。
(2)登録免許税・不動産取得税の負担の軽減措置
「第二会社方式」による事業譲渡・会社分割を行う場合、不動産等の移転が必要なときに発生する登録免許税及び不動産取得税が軽減されます。
(3)必要な事業資金に対する金融支援
・日本政策金融公庫による低利融資制度
・信用保証協会による債務保証
3.改正産活法の適用要件
一定の要件の下、「中小企業承継事業再生計画」を策定し、国の認定等を受けなければ上記2の支援措置の適用を受けることができません。

↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。

↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。

同法では、1つの目玉として、「第二会社方式」により事業の存続を図るための各種の支援策が創設されました。
経営悪化に苦しむ中小企業は多いと思いますが、この法律の施行により事業再生が可能となる会社もかなりの数になるのではないかと思います。
以下、簡単にですが内容をご紹介したいと思います。
1.「第二会社方式」とは
収益性のある優良事業部門を別法人(第二会社)に分割等して事業の存続を図るとともに、負債・赤字を残した旧会社を清算等する再生手法の一つです。金融機関の協力が得やすい等の理由から、抜本的な再生を図る際に活用するケースが最近増えてきています。
過剰債務を抱え、かつ、収益性のある事業を有した会社であれば検討の余地は十分にあると思います。
2.「第二会社方式」に対する支援措置
(1)営業上必要な許認可の承継
今までの会社分割等では、旧会社の許認可の引継ぎが問題となるケースが多かったのですが、これを解消するための支援措置が設けられました。
(2)登録免許税・不動産取得税の負担の軽減措置
「第二会社方式」による事業譲渡・会社分割を行う場合、不動産等の移転が必要なときに発生する登録免許税及び不動産取得税が軽減されます。
(3)必要な事業資金に対する金融支援
・日本政策金融公庫による低利融資制度
・信用保証協会による債務保証
3.改正産活法の適用要件
一定の要件の下、「中小企業承継事業再生計画」を策定し、国の認定等を受けなければ上記2の支援措置の適用を受けることができません。
文責:法人ソリューション1部
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。
09年08月10日
社長が幹部を育てる方法 4
会社経営を行っていく上で様々な課題は日々でてきます。ある一つの課題を解決するために4段階のステップがあるとします。最初の段階で、5つの選択肢が想定されています。次の段階では、その選択肢のひとつひとつに対して、さらに5つの選択肢が考えられています。つまりその課題の内容に入ろうとすると、第一段階で5となり、さらに25の選択肢が提示される。さらに3段階目で125となり、最終段階の4段階では何と625という膨大な選択肢にふくれ上がってしまいます。これらを一つ一つ検証することは事実上、無理です。にもかかわらず、幹部としての資質に欠ける人は「間違った選択をしたらどうしよう」という恐怖心から、最初の一歩を踏み出す事ができないのです。
こんな幹部が率いるチームの仕事は、遅々として進みません。
課題という大きな川があるとします。「まずは川に飛び込んでみるのです。」橋を探したり、船で渡ったり、筏を作ったりそのような事を考えているうちに時間は刻々と過ぎ、日が暮れてしまいます。そのような事をいちいち考える前にまずは思い切って飛び込んでみるのです。飛び込んでみると、意外と川が浅く、水も冷たくない。それならそのまま渡ってしまえばいい。思った以上に急流で、もし渡るのが困難なら、その時に考えればいいだけの事。
仕事も同様、最初の一歩も踏み出さず、ただ考えあぐねている人がどうして仕事の成果を上げる事ができるであろうか?考えあぐねている間に時間は刻々とすぎ、有能な幹部に次々に追い抜かれてしまいます。
「仕事にはスピード感と勢いが必要」だということなのです。計画段階であれこれと悩み時間を浪費するよりも、実行そのものに時間をかけるのが正解なのです。ただ、この仕事の進め方は様々な局面で多用されますが、万能ではありません。将来を左右するような課題が発生した時などは、当然綿密な準備を重ねて慎重に行う必要があります。
しかし、そのような事は頻繁に起こりうることではありません。基本的には実績や成果をあげていく上ではスピード重視の考え方は欠かせないのです。普段の仕事は60%をメドにスピード優先で行い、大事な案件は、完成度を100%に近づける事が必要です。
悩めば悩むほど時間を浪費してしまいますし、前に進む事はできません。まずは、動いてみる。確かに不安はあります。しかし、その一歩を踏み出さない事にはその課題をクリアすることはできません。また、自分自身を高めていくためには幾度の失敗を繰り返し、それを乗り越えてこそが自分自身の成長への繋がっていくのではないかと思います。
「スピード感と勢い」この思い切った行動こそが幹部の資質には必要なのです。そういった幹部には自ずと部下はついてくるものです。

↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。

↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。

こんな幹部が率いるチームの仕事は、遅々として進みません。
課題という大きな川があるとします。「まずは川に飛び込んでみるのです。」橋を探したり、船で渡ったり、筏を作ったりそのような事を考えているうちに時間は刻々と過ぎ、日が暮れてしまいます。そのような事をいちいち考える前にまずは思い切って飛び込んでみるのです。飛び込んでみると、意外と川が浅く、水も冷たくない。それならそのまま渡ってしまえばいい。思った以上に急流で、もし渡るのが困難なら、その時に考えればいいだけの事。
仕事も同様、最初の一歩も踏み出さず、ただ考えあぐねている人がどうして仕事の成果を上げる事ができるであろうか?考えあぐねている間に時間は刻々とすぎ、有能な幹部に次々に追い抜かれてしまいます。
「仕事にはスピード感と勢いが必要」だということなのです。計画段階であれこれと悩み時間を浪費するよりも、実行そのものに時間をかけるのが正解なのです。ただ、この仕事の進め方は様々な局面で多用されますが、万能ではありません。将来を左右するような課題が発生した時などは、当然綿密な準備を重ねて慎重に行う必要があります。
しかし、そのような事は頻繁に起こりうることではありません。基本的には実績や成果をあげていく上ではスピード重視の考え方は欠かせないのです。普段の仕事は60%をメドにスピード優先で行い、大事な案件は、完成度を100%に近づける事が必要です。
悩めば悩むほど時間を浪費してしまいますし、前に進む事はできません。まずは、動いてみる。確かに不安はあります。しかし、その一歩を踏み出さない事にはその課題をクリアすることはできません。また、自分自身を高めていくためには幾度の失敗を繰り返し、それを乗り越えてこそが自分自身の成長への繋がっていくのではないかと思います。
「スピード感と勢い」この思い切った行動こそが幹部の資質には必要なのです。そういった幹部には自ずと部下はついてくるものです。
文責:ワンストップソリューション部
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。
09年08月06日
地震保険は役に立たないか?その1
阪神淡路大震災から14年の歳月が過ぎ、あの痛ましい出来事の記憶がわずかに薄れ始めたさなかに、新潟県中越地震や福岡県西方沖地震など相次いで大型地震が発生し、当時、私どもも福岡県下では、被害報告を多数受けました。特に、平成17年3月20日午前10時53分に発生した、「福岡県西方沖地震」で、不幸にも罹災された被災者の方々には、心よりお見舞いを申し上げるとともに、一日も早く被災前の平穏な日常生活を取り戻せることを、お祈りして止みませんでした。
今回は、福岡県民の加入率が16%前半(「福岡県西方沖地震」発生前)と言われる地震保険について、お話しさせていただきたいと思います。
地震保険には、
A.一般住宅や居住部分のある店舗併用住宅の建物および家財が補償の対象となる「家計地震」(住まいの地震保険)と、
B.Aで担保されない営業用の建物、什器、機械、商品などについて、地震危険を火災保険の特約として補償の対象とする、「地震危険拡張担保特約」
の2種類があります。
実際に罹災された方のコメントが新聞紙上にも掲載されていましたが、特に「家計地震」では、実際に被った損害額に対して、支払われる(認定された)保険金額が「思いのほか少ない!」と、お感じになった方が、多かったようです。
ところで、そもそも家計地震の主な目的は、
1.法律(「地震保険に関する法律」)に基づいて、政府と民間の損保会社が共同で運営する制度
2.利潤を求めず、保険料は準備金として積立てられる
3.地震災害による被災者の生活の安定に寄与することを目的とする
ですので、あくまで被災者の方々への一時的なお見舞い費用としての概念が強く、実質損害をほぼ完全に填補する火災保険などの保険商品とは、イメージが大きく異なります。しかしながら、ジャーナリストの鳥越俊太郎氏のテレビCMでもご紹介されているとおり、地震による火災の被害は、火災保険では支払い対象にはなりませんし、地震による建物の倒壊なども地震保険を付帯していないと、全くカバーできません。
また、支払い認定基準も全壊、半壊、一部損壊と3種類で、損保会社が委託した鑑定人が実地調査を行い基準に沿って判定を行うわけですが、何故そのように判定されたのか?なども、一般のご契約者様には分かりづらく、理解しがたい要因の1つになっているのではないかと考えます。
地震保険の支払い基準や、仕組み、どのようなケースで実際に支払われるのか?など、可能な限り実例を交えて、ご契約前に十分な説明を行う「説明責任」を負っていることを、我々損害保険を取り扱う代理店のエージェントが、再度しっかりと自覚しなければなりませんし、保険契約を結ぶ際にはご契約者様の立場としても、なぜ?どうして?といった、素朴な疑問をどんどん投げかけていただくことは、こと地震保険に限らず、あらゆる保険契約に必要不可欠であると考えます。
次回は、一般物件、工場物件などの「地震危険拡張担保特約」についてお話したいと思います。

↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。

↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。

今回は、福岡県民の加入率が16%前半(「福岡県西方沖地震」発生前)と言われる地震保険について、お話しさせていただきたいと思います。
地震保険には、
A.一般住宅や居住部分のある店舗併用住宅の建物および家財が補償の対象となる「家計地震」(住まいの地震保険)と、
B.Aで担保されない営業用の建物、什器、機械、商品などについて、地震危険を火災保険の特約として補償の対象とする、「地震危険拡張担保特約」
の2種類があります。
実際に罹災された方のコメントが新聞紙上にも掲載されていましたが、特に「家計地震」では、実際に被った損害額に対して、支払われる(認定された)保険金額が「思いのほか少ない!」と、お感じになった方が、多かったようです。
ところで、そもそも家計地震の主な目的は、
1.法律(「地震保険に関する法律」)に基づいて、政府と民間の損保会社が共同で運営する制度
2.利潤を求めず、保険料は準備金として積立てられる
3.地震災害による被災者の生活の安定に寄与することを目的とする
ですので、あくまで被災者の方々への一時的なお見舞い費用としての概念が強く、実質損害をほぼ完全に填補する火災保険などの保険商品とは、イメージが大きく異なります。しかしながら、ジャーナリストの鳥越俊太郎氏のテレビCMでもご紹介されているとおり、地震による火災の被害は、火災保険では支払い対象にはなりませんし、地震による建物の倒壊なども地震保険を付帯していないと、全くカバーできません。
また、支払い認定基準も全壊、半壊、一部損壊と3種類で、損保会社が委託した鑑定人が実地調査を行い基準に沿って判定を行うわけですが、何故そのように判定されたのか?なども、一般のご契約者様には分かりづらく、理解しがたい要因の1つになっているのではないかと考えます。
地震保険の支払い基準や、仕組み、どのようなケースで実際に支払われるのか?など、可能な限り実例を交えて、ご契約前に十分な説明を行う「説明責任」を負っていることを、我々損害保険を取り扱う代理店のエージェントが、再度しっかりと自覚しなければなりませんし、保険契約を結ぶ際にはご契約者様の立場としても、なぜ?どうして?といった、素朴な疑問をどんどん投げかけていただくことは、こと地震保険に限らず、あらゆる保険契約に必要不可欠であると考えます。
次回は、一般物件、工場物件などの「地震危険拡張担保特約」についてお話したいと思います。
文責:株式会社プロネットインシュア
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。
09年08月03日
改正育児・介護休業法が成立
平成21年6月24日、改正育児・介護休業法が参院本会議において全会一致で可決、成立しました。今回の改正の目的は、子育てがしやすい環境づくり、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる環境を整備するためとされ、主な改正内容は以下の通りです。
1.子育て期間中の働き方の見直し
●3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度を設けることを義務化。
●所定外労働の免除を義務化(3歳までの子を養育する労働者からの請求による)。
●子の看護休暇制度を拡充する
(小学校就学前の子が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)。
※現行では、小学校就学前の子がいれば、人数に関わりなく年5日。
2.父親も子育てができる働き方の実現
●父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月までの間に、1年間育児休業を取得可能とする。
●父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。
●労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止をする。
3.仕事と介護の両立支援
●要介護状態にある家族の通院の付き添い等のため、介護休暇制度を創設する。
(要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)
4.その他
●育児休業の取得等に伴う苦情や紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停制度を創設する。
●勧告に従わない場合の公表制度や、報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者等に対する過料を創設する。
施行は公布から1年(一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主について3年)以内の政令で定める日からです。ただし、上記4のうち、調停については平成22年4月1日、その他は公布から3カ月以内の政令で定める日からです。
厚生労働省のHPでもご覧になれますので、ご参照ください。
企業側にとっては、上記1のような義務化により負担も大きくなり、社員が短時間勤務や残業免除の制度を利用する場合、他の社員の労働時間が増えたり、新たな社員の採用などの対応に迫られることにもなります。在宅勤務制度の導入などにより、出産・育児中の優秀な社員をつなぎとめておくことも選択肢の一つになるのではないでしょうか。

↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。

↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。

1.子育て期間中の働き方の見直し
●3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度を設けることを義務化。
●所定外労働の免除を義務化(3歳までの子を養育する労働者からの請求による)。
●子の看護休暇制度を拡充する
(小学校就学前の子が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)。
※現行では、小学校就学前の子がいれば、人数に関わりなく年5日。
2.父親も子育てができる働き方の実現
●父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月までの間に、1年間育児休業を取得可能とする。
●父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。
●労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止をする。
3.仕事と介護の両立支援
●要介護状態にある家族の通院の付き添い等のため、介護休暇制度を創設する。
(要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)
4.その他
●育児休業の取得等に伴う苦情や紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停制度を創設する。
●勧告に従わない場合の公表制度や、報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者等に対する過料を創設する。
施行は公布から1年(一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主について3年)以内の政令で定める日からです。ただし、上記4のうち、調停については平成22年4月1日、その他は公布から3カ月以内の政令で定める日からです。
厚生労働省のHPでもご覧になれますので、ご参照ください。
企業側にとっては、上記1のような義務化により負担も大きくなり、社員が短時間勤務や残業免除の制度を利用する場合、他の社員の労働時間が増えたり、新たな社員の採用などの対応に迫られることにもなります。在宅勤務制度の導入などにより、出産・育児中の優秀な社員をつなぎとめておくことも選択肢の一つになるのではないでしょうか。
文責:ヒューマニー事業部
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。