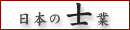09年09月10日
年齢と性別による生命保険料の差
ご存知のように生命保険の保険料は、中後年齢層に比べ若年層の方が安く、また、同年齢なら男性に比べ女性の方が一般的に安く設定されています。
これは、保険料を算出するときの要件のひとつである「死亡率」「罹患率」の違いによるものです。
通常、死亡率は平均余命(*1)が長い若年層が中高年層より低く、また平均寿命(*2)が長い女性の方が男性よりも低い為、死亡する可能性が低い若年層と、同年齢ならば女性の保険料が安くなる訳ですね。
これは、医療保険においても同じような考え方により、罹患率の違いから、やはり若年層および女性の方が安くなる訳です。
ただ、「がん保険」に限っては中高年層の定期型商品の場合、これが逆転し女性の方が高くなっていることがあります。
これは、乳がんや子宮がん等女性特有のがん罹患の危険が高いからですね。
女性のみなさん、定期的な健診等でくれぐれも気を付けましょうね。
(*1)平均余命:一定年齢者の、生存後に死亡するであろう年齢の平均値
(*2)平均寿命:0歳児の平均余命のこと

↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。

↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。

これは、保険料を算出するときの要件のひとつである「死亡率」「罹患率」の違いによるものです。
通常、死亡率は平均余命(*1)が長い若年層が中高年層より低く、また平均寿命(*2)が長い女性の方が男性よりも低い為、死亡する可能性が低い若年層と、同年齢ならば女性の保険料が安くなる訳ですね。
これは、医療保険においても同じような考え方により、罹患率の違いから、やはり若年層および女性の方が安くなる訳です。
ただ、「がん保険」に限っては中高年層の定期型商品の場合、これが逆転し女性の方が高くなっていることがあります。
これは、乳がんや子宮がん等女性特有のがん罹患の危険が高いからですね。
女性のみなさん、定期的な健診等でくれぐれも気を付けましょうね。
(*1)平均余命:一定年齢者の、生存後に死亡するであろう年齢の平均値
(*2)平均寿命:0歳児の平均余命のこと
文責:株式会社プロネットインシュア
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。
09年09月07日
在宅勤務制度
今回は、2009年8月3日のブログに掲載しました『在宅勤務制度』についてすすめていきます。
現在、企業経営や雇用環境などを取り巻く状況はますます厳しく、賃金等の労働条件の見直しや雇用調整など雇用対策を行っている、検討している企業も多くあると思われます。このような中で、その他の勤務形態として『在宅勤務制度』の導入を検討することも雇用対策へつながるのではないでしょうか。
在宅勤務は、『テレワーク』注の対象者を就業形態の違いにより分類しているもので、雇用型テレワーカーとして自宅を就業場所とする在宅勤務、いつでもどこでも仕事が可能なモバイル勤務などがあります。SOHOなどの独立自営している方などは自営型テレワーカーとして分けられます。
注 テレワーク:パソコンなどの通信情報技術を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことです。
企業がテレワークを導入する目的は、企業の状況、業種や職種などでさまざまで、効果も取り組み等で多少異なってきます。
≪テレワークの効果≫
・社員の業務生産性・効率性の向上
・顧客満足度の向上
・少子化・高齢化問題等への対応、ワーク・ライフ・バランスの充実
・社員の意識改革、企業風土の変革
・有能・多様な人材の確保
・事業継続性の確保、危機管理
・環境貢献
・コスト削減
しかし、テレワーク導入に際する懸念事項として、情報漏洩なども含め情報セキュリティの問題、時間管理はどうするか、評価できるのか、コミュニケーションはきちんととれるか、コスト面など課題も多く、導入・運用までの一歩を躊躇されます。
導入にあたっては、現在企業が抱える課題に応じて、導入の目的を定め、試行段階的な実施を行い、その段階で出てくる問題をひとつひとつクリアしながら本格導入を開始していくことが望ましいと考えます。
テレワーク、在宅勤務制度などについては、社団法人日本テレワーク協会の相談センターも設置されていますので、ご相談されてはいかがでしょうか。

↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。

↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。

現在、企業経営や雇用環境などを取り巻く状況はますます厳しく、賃金等の労働条件の見直しや雇用調整など雇用対策を行っている、検討している企業も多くあると思われます。このような中で、その他の勤務形態として『在宅勤務制度』の導入を検討することも雇用対策へつながるのではないでしょうか。
在宅勤務は、『テレワーク』注の対象者を就業形態の違いにより分類しているもので、雇用型テレワーカーとして自宅を就業場所とする在宅勤務、いつでもどこでも仕事が可能なモバイル勤務などがあります。SOHOなどの独立自営している方などは自営型テレワーカーとして分けられます。
注 テレワーク:パソコンなどの通信情報技術を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことです。
企業がテレワークを導入する目的は、企業の状況、業種や職種などでさまざまで、効果も取り組み等で多少異なってきます。
≪テレワークの効果≫
・社員の業務生産性・効率性の向上
・顧客満足度の向上
・少子化・高齢化問題等への対応、ワーク・ライフ・バランスの充実
・社員の意識改革、企業風土の変革
・有能・多様な人材の確保
・事業継続性の確保、危機管理
・環境貢献
・コスト削減
しかし、テレワーク導入に際する懸念事項として、情報漏洩なども含め情報セキュリティの問題、時間管理はどうするか、評価できるのか、コミュニケーションはきちんととれるか、コスト面など課題も多く、導入・運用までの一歩を躊躇されます。
導入にあたっては、現在企業が抱える課題に応じて、導入の目的を定め、試行段階的な実施を行い、その段階で出てくる問題をひとつひとつクリアしながら本格導入を開始していくことが望ましいと考えます。
テレワーク、在宅勤務制度などについては、社団法人日本テレワーク協会の相談センターも設置されていますので、ご相談されてはいかがでしょうか。
文責:ヒューマニー事業部
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。
09年09月04日
不況期の企業経営 -その7-
世間的には経済的な不況は落ち着きつつあると言われていますが、こと中小企業に関しては状況は殆ど変わっていないのが現状です。未曾有の不況に直面し、多くの企業が固定費であります、人件費の削減を求められ、非正規雇用者の人員削減に着手しています。更に、一部の企業では、給与の一律カットを行い、人員削減の対象を正規雇用者にまで広げようとしています。しかし、企業がまず着手すべきは、自社の人事制度の「甘い」部分を徹底的に点検し、厳しい経営環境に生き残るための体制を早急に築くことです。
どんな時代でもやはり「企業は人なり」です。
この大不況下で、どのような人事施策を取るかは企業の今後の浮沈のカギを握ります。
こんな時代だからこそ、人事制度を見直す絶好のチャンスです。
まずは、雇いいれる段階での募集や面接等から見直す必要があります。特化した形での募集や面接はできませんが、意識してやることは可能だと思います。本当に必要な人材を募るそして見極める。このスタート段階こそがとても重要になってきます。この不況期、雇用状況が厳しい為、働きたくても働けない人があふれています。そんな時だからこそよりより人材を確保するチャンスではないでしょうか。
次に雇いいれた後です。以前の中小企業では、「やらせて覚えさせる」といった言わば「何も言わずに育てる」といった教育方針の企業が多かったと思います。しかし、今は「OJT」といった指導方法が非常に重要視されています。「OJT」とは企業内で行われる職業指導手法のひとつで、職場の上司や先輩が部下や後輩に対し、具体的な仕事を通じて、仕事に必要な知識・技術・技能・態度などを、意図的・計画的・継続的に指導し、修得させることによって、全体的な業務処理能力や力量を育成するすべての活動です。
このOJTを導入することでのOJTの成果は、「実務の中で仕事を覚える」ことにより「OJTの成果が仕事の成果になる」など、研修の成果が業績に反映される。いわば「新入社員の成長」と「企業の業績向上」という、一石二鳥が期待できます。ただし、指導者となった先輩に指導力が伴わない場合、新入社員の能力向上どころか、その可能性の芽を摘んでしまう。そのため指導者への課題として、「どの分野は誰が詳しい」といった情報を新入社員に伝えるなど、職場内でのコミュニケーションの指導にも配慮が求められます。
以前のようにいい人材を確保してもすぐに辞めてしまう状況を無くし、長く企業に留まり戦力として育てることこそが他企業と差をつける一つの手段だと思います。今だからこそ、思い切って新しい手法を取り入れることこそ大きく変革するには必要なことではないでしょうか?

↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。

↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。

どんな時代でもやはり「企業は人なり」です。
この大不況下で、どのような人事施策を取るかは企業の今後の浮沈のカギを握ります。
こんな時代だからこそ、人事制度を見直す絶好のチャンスです。
まずは、雇いいれる段階での募集や面接等から見直す必要があります。特化した形での募集や面接はできませんが、意識してやることは可能だと思います。本当に必要な人材を募るそして見極める。このスタート段階こそがとても重要になってきます。この不況期、雇用状況が厳しい為、働きたくても働けない人があふれています。そんな時だからこそよりより人材を確保するチャンスではないでしょうか。
次に雇いいれた後です。以前の中小企業では、「やらせて覚えさせる」といった言わば「何も言わずに育てる」といった教育方針の企業が多かったと思います。しかし、今は「OJT」といった指導方法が非常に重要視されています。「OJT」とは企業内で行われる職業指導手法のひとつで、職場の上司や先輩が部下や後輩に対し、具体的な仕事を通じて、仕事に必要な知識・技術・技能・態度などを、意図的・計画的・継続的に指導し、修得させることによって、全体的な業務処理能力や力量を育成するすべての活動です。
このOJTを導入することでのOJTの成果は、「実務の中で仕事を覚える」ことにより「OJTの成果が仕事の成果になる」など、研修の成果が業績に反映される。いわば「新入社員の成長」と「企業の業績向上」という、一石二鳥が期待できます。ただし、指導者となった先輩に指導力が伴わない場合、新入社員の能力向上どころか、その可能性の芽を摘んでしまう。そのため指導者への課題として、「どの分野は誰が詳しい」といった情報を新入社員に伝えるなど、職場内でのコミュニケーションの指導にも配慮が求められます。
以前のようにいい人材を確保してもすぐに辞めてしまう状況を無くし、長く企業に留まり戦力として育てることこそが他企業と差をつける一つの手段だと思います。今だからこそ、思い切って新しい手法を取り入れることこそ大きく変革するには必要なことではないでしょうか?
文責:経理サポート部
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。
09年08月31日
住宅取得等資金贈与の500万円の非課税特例
贈与税といえば、『1年間に110万円までの贈与は非課税』ということは多くの方が知っていらっしゃることと思います。
この度、経済の回復のために住宅取得等資金贈与の500万円の非課税が創設されています。
1.平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に
2.20歳以上の方が
3.その方の父母や祖父母などの直系尊属から
4.自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築・取得・増改築に充てるための金銭を贈与により取得し
5.贈与を受けた年の翌年3月15日までにその金銭の全額を充てて一定の要件を満たす家屋の新築・取得・増改築を行い、
6.贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であることと見込まれる方が、
7.贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の期限内申告書を提出しなければなりません。
なお、親族の工務店に新築・増改築を依頼する場合や親族から家屋を取得する場合にはこの非課税制度の適用はありません。
また、直系尊属から金銭ではなく、住宅用家屋そのものを贈与された場合にもこの非課税制度の適用はありません。
祖父と父から500万円ずつ、計1,000万円贈与された場合には、あくまでももらった方1人につき500万円が限度であるため、1,000万すべてが非課税になるわけではありませんのでご注意ください。
この非課税制度は他の控除額との併用が可能です。非課税制度(500万円)適用後の残額には、暦年課税にあっては基礎控除額(110万円)、相続時精算課税にあっては特別控除額(2,500万円)及び特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る特別控除額(1,000万円)が適用できます。なお、相続時精算課税に係る特別控除額(2,500万円)及び特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る特別控除額(1,000万円)の適用は、原則として、父母からの贈与の場合に限られます。
一定の要件につきましては、詳しくは、お近くの税務署や専門家にお尋ねください。

↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。

↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。

この度、経済の回復のために住宅取得等資金贈与の500万円の非課税が創設されています。
1.平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に
2.20歳以上の方が
3.その方の父母や祖父母などの直系尊属から
4.自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築・取得・増改築に充てるための金銭を贈与により取得し
5.贈与を受けた年の翌年3月15日までにその金銭の全額を充てて一定の要件を満たす家屋の新築・取得・増改築を行い、
6.贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であることと見込まれる方が、
7.贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の期限内申告書を提出しなければなりません。
なお、親族の工務店に新築・増改築を依頼する場合や親族から家屋を取得する場合にはこの非課税制度の適用はありません。
また、直系尊属から金銭ではなく、住宅用家屋そのものを贈与された場合にもこの非課税制度の適用はありません。
祖父と父から500万円ずつ、計1,000万円贈与された場合には、あくまでももらった方1人につき500万円が限度であるため、1,000万すべてが非課税になるわけではありませんのでご注意ください。
この非課税制度は他の控除額との併用が可能です。非課税制度(500万円)適用後の残額には、暦年課税にあっては基礎控除額(110万円)、相続時精算課税にあっては特別控除額(2,500万円)及び特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る特別控除額(1,000万円)が適用できます。なお、相続時精算課税に係る特別控除額(2,500万円)及び特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る特別控除額(1,000万円)の適用は、原則として、父母からの贈与の場合に限られます。
一定の要件につきましては、詳しくは、お近くの税務署や専門家にお尋ねください。
文責:資産税部
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。
09年08月27日
〜短期前払費用の取扱いについて〜
今回は、短期前払費用の取扱いについて検討をくわえることとする。
まず、法人税法基本通達2-2-14(短期前払費用)を確認することとする。
(短期の前払費用)
2−2−14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2−2−14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2−8「七」により追加、昭61年直法2−12「二」により改正)
(注)例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。
次に、国税庁の質疑応答事例について確認する。
【照会要旨】
当事者間の契約により、年1回3月決算の法人が次のような支払を継続的に行うこととしているものについては、法人税基本通達2−2−14((短期の前払費用))を適用し、その支払額の全額をその支払った日の属する事業年度において損金の額に算入して差し支えありませんか。
事例1:期間40年の土地賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の地代月額1,000,000円を支払う。
事例2:期間20年の土地賃借に係る賃料について、毎年、地代年額(4月から翌年3月)241,620円を3月末に前払により支払う。
事例3:期間2年(延長可能)のオフィスビルフロアの賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の家賃月額611,417円を支払う。
事例4:期間4年のシステム装置のリース料について、12ケ月分(4月から翌年3月)379,425円を3月下旬に支払う。
事例5:期間10年の建物賃借に係る賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月)1,000,000円を2月に前払により支払う。
【回答要旨】
・ 事例1から事例4までについては、照会意見のとおりで差し支えありません。
・ 事例5については、法人税基本通達2−2−14の適用が認められません。
(理由)
(1) 本通達の趣旨について
本通達は、1年以内の短期前払費用について、収益との厳密な期間対応による繰延経理をすることなく、その支払時点で損金算入を認めるというものであり、企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるというものです。
(2) 照会に対する考え方について
事例1から事例4までについては、基本的には、これを認めることが相当と考えられますが、一方では、利益が出たから今期だけまとめて1年分支払うというような利益操作のための支出や収益との対応期間のズレを放置すると課税上の弊害が生ずると認められるものについては、これを排除していく必要があります。
このため、継続的な支払を前提条件とすることや収入との直接的な見合関係にある費用については本通達の適用対象外とするということは、従来と同様、当然に本通達の適用に当たって必要とされるのですが、これに加え、役務の受入れの開始前にその対価の支払が行われ、その支払時から1年を超える期間を対価支払の対象期間とするようなものは、何らかの歯止めを置いた上で本通達の適用を認めることが相当と考えられます。
【関係法令通達】
法人税基本通達2−2−14
注記
平成20年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるというものであるが、重要性についての裁決を国税不服審判所の裁決事例より抜粋した。
当該事業年度末に約束手形で支給された翌事業年度の年俸制に係る役員報酬及び従業員給与については、当該事業年度内に具体的な役務提供がされておらず、また、会計上重要性の乏しい費用とは認められないから、当該事業年度の損金の額に算入できないとした事例
▼ 裁決事例集 No.65 - 343頁
請求人は、臨時株主総会又は従業員との間の合意による役員報酬又は従業員給与の年俸額(以下「本件役員報酬等」という。)に係る損金算入につき、本件役員報酬等を12で除した月割額から社会保険料等を控除した金額を券面額とする12枚の約束手形を振り出し、当該各事業年度内に支払っているから、その債務は当該事業年度の終了の日までに確定しており、仮にそうでないとしても、本件役員報酬等は支払いの日から1年以内に役務提供を受ける短期前払費用であり、法人税法基本通達2−2−14の後段の取扱い(以下「本件取扱い」という。)が適用されるから、たとえそれがその翌事業年度の業務執行等の役務に対応するものであっても、それは当該事業年度の損金の額に算入される旨主張する。
しかしながら、本件役員報酬等については、その具体的な給付をなすべき原因である役員の職務執行又は従業員の役務提供が当該事業年度の終了の日までになされていないから、その債務が確定しているとは認められず、また、本件役員報酬等は、請求人の財務内容に占める割合などからして、重要性の乏しい費用とは認められないため、本件役員報酬等には本件取扱いの適用がなく、したがって、それを当該事業年度の損金の額に算入することはできない。
平成15年2月20日裁決
(平15.2.20裁決、裁決事例集No.65 343頁)
《裁決書(抄)》
1 事実
(1)事案の概要
本件は、写真製版業及び出版業を営む同族会社である審査請求人(以下「請求人」という。)が、翌事業年度に対応する役員報酬等を事業年度終了の日までに一括して支払ったことについて、当該役員報酬等をいつの事業年度の損金の額に算入すべきであるかが争われた事案である。
(2)審査請求に至る経緯
イ 請求人は、平成9年5月1日から平成10年4月30日まで、平成10年5月1日から平成11年4月30日まで及び平成11年5月1日から平成12年4月30日までの各事業年度(以下、順次「平成10年4月期」、「平成11年4月期」及び「平成12年4月期」といい、これらを併せて「本件各事業年度」という。)の法人税について、青色の確定申告書に別表1の「確定申告」欄のとおり記載して、いずれも法定申告期限までに申告した。
ロ 原処分庁は、これに対し、平成13年5月21日付で、別表1の「更正処分等」欄のとおりの各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)をした。
ハ 請求人は、原処分を不服として、平成13年7月17日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、同年10月15日付で、平成10年4月期及び平成11年4月期の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分に対する異議申立てをいずれも棄却し、平成12年4月期の更正処分に対する異議申立てを却下する異議決定をした。
ニ 請求人は、異議決定を経た後の原処分に不服があるとして、平成13年11月14日に審査請求をした。
(3)関係法令等
イ 法人税法(平成12年法律第97号による改正前のもの。以下同じ。)第22条《各事業年度の所得の金額の計算》
法人税法第22条第3項第2号は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額として、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(以下「費用等」という。)の額を掲げるとともに、その費用等の範囲について、償却費以外の費用の場合には、当該事業年度終了の日までに債務の確定しているものとする旨規定している。
ロ 法人税基本通達2−2−12《債務の確定の判定》(以下「本件債務通達」という。)
本件債務通達は、上記イの「当該事業年度終了の日までに債務の確定しているもの」とは、別に定めるものを除き、当該事業年度終了の日までに、〔1〕当該費用に係る債務が成立していること(以下「債務成立要件」という。)、〔2〕当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること(以下「給付原因発生要件」という。)及び〔3〕その金額を合理的に算定することができるものであること(以下「合理的算定要件」といい、債務成立要件及び給付原因発生要件と併せて「確定債務3要件」という。)の3つの要件をすべて満たしている場合をいう旨定めている。
ハ 法人税基本通達2−2−14《短期の前払費用》(以下「本件前払通達」という。)
本件前払通達は、その前段において、前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていないものをいう。以下同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないとの原則を定めるとともに、その後段において、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める旨の取扱い(以下「後段の取扱い」という。)を定めている。
(4)基礎事実
以下の事実は、請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所が調査したところによっても、その事実が認められる。
イ 役員報酬
(イ)請求人の平成9年4月25日付の臨時株主総会議事録には、役員報酬について、要旨次のとおり決議された旨の記載がある。
A 取締役の平成9年4月26日から平成10年4月25日までの年俸額(以下「9年4月役員報酬」という。)は、Gが18,000,000円、Hが7,750,800円。
B 当該取締役が、上記Aの期間中に辞任するか解任された場合は、原則として、年俸額を日数按分する。
(ロ)請求人の平成10年4月24日付の臨時株主総会議事録には、役員報酬について、要旨次のとおり決議された旨の記載がある。
A 取締役の平成10年4月26日から平成11年4月25日までの年俸額(以下「10年4月役員報酬」という。)は、Gが18,000,000円、Hが7,750,800円。
B 当該取締役が、上記Aの期間中に辞任するか解任された場合は、原則として、年俸額を日数按分する。
(ハ)請求人の平成11年4月23日付の臨時株主総会議事録には、役員報酬について、要旨次のとおり決議された旨の記載がある。
A 取締役の平成11年4月26日から平成12年4月25日までの年俸額(以下「11年4月役員報酬」という。)は、Gが18,000,000円、Hが8,110,800円。
B 当該取締役が、上記Aの期間中に辞任するか解任された場合は、原則として、年俸額を日数按分する。
(ニ)請求人の平成12年4月25日付の臨時株主総会議事録には、役員報酬について、要旨次のとおり決議された旨の記載がある。
A 取締役の平成12年4月26日から平成13年4月25日までの年俸額(以下「12年4月役員報酬」といい、「10年4月役員報酬」及び「11年4月役員報酬」と併せて「本件各役員報酬」という。)は、Gが18,000,000円、Hが8,110,800円。
B 当該取締役が、上記Aの期間中に辞任するか解任された場合は、原則として、年俸額を日数按分する。
(ホ)請求人は、9年4月役員報酬の合計金額25,750,800円、10年4月役員報酬の合計金額25,750,800円、11年4月役員報酬の合計金額26,110,800円及び12年4月役員報酬の合計金額26,110,800円を、それぞれ平成8年5月1日から平成9年4月30日までの事業年度(以下「平成9年4月期」という。)、平成10年4月期、平成11年4月期及び平成12年4月期の損金の額に算入した。
(ヘ)請求人は、上記(ホ)の各金額を、それぞれ平成9年4月25日、平成10年4月25日、平成11年4月25日及び平成12年4月25日に、社会保険料等として控除する金額を差し引いた残額の12分の1を額面金額とする12枚の約束手形を振り出して支給した。
なお、約束手形の決済期日は、各年5月25日以降の各月の25日である。
ロ 従業員給与
(イ)年俸制に関する合意書
請求人が、従業員(以下「本件従業員」という。)との間で締結した平成10年4月24日付、平成11年4月26日付及び平成12年4月25日付の年俸制に関する各合意書(以下「本件各合意書」という。)には、要旨別表2及び次のAないしCのとおりの内容が記載されている(以下、本件各合意書の各日付に従い、本件各合意書記載の年俸を順次「10年4月給料」、「11年4月給料」及び「12年4月給料」といい、これらを併せて「本件各給料」という。)。
A 本件従業員は、請求人に対して、年俸対象期間中において、その労務を誠実に提供しなければならない。ただし、年俸対象期間中に本件従業員が退職する場合は、本件従業員は、退職後は労務を提供しないことになるので、退職月後に決済される予定の月割額を受給する権利はない(本件各合意書の第4条)。
B 請求人は、本件従業員に対し、年俸金額を12で除した額を毎月28日に支払う(本件各合意書の第3条第1項)。
C 請求人は、本件従業員に対して、年俸金額の月割額から控除すべき金額を差し引いた残額を額面金額とする約束手形で支払う(本件各合意書の第3条第2項)。
(ロ)請求人は、10年4月給料の合計金額14,983,200円、11年4月給料の合計金額21,392,400円及び12年4月給料の合計金額18,177,600円を、それぞれ平成10年4月期、平成11年4月期及び平成12年4月期の損金の額に算入した。
(ハ)請求人は、本件各合意書の内容(上記(イ)のB及びC)に応じた約束手形を振り出した。
(ニ)承諾書
本件従業員が請求人に対して提出した平成10年4月24日付、平成11年4月26日付及び平成12年4月25日付の各承諾書(以下「本件各承諾書」という。)には、別表3の内容を承諾する旨の記載がある(以下、本件各承諾書の各日付に従い、本件各承諾書記載の賞与を順次「10年4月賞与」、「11年4月賞与」及び「12年4月賞与」といい、これらを併せて「本件各賞与」という。)。
(ホ)請求人は、10年4月賞与の合計金額1,205,000円、11年4月賞与の合計金額4,540,000円及び12年4月賞与の合計金額4,140,000円を、それぞれ平成10年4月期、平成11年4月期及び平成12年4月期の損金の額に算入した。
なお、請求人は、平成9年4月期において、平成10年4月期に対応する給料及び賞与を損金の額に算入していない。
2 主張
(1)原処分庁の主張
イ 平成12年4月期に係る更正処分
平成12年4月期に係る更正処分は、当該事業年度の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものではないから、当該更正処分に対する審査請求は不適法である。
よって、当該審査請求を却下するとの裁決を求める。
ロ 原処分のうち上記イ以外の各処分
原処分のうち上記イ以外の各処分は、次の理由により適法であるから、当該各処分に係る審査請求をいずれも棄却するとの裁決を求める。
(イ)平成10年4月期及び平成11年4月期に係る各更正処分
本件各役員報酬、本件各給料及び本件各賞与(以下、これらを併せて「本件各役員報酬等」という。)は、以下の理由により、その支払った日の属する事業年度(以下「支払事業年度」という。)の損金の額に算入すべきではなく、その翌事業年度の損金の額に算入すべきである。
A 債務の確定
費用等が法人税法第22条第3項第2号の債務の確定したものとして損金の額に算入すべき金額となるためには、本件債務通達の定める確定債務3要件を満たす必要がある。
また、役員報酬は、役員が株主からの委任を受けて業務を執行したことの対価として支払われるものであり、また、従業員給料及び賞与は、法人と使用人の雇用契約に基づいて提供した労務の対価として支払われるものであるから、役員報酬、従業員給料及び賞与(以下「役員報酬等」という。)は、時の経過に応じて自動的に費用化される性質のものではなく、役員及び従業員が、業務の執行や労務の提供(以下「労務の提供等」という。)をして、その職務等を全うすることによって初めて、役員及び従業員は役員報酬等を法人に請求することができ、法人においては、その時に支払債務が確定することになる。
そうすると、本件各役員報酬等は、その支払事業年度の翌事業年度に対応する費用であり、各支払事業年度終了の日までに、労務の提供等がされていないから、本件債務通達の給付原因発生要件を満たしているとはいえず、請求人の支払債務は確定していないことになる。
したがって、本件各役員報酬等は、各支払事業年度の損金の額に算入すべき金額とはならない。
B 本件前払通達の後段の適用
請求人は、仮に本件各役員報酬等が各支払事業年度の翌事業年度に対応する費用であるとしても、本件前払通達が定める後段の取扱いの要件を充足しているから、本件各役員報酬等を各支払事業年度の損金の額に算入することができる旨主張する。
しかしながら、本件前払通達の後段の取扱いは、前段で定められた前払費用に係る費用収益対応の原則の例外であり、この例外を認める根拠は、「重要性の原則」(企業の会計処理の基準となる原則の1つで、重要性の乏しいものについては本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることを認める旨の原則をいう。以下同じ。)に基づく会計処理を、税務においても認めたものであると解されている。
これを本件についてみると、本件各役員報酬等は、課税所得の計算上重要性が乏しいとは到底いえないから、本件前払通達の後段の取扱いの適用を受けることはできない。
したがって、請求人の主張には理由がない。
(ロ)本件各賦課決定処分
上記(イ)のとおり、平成10年4月期及び平成11年4月期に係る各更正処分は適法であり、また、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、平成10年4月期については同条第1項及び第2項の、平成11年4月期については同条第1項の規定に基づいて行った本件各賦課決定処分は、いずれも適法である。
(2)請求人の主張
原処分は、次の理由により違法であるから、その全部の取消しを求める。
イ 本件各更正処分
本件各役員報酬等は、以下の理由により、その支払事業年度の損金の額に算入すべきである。
(イ)債務の確定
A 法人税法第22条第3項の解釈及び適用
法人税法第22条第3項は、債務の確定という法人税法特有の概念を用いて、企業会計上当該事業年度の費用とされるものであっても、債務の確定がないものについては、法人税法に特段の定めがあるものを除き、法人税法上、損金として取り扱われないことを定めている。
このように、法人税法が、損金の額に算入すべき金額について、債務の確定なる概念を特に要求しているのは、費用を、単に会計的事実によってではなく、何らかの法的な債権債務関係によってとらえようとする立場を採っているからであり、法人が計上した費用が企業会計上は期間に対応していないとしても、必ずしも法人税法上の損金にならないわけではない。
B 本件における「債務の確定」
(A)原処分庁は、役員報酬等が、時の経過に応じて自動的に費用化される性質のものではなく、役員及び従業員が、労務の提供等をして、その職務を全うすることによって初めて、請求することができ、法人の支払義務もその時に確定するものである旨主張する。
(B)確かに、会社と役員及び従業員との間に法律の規定と異なる特段の取決めがない場合には、原処分庁が主張するように取り扱うべきである。
しかしながら、本件については、臨時株主総会議事録、本件各合意書及び本件各承諾書における特段の取決め(以下「本件取決め」という。)があることによって、本件各役員報酬等の支払対象である役員(以下「本件役員」という。)及び本件従業員は、その職務等を全うする前に、上記の特段の取決めを根拠に、本件各役員報酬等の支払を求めることができ、また、請求人は、当該求めに応じて支払う義務を負い、請求人は、実際に当該支払義務に基づいて、本件役員及び本件従業員に対して手形を振り出しているのである。
したがって、請求人の債務は確定したものであるといえる。
C これに対して、原処分庁は、本件各役員報酬等に係る債務について、当該事業年度終了の日までに本件債務通達の給付原因発生要件を満たしているとはいえず、請求人の支払債務は確定していないと主張する。
しかしながら、上記Bの(B)のとおり、本件各役員報酬等は、本件取決めによって、各支払事業年度終了の日までにその債務が確定し、本件債務通達を充足しているにもかかわらず、翌事業年度に対応する費用であるという理由だけでその事実を否定するのは、私的自治という私法取引の大原則を無視した重大な誤りであり、違法なものである。
D 以上のとおりであり、本件各役員報酬等は、それが翌事業年度に対応する費用かどうかに関係なく、各支払事業年度において、本件取決めによる支払義務があるから、上記のとおり法人税法に内在する「法的な債権債務関係」に基づき、各支払事業年度の損金とすべきである。
(ロ)本件前払通達の後段の適用
仮に、本件各役員報酬等が支払事業年度の翌事業年度に対応する費用であるとしても、本件各役員報酬等は、本件前払通達の後段の取扱いが定める費用等に該当するから、各支払事業年度の損金の額に算入すべきである。
A 本件前払通達の後段は、期間対応していない費用であっても、〔1〕支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係る前払費用であること、〔2〕支払った額に相当する金額を継続してその支払事業年度の損金の額に算入していること、この2つの要件を満たすものについては、支払事業年度の損金の額に算入することを認める旨定めているところ、原処分庁は、当該後段の取扱いについては、重要性の原則から逸脱しない限度でその適用が認められるものである旨主張する。
B しかし、本件前払通達の後段の取扱いには、「重要性の乏しいものを対象にする。」あるいは「重要性の高いものは除外する。」などという文言はないのに、課税当局が、恣意的に「重要性の有無」という尺度で適用対象を判断することになると、納税者の税額確定における予測可能性が担保されないことになる。
このような公権力による恣意的な課税は、日本国憲法の要請する租税法律主義に反することとなり、違憲である。
C また、仮に、本件前払通達の後段の取扱いが重要性の原則に基づくものであるとしても、次のとおり、本件各役員報酬等について適用がないとする理由が不明確である。
(A)原処分庁は、請求人が、支払事業年度の翌事業年度に係る前払家賃を、その支払った日の属する各事業年度の損金の額に算入しているにもかかわらず、本件各更正処分の対象とはしていない。
(B)また、原処分庁は、本件各役員報酬等について、役務提供の内容が翌事業年度に対応するものであるからという理由で、その各支払事業年度の損金の額への算入を認めない。
(C)原処分庁が、このように矛盾した取扱いをし、その主張する「重要性の原則」についての具体的な適用基準を明確にしないまま、本件前払通達の後段の取扱いを適用するか否かの判断をしていることは、原処分庁が通達を単なる課税の道具としかとらえていないことを示しており、租税法規の補完である通達の性格に反し、租税法律主義にも違反しているから、違法である。
(ハ)以上のとおり、本件各更正処分は、法人税法第22条第3項及び本件前払通達の解釈から不適法であり、取り消すべきである。
ロ 本件各賦課決定処分
上記イのとおり、本件各更正処分は違法であるから、本件各賦課決定処分は、いずれもその全部を取り消すべきである。
3 判断
(1)平成12年4月期に係る更正処分
平成12年4月期については、別表1のとおり、原処分庁が行った上記の更正処分によっても、請求人が納付すべき税額が増加しないことから、当該更正処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益が認められない。
したがって、当該更正処分に対する審査請求は、不適法であり、却下するのが相当である。
(2)平成10年4月期及び平成11年4月期に係る更正処分
イ 債務の確定
(イ)法人税法第22条第3項第2号は、上記1の(3)のイのとおり、内国法人の各事業年度の損金の額に算入すべき金額について、費用等の額で、かつ、償却費以外の費用の場合には当該事業年度終了の日までに債務の確定しているものとする旨規定している。
そして、この「債務の確定しているもの」に係る判定については、本件債務通達が、上記1の(3)のロのとおり、別に定めるものを除き、当該事業年度終了の日までに確定債務3要件のすべてに該当することをもって、「債務の確定しているもの」と判定する旨定めているところ、当審判所においても、課税の公平を図り、所得計算は可能な限り客観的に覚知し得る事実関係に基づいて行われるべきであるという観点から、本件債務通達の取扱いを相当と認める。
そうすると、費用等を損金の額に算入するためには、当該費用等を損金の額に算入しようとする事業年度終了の日までに、単に債務が成立しているということだけでは足りず、確定債務3要件のうちの他の2要件である給付原因発生要件及び合理的算定要件をも充足することにより、債務が確定することが必要である。
(ロ)本件における債務の確定
A 請求人は、本件各役員報酬等について、法人とその役員及び従業員との間に法律の規定と異なる特段の取決めがない場合には、原処分庁が主張するように取り扱うべきであるが、本件取決めによって、各支払事業年度終了の日までにその債務が確定しているのであるから、当該各支払事業年度の損金に算入すべきである旨主張する。
B 確かに、請求人が主張するように、本件取決めによって、請求人と本件役員及び本件従業員との間において、請求人がいう法的な債務が成立し、本件各役員報酬等が具体的に支払われていることが認められる。
しかしながら、本件各役員報酬等が、法人税法上いずれの事業年度の損金の額に算入されるべきかを判断するに当たっては、本件取決めの有無、内容及び法的性格等を考慮しつつも、あくまでも上記1の(3)のイないしハの法人税に関する法令等の規定に従って、上記(イ)のとおり、法人税法が要件としている債務が確定しているかどうかを検討すべきである。
C そうすると、請求人が本件各役員報酬等をその支払事業年度である本件各事業年度の損金の額に算入するためには、本件各事業年度終了の日までに確定債務3要件すべてを充足しなければならないところ、上記1の(4)のとおり、本件取決めによっても、辞任や退職等によって労務の提供等がされない場合には、役員報酬等の支払義務が生じないことと定められていることからしても、後記Dの金額を除いた本件各役員報酬等は、それぞれ本件各事業年度の翌事業年度において役務の提供等を受けることを具体的な給付をすべき原因として支出されたものであるから、給付原因発生要件を充足しているとは認められない。
したがって、請求人が平成10年4月期及び平成11年4月期の損金の額に算入した本件各役員報酬等の金額は、後記Dの金額を除いて、それぞれ平成10年4月期及び平成11年4月期の各事業年度終了の日までに、当該事業年度の損金の額に算入すべき債務が確定しているものとは認められないので、具体的に役務の提供等を受けた事業年度の損金の額に算入すべきである。
D 他方、10年4月役員報酬及び11年4月役員報酬のうち別表4の1及び2の各「〔2〕」欄に記載された金額は、上記1の(4)のとおり、平成10年4月期及び平成11年4月期に対応する費用等の金額であり、確定債務3要件を充足していると認められることから、それぞれの金額を各事業年度の損金の額に算入することが相当である。
ロ 本件前払通達
(イ)本件前払通達の後段の取扱い
A 前払費用は、企業会計上、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合において、いまだ提供されていない役務に対して支払われる対価で、時間の経過とともに次期以降の費用となるものをいう。また、前払費用のうち、重要性の乏しいものについては、重要性の原則から、これを経過勘定項目として処理しないことができるとされ、その代表的なものは、未経過保険料、未経過利息、前払賃借料等で、時の経過に応じて自動的、合理的に費用化されるものである。
B そして、前払費用は、本来、その支出事業年度の損金に算入されないのが原則であるが、本件前払通達は、上記Aのような企業会計の趣旨から、法人税法第22条第4項に規定する一般に公正妥当と認められる会計処理の基準といえる重要性の原則に沿う限りにおいて、後段の取扱いを例外として適用する旨定めているものと解される。
C そうすると、本件前払通達の後段の取扱いは、重要性の原則の範囲内においてその適用が認められるべきものであり、同原則の範囲内か否かの判断に当たっては、前払費用の金額だけではなく、当該法人の財務内容に占める割合や影響等も含めて総合的に考慮する必要があると考えるべきである。
D これに対して、請求人は、〔1〕本件前払通達の後段の取扱いには「重要性の乏しいものを対象にする。」などの文言はなく、「重要性の有無」で適用対象を判断すると納税者の予測可能性が担保されなくなること、〔2〕本件前払通達の後段の取扱いを具体的な適用基準を明確にしないまま適用するのは、租税法規の補完という通達の性格に反することを理由として、租税法律主義に反する旨主張する。
しかしながら、このような重要性の原則は、企業会計上の明確な原則であり、その適用範囲も合理的に判断できるものであるから、本件前払通達の後段の取扱いが重要性の原則に基づくことやその判断基準が本件前払通達に明示されていないからといって、租税法律主義に反するとはいえない。
(ロ)本件各役員報酬等に対する本件前払通達の後段の取扱いの適用
上記(イ)のCの基準に照らして、本件前払通達の後段の取扱いが、本件各役員報酬等に適用されるか否かについて、以下検討する。
A 請求人は、本件各役員報酬等が、本件前払通達の後段の取扱いの各要件に該当するので、後段の取扱いが適用され、本件各事業年度の損金の額へ算入すべきである旨主張する。
B しかしながら、本件各役員報酬は請求人の業務を執行したことに対する対価として、本件各給料及び本件各賞与は請求人の指揮命令の下に労務を提供したことに対する対価として、それぞれ支払われるものであって、このような人件費は、企業が営利活動を行う上で必要なものであり、企業活動の根幹に係る行為に対する対価であることからすると、会計科目としての重要性を有するといえる。
また、請求人の本件各事業年度の申告所得金額に対する人件費(請求人が決算書に記載している「給与」金額をいい、以下同じ。)の割合は、おおむね314.3ないし853.2%、売上金額に対する人件費の割合は、おおむね52.5ないし56.3%で、本件各事業年度に係る人件費のうちに本件各役員報酬等の金額が占める割合も、おおむね31.0ないし40.7%と、高率かつ可変的であり、金額的にみても重要性を有するといえる。
そうすると、本件各役員報酬等は、時の経過に応じて自動的、合理的に費用化されるような重要性の乏しい費用とは本質的にその性質を異にするものであると認められ、本件各役員報酬等に対して、本件前払通達の後段の取扱いを適用することはできないと解するのが相当である。
したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。
ハ 以上のことから、請求人が平成10年4月期及び平成11年4月期の損金の額に算入した本件各役員報酬等の金額は、上記イの(ロ)のDの金額を除き、いずれも当該事業年度の損金の額に算入されない費用等として取り扱うのが相当である。
なお、9年4月役員報酬の合計金額のうち、別表4の3の「〔3〕」欄に記載された金額は、平成10年4月期に対応する費用等の金額であるから、同事業年度の損金の額に算入すべき費用等として取り扱うのが相当である。
(3)平成10年4月期及び平成11年4月期の所得金額及び税額
イ 平成10年4月期
(イ)請求人の平成10年4月期の所得金額は、別表5の1のとおり、更正処分前の請求人の平成10年4月期の所得金額である別表1の「確定申告」欄の○○○○円に、平成11年4月期に対応する費用等の金額に当たる〔1〕10年4月役員報酬の合計金額のうち別表4の1の「〔3〕」欄の金額25,398,050円、〔2〕10年4月給料の合計金額14,983,200円及び〔3〕10年4月賞与の合計金額1,205,000円を加算し、平成10年4月期に対応する費用等の金額に当たる、9年4月役員報酬の合計金額のうち別表4の3の「〔3〕」欄の金額25,398,050円を減算した、○○○○円となる。
(ロ)そして、上記(イ)の所得金額に対する請求人の納付すべき法人税額(差引合計税額)は、11,583,000円となる。
なお、原処分庁は、法人税法第67条《同族会社の特別税率》の適用に当たり、平成10年4月期に留保した金額から9年4月役員報酬の合計金額を減算していないが、9年4月役員報酬の合計金額のうち平成10年4月期の損金の額に算入される金額25,398,050円は、平成10年4月期の留保金額を算定する上で、同期に留保した金額から控除されるべきである。
(ハ)そうすると、請求人の納付すべき法人税額は、平成10年4月期に係る更正処分の額を下回るから、平成10年4月期に係る更正処分は、その一部を取り消すべきである。
ロ 平成11年4月期
(イ)請求人の平成11年4月期の所得金額は、別表5の2のとおり、更正処分前の請求人の平成11年4月期の所得金額である別表1の「確定申告」欄の○○○○円に、平成12年4月期に対応する費用等の金額に当たる〔1〕11年4月役員報酬の合計金額のうち別表4の2の「〔3〕」欄の金額25,754,096円、〔2〕11年4月給料の合計金額21,392,400円及び〔3〕11年4月賞与の合計金額4,540,000円を加算し、平成11年4月期に対応する費用等の金額に当たる〔4〕10年4月役員報酬の合計金額のうち別表4の1の「〔3〕」欄の金額25,398,050円、〔5〕10年4月給料の合計金額14,983,200円、〔6〕10年4月賞与の合計金額1,205,000円及び〔7〕上記イで認定した所得に基づいて、新たに平成10年4月期の損金の額に算入される事業税の金額1,942,600円を減算した、○○○○円となる。
(ロ)そして、上記(イ)の所得金額に対する請求人の納付すべき法人税額(差引合計税額)は、8,478,300円となる。
(ハ)そうすると、請求人の納付すべき法人税額は平成11年4月期に係る更正処分の額を下回るから、平成11年4月期に係る更正処分はその一部を取り消すべきである。
ハ 本件各賦課決定処分
平成10年4月期及び平成11年4月期に係る更正処分は、上記イの(ハ)及びロの(ハ)のとおり、いずれもその一部を取り消すべきであり、過少申告加算税の賦課決定処分の基礎となる税額は、平成10年4月期が6,400,000円、平成11年4月期が2,940,000円となる。
また、この税額の計算の基礎となった事実については、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。
したがって、請求人の過少申告加算税の額は、平成10年4月期が701,000円、平成11年4月期が294,000円となる。
そうすると、平成10年4月期については、賦課決定処分の額を下回ることから、平成10年4月期の過少申告加算税の賦課決定処分は、その一部を取り消すべきである。
他方、平成11年4月期については、賦課決定処分の額と同額であるから、平成11年4月期の過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。
(4)その他
原処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。
上記、裁決事例より、重要性についての見解を窺うことができるものである。

↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。

↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。

ページ移動
前へ
1,2, ... ,47,48,49, ... ,90,91
次へ
Page 48 of 91
まず、法人税法基本通達2-2-14(短期前払費用)を確認することとする。
(短期の前払費用)
2−2−14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2−2−14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2−8「七」により追加、昭61年直法2−12「二」により改正)
(注)例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。
次に、国税庁の質疑応答事例について確認する。
【照会要旨】
当事者間の契約により、年1回3月決算の法人が次のような支払を継続的に行うこととしているものについては、法人税基本通達2−2−14((短期の前払費用))を適用し、その支払額の全額をその支払った日の属する事業年度において損金の額に算入して差し支えありませんか。
事例1:期間40年の土地賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の地代月額1,000,000円を支払う。
事例2:期間20年の土地賃借に係る賃料について、毎年、地代年額(4月から翌年3月)241,620円を3月末に前払により支払う。
事例3:期間2年(延長可能)のオフィスビルフロアの賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の家賃月額611,417円を支払う。
事例4:期間4年のシステム装置のリース料について、12ケ月分(4月から翌年3月)379,425円を3月下旬に支払う。
事例5:期間10年の建物賃借に係る賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月)1,000,000円を2月に前払により支払う。
【回答要旨】
・ 事例1から事例4までについては、照会意見のとおりで差し支えありません。
・ 事例5については、法人税基本通達2−2−14の適用が認められません。
(理由)
(1) 本通達の趣旨について
本通達は、1年以内の短期前払費用について、収益との厳密な期間対応による繰延経理をすることなく、その支払時点で損金算入を認めるというものであり、企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるというものです。
(2) 照会に対する考え方について
事例1から事例4までについては、基本的には、これを認めることが相当と考えられますが、一方では、利益が出たから今期だけまとめて1年分支払うというような利益操作のための支出や収益との対応期間のズレを放置すると課税上の弊害が生ずると認められるものについては、これを排除していく必要があります。
このため、継続的な支払を前提条件とすることや収入との直接的な見合関係にある費用については本通達の適用対象外とするということは、従来と同様、当然に本通達の適用に当たって必要とされるのですが、これに加え、役務の受入れの開始前にその対価の支払が行われ、その支払時から1年を超える期間を対価支払の対象期間とするようなものは、何らかの歯止めを置いた上で本通達の適用を認めることが相当と考えられます。
【関係法令通達】
法人税基本通達2−2−14
注記
平成20年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるというものであるが、重要性についての裁決を国税不服審判所の裁決事例より抜粋した。
当該事業年度末に約束手形で支給された翌事業年度の年俸制に係る役員報酬及び従業員給与については、当該事業年度内に具体的な役務提供がされておらず、また、会計上重要性の乏しい費用とは認められないから、当該事業年度の損金の額に算入できないとした事例
▼ 裁決事例集 No.65 - 343頁
請求人は、臨時株主総会又は従業員との間の合意による役員報酬又は従業員給与の年俸額(以下「本件役員報酬等」という。)に係る損金算入につき、本件役員報酬等を12で除した月割額から社会保険料等を控除した金額を券面額とする12枚の約束手形を振り出し、当該各事業年度内に支払っているから、その債務は当該事業年度の終了の日までに確定しており、仮にそうでないとしても、本件役員報酬等は支払いの日から1年以内に役務提供を受ける短期前払費用であり、法人税法基本通達2−2−14の後段の取扱い(以下「本件取扱い」という。)が適用されるから、たとえそれがその翌事業年度の業務執行等の役務に対応するものであっても、それは当該事業年度の損金の額に算入される旨主張する。
しかしながら、本件役員報酬等については、その具体的な給付をなすべき原因である役員の職務執行又は従業員の役務提供が当該事業年度の終了の日までになされていないから、その債務が確定しているとは認められず、また、本件役員報酬等は、請求人の財務内容に占める割合などからして、重要性の乏しい費用とは認められないため、本件役員報酬等には本件取扱いの適用がなく、したがって、それを当該事業年度の損金の額に算入することはできない。
平成15年2月20日裁決
(平15.2.20裁決、裁決事例集No.65 343頁)
《裁決書(抄)》
1 事実
(1)事案の概要
本件は、写真製版業及び出版業を営む同族会社である審査請求人(以下「請求人」という。)が、翌事業年度に対応する役員報酬等を事業年度終了の日までに一括して支払ったことについて、当該役員報酬等をいつの事業年度の損金の額に算入すべきであるかが争われた事案である。
(2)審査請求に至る経緯
イ 請求人は、平成9年5月1日から平成10年4月30日まで、平成10年5月1日から平成11年4月30日まで及び平成11年5月1日から平成12年4月30日までの各事業年度(以下、順次「平成10年4月期」、「平成11年4月期」及び「平成12年4月期」といい、これらを併せて「本件各事業年度」という。)の法人税について、青色の確定申告書に別表1の「確定申告」欄のとおり記載して、いずれも法定申告期限までに申告した。
ロ 原処分庁は、これに対し、平成13年5月21日付で、別表1の「更正処分等」欄のとおりの各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)をした。
ハ 請求人は、原処分を不服として、平成13年7月17日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、同年10月15日付で、平成10年4月期及び平成11年4月期の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分に対する異議申立てをいずれも棄却し、平成12年4月期の更正処分に対する異議申立てを却下する異議決定をした。
ニ 請求人は、異議決定を経た後の原処分に不服があるとして、平成13年11月14日に審査請求をした。
(3)関係法令等
イ 法人税法(平成12年法律第97号による改正前のもの。以下同じ。)第22条《各事業年度の所得の金額の計算》
法人税法第22条第3項第2号は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額として、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(以下「費用等」という。)の額を掲げるとともに、その費用等の範囲について、償却費以外の費用の場合には、当該事業年度終了の日までに債務の確定しているものとする旨規定している。
ロ 法人税基本通達2−2−12《債務の確定の判定》(以下「本件債務通達」という。)
本件債務通達は、上記イの「当該事業年度終了の日までに債務の確定しているもの」とは、別に定めるものを除き、当該事業年度終了の日までに、〔1〕当該費用に係る債務が成立していること(以下「債務成立要件」という。)、〔2〕当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること(以下「給付原因発生要件」という。)及び〔3〕その金額を合理的に算定することができるものであること(以下「合理的算定要件」といい、債務成立要件及び給付原因発生要件と併せて「確定債務3要件」という。)の3つの要件をすべて満たしている場合をいう旨定めている。
ハ 法人税基本通達2−2−14《短期の前払費用》(以下「本件前払通達」という。)
本件前払通達は、その前段において、前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていないものをいう。以下同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないとの原則を定めるとともに、その後段において、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める旨の取扱い(以下「後段の取扱い」という。)を定めている。
(4)基礎事実
以下の事実は、請求人及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所が調査したところによっても、その事実が認められる。
イ 役員報酬
(イ)請求人の平成9年4月25日付の臨時株主総会議事録には、役員報酬について、要旨次のとおり決議された旨の記載がある。
A 取締役の平成9年4月26日から平成10年4月25日までの年俸額(以下「9年4月役員報酬」という。)は、Gが18,000,000円、Hが7,750,800円。
B 当該取締役が、上記Aの期間中に辞任するか解任された場合は、原則として、年俸額を日数按分する。
(ロ)請求人の平成10年4月24日付の臨時株主総会議事録には、役員報酬について、要旨次のとおり決議された旨の記載がある。
A 取締役の平成10年4月26日から平成11年4月25日までの年俸額(以下「10年4月役員報酬」という。)は、Gが18,000,000円、Hが7,750,800円。
B 当該取締役が、上記Aの期間中に辞任するか解任された場合は、原則として、年俸額を日数按分する。
(ハ)請求人の平成11年4月23日付の臨時株主総会議事録には、役員報酬について、要旨次のとおり決議された旨の記載がある。
A 取締役の平成11年4月26日から平成12年4月25日までの年俸額(以下「11年4月役員報酬」という。)は、Gが18,000,000円、Hが8,110,800円。
B 当該取締役が、上記Aの期間中に辞任するか解任された場合は、原則として、年俸額を日数按分する。
(ニ)請求人の平成12年4月25日付の臨時株主総会議事録には、役員報酬について、要旨次のとおり決議された旨の記載がある。
A 取締役の平成12年4月26日から平成13年4月25日までの年俸額(以下「12年4月役員報酬」といい、「10年4月役員報酬」及び「11年4月役員報酬」と併せて「本件各役員報酬」という。)は、Gが18,000,000円、Hが8,110,800円。
B 当該取締役が、上記Aの期間中に辞任するか解任された場合は、原則として、年俸額を日数按分する。
(ホ)請求人は、9年4月役員報酬の合計金額25,750,800円、10年4月役員報酬の合計金額25,750,800円、11年4月役員報酬の合計金額26,110,800円及び12年4月役員報酬の合計金額26,110,800円を、それぞれ平成8年5月1日から平成9年4月30日までの事業年度(以下「平成9年4月期」という。)、平成10年4月期、平成11年4月期及び平成12年4月期の損金の額に算入した。
(ヘ)請求人は、上記(ホ)の各金額を、それぞれ平成9年4月25日、平成10年4月25日、平成11年4月25日及び平成12年4月25日に、社会保険料等として控除する金額を差し引いた残額の12分の1を額面金額とする12枚の約束手形を振り出して支給した。
なお、約束手形の決済期日は、各年5月25日以降の各月の25日である。
ロ 従業員給与
(イ)年俸制に関する合意書
請求人が、従業員(以下「本件従業員」という。)との間で締結した平成10年4月24日付、平成11年4月26日付及び平成12年4月25日付の年俸制に関する各合意書(以下「本件各合意書」という。)には、要旨別表2及び次のAないしCのとおりの内容が記載されている(以下、本件各合意書の各日付に従い、本件各合意書記載の年俸を順次「10年4月給料」、「11年4月給料」及び「12年4月給料」といい、これらを併せて「本件各給料」という。)。
A 本件従業員は、請求人に対して、年俸対象期間中において、その労務を誠実に提供しなければならない。ただし、年俸対象期間中に本件従業員が退職する場合は、本件従業員は、退職後は労務を提供しないことになるので、退職月後に決済される予定の月割額を受給する権利はない(本件各合意書の第4条)。
B 請求人は、本件従業員に対し、年俸金額を12で除した額を毎月28日に支払う(本件各合意書の第3条第1項)。
C 請求人は、本件従業員に対して、年俸金額の月割額から控除すべき金額を差し引いた残額を額面金額とする約束手形で支払う(本件各合意書の第3条第2項)。
(ロ)請求人は、10年4月給料の合計金額14,983,200円、11年4月給料の合計金額21,392,400円及び12年4月給料の合計金額18,177,600円を、それぞれ平成10年4月期、平成11年4月期及び平成12年4月期の損金の額に算入した。
(ハ)請求人は、本件各合意書の内容(上記(イ)のB及びC)に応じた約束手形を振り出した。
(ニ)承諾書
本件従業員が請求人に対して提出した平成10年4月24日付、平成11年4月26日付及び平成12年4月25日付の各承諾書(以下「本件各承諾書」という。)には、別表3の内容を承諾する旨の記載がある(以下、本件各承諾書の各日付に従い、本件各承諾書記載の賞与を順次「10年4月賞与」、「11年4月賞与」及び「12年4月賞与」といい、これらを併せて「本件各賞与」という。)。
(ホ)請求人は、10年4月賞与の合計金額1,205,000円、11年4月賞与の合計金額4,540,000円及び12年4月賞与の合計金額4,140,000円を、それぞれ平成10年4月期、平成11年4月期及び平成12年4月期の損金の額に算入した。
なお、請求人は、平成9年4月期において、平成10年4月期に対応する給料及び賞与を損金の額に算入していない。
2 主張
(1)原処分庁の主張
イ 平成12年4月期に係る更正処分
平成12年4月期に係る更正処分は、当該事業年度の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものではないから、当該更正処分に対する審査請求は不適法である。
よって、当該審査請求を却下するとの裁決を求める。
ロ 原処分のうち上記イ以外の各処分
原処分のうち上記イ以外の各処分は、次の理由により適法であるから、当該各処分に係る審査請求をいずれも棄却するとの裁決を求める。
(イ)平成10年4月期及び平成11年4月期に係る各更正処分
本件各役員報酬、本件各給料及び本件各賞与(以下、これらを併せて「本件各役員報酬等」という。)は、以下の理由により、その支払った日の属する事業年度(以下「支払事業年度」という。)の損金の額に算入すべきではなく、その翌事業年度の損金の額に算入すべきである。
A 債務の確定
費用等が法人税法第22条第3項第2号の債務の確定したものとして損金の額に算入すべき金額となるためには、本件債務通達の定める確定債務3要件を満たす必要がある。
また、役員報酬は、役員が株主からの委任を受けて業務を執行したことの対価として支払われるものであり、また、従業員給料及び賞与は、法人と使用人の雇用契約に基づいて提供した労務の対価として支払われるものであるから、役員報酬、従業員給料及び賞与(以下「役員報酬等」という。)は、時の経過に応じて自動的に費用化される性質のものではなく、役員及び従業員が、業務の執行や労務の提供(以下「労務の提供等」という。)をして、その職務等を全うすることによって初めて、役員及び従業員は役員報酬等を法人に請求することができ、法人においては、その時に支払債務が確定することになる。
そうすると、本件各役員報酬等は、その支払事業年度の翌事業年度に対応する費用であり、各支払事業年度終了の日までに、労務の提供等がされていないから、本件債務通達の給付原因発生要件を満たしているとはいえず、請求人の支払債務は確定していないことになる。
したがって、本件各役員報酬等は、各支払事業年度の損金の額に算入すべき金額とはならない。
B 本件前払通達の後段の適用
請求人は、仮に本件各役員報酬等が各支払事業年度の翌事業年度に対応する費用であるとしても、本件前払通達が定める後段の取扱いの要件を充足しているから、本件各役員報酬等を各支払事業年度の損金の額に算入することができる旨主張する。
しかしながら、本件前払通達の後段の取扱いは、前段で定められた前払費用に係る費用収益対応の原則の例外であり、この例外を認める根拠は、「重要性の原則」(企業の会計処理の基準となる原則の1つで、重要性の乏しいものについては本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることを認める旨の原則をいう。以下同じ。)に基づく会計処理を、税務においても認めたものであると解されている。
これを本件についてみると、本件各役員報酬等は、課税所得の計算上重要性が乏しいとは到底いえないから、本件前払通達の後段の取扱いの適用を受けることはできない。
したがって、請求人の主張には理由がない。
(ロ)本件各賦課決定処分
上記(イ)のとおり、平成10年4月期及び平成11年4月期に係る各更正処分は適法であり、また、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、平成10年4月期については同条第1項及び第2項の、平成11年4月期については同条第1項の規定に基づいて行った本件各賦課決定処分は、いずれも適法である。
(2)請求人の主張
原処分は、次の理由により違法であるから、その全部の取消しを求める。
イ 本件各更正処分
本件各役員報酬等は、以下の理由により、その支払事業年度の損金の額に算入すべきである。
(イ)債務の確定
A 法人税法第22条第3項の解釈及び適用
法人税法第22条第3項は、債務の確定という法人税法特有の概念を用いて、企業会計上当該事業年度の費用とされるものであっても、債務の確定がないものについては、法人税法に特段の定めがあるものを除き、法人税法上、損金として取り扱われないことを定めている。
このように、法人税法が、損金の額に算入すべき金額について、債務の確定なる概念を特に要求しているのは、費用を、単に会計的事実によってではなく、何らかの法的な債権債務関係によってとらえようとする立場を採っているからであり、法人が計上した費用が企業会計上は期間に対応していないとしても、必ずしも法人税法上の損金にならないわけではない。
B 本件における「債務の確定」
(A)原処分庁は、役員報酬等が、時の経過に応じて自動的に費用化される性質のものではなく、役員及び従業員が、労務の提供等をして、その職務を全うすることによって初めて、請求することができ、法人の支払義務もその時に確定するものである旨主張する。
(B)確かに、会社と役員及び従業員との間に法律の規定と異なる特段の取決めがない場合には、原処分庁が主張するように取り扱うべきである。
しかしながら、本件については、臨時株主総会議事録、本件各合意書及び本件各承諾書における特段の取決め(以下「本件取決め」という。)があることによって、本件各役員報酬等の支払対象である役員(以下「本件役員」という。)及び本件従業員は、その職務等を全うする前に、上記の特段の取決めを根拠に、本件各役員報酬等の支払を求めることができ、また、請求人は、当該求めに応じて支払う義務を負い、請求人は、実際に当該支払義務に基づいて、本件役員及び本件従業員に対して手形を振り出しているのである。
したがって、請求人の債務は確定したものであるといえる。
C これに対して、原処分庁は、本件各役員報酬等に係る債務について、当該事業年度終了の日までに本件債務通達の給付原因発生要件を満たしているとはいえず、請求人の支払債務は確定していないと主張する。
しかしながら、上記Bの(B)のとおり、本件各役員報酬等は、本件取決めによって、各支払事業年度終了の日までにその債務が確定し、本件債務通達を充足しているにもかかわらず、翌事業年度に対応する費用であるという理由だけでその事実を否定するのは、私的自治という私法取引の大原則を無視した重大な誤りであり、違法なものである。
D 以上のとおりであり、本件各役員報酬等は、それが翌事業年度に対応する費用かどうかに関係なく、各支払事業年度において、本件取決めによる支払義務があるから、上記のとおり法人税法に内在する「法的な債権債務関係」に基づき、各支払事業年度の損金とすべきである。
(ロ)本件前払通達の後段の適用
仮に、本件各役員報酬等が支払事業年度の翌事業年度に対応する費用であるとしても、本件各役員報酬等は、本件前払通達の後段の取扱いが定める費用等に該当するから、各支払事業年度の損金の額に算入すべきである。
A 本件前払通達の後段は、期間対応していない費用であっても、〔1〕支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係る前払費用であること、〔2〕支払った額に相当する金額を継続してその支払事業年度の損金の額に算入していること、この2つの要件を満たすものについては、支払事業年度の損金の額に算入することを認める旨定めているところ、原処分庁は、当該後段の取扱いについては、重要性の原則から逸脱しない限度でその適用が認められるものである旨主張する。
B しかし、本件前払通達の後段の取扱いには、「重要性の乏しいものを対象にする。」あるいは「重要性の高いものは除外する。」などという文言はないのに、課税当局が、恣意的に「重要性の有無」という尺度で適用対象を判断することになると、納税者の税額確定における予測可能性が担保されないことになる。
このような公権力による恣意的な課税は、日本国憲法の要請する租税法律主義に反することとなり、違憲である。
C また、仮に、本件前払通達の後段の取扱いが重要性の原則に基づくものであるとしても、次のとおり、本件各役員報酬等について適用がないとする理由が不明確である。
(A)原処分庁は、請求人が、支払事業年度の翌事業年度に係る前払家賃を、その支払った日の属する各事業年度の損金の額に算入しているにもかかわらず、本件各更正処分の対象とはしていない。
(B)また、原処分庁は、本件各役員報酬等について、役務提供の内容が翌事業年度に対応するものであるからという理由で、その各支払事業年度の損金の額への算入を認めない。
(C)原処分庁が、このように矛盾した取扱いをし、その主張する「重要性の原則」についての具体的な適用基準を明確にしないまま、本件前払通達の後段の取扱いを適用するか否かの判断をしていることは、原処分庁が通達を単なる課税の道具としかとらえていないことを示しており、租税法規の補完である通達の性格に反し、租税法律主義にも違反しているから、違法である。
(ハ)以上のとおり、本件各更正処分は、法人税法第22条第3項及び本件前払通達の解釈から不適法であり、取り消すべきである。
ロ 本件各賦課決定処分
上記イのとおり、本件各更正処分は違法であるから、本件各賦課決定処分は、いずれもその全部を取り消すべきである。
3 判断
(1)平成12年4月期に係る更正処分
平成12年4月期については、別表1のとおり、原処分庁が行った上記の更正処分によっても、請求人が納付すべき税額が増加しないことから、当該更正処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益が認められない。
したがって、当該更正処分に対する審査請求は、不適法であり、却下するのが相当である。
(2)平成10年4月期及び平成11年4月期に係る更正処分
イ 債務の確定
(イ)法人税法第22条第3項第2号は、上記1の(3)のイのとおり、内国法人の各事業年度の損金の額に算入すべき金額について、費用等の額で、かつ、償却費以外の費用の場合には当該事業年度終了の日までに債務の確定しているものとする旨規定している。
そして、この「債務の確定しているもの」に係る判定については、本件債務通達が、上記1の(3)のロのとおり、別に定めるものを除き、当該事業年度終了の日までに確定債務3要件のすべてに該当することをもって、「債務の確定しているもの」と判定する旨定めているところ、当審判所においても、課税の公平を図り、所得計算は可能な限り客観的に覚知し得る事実関係に基づいて行われるべきであるという観点から、本件債務通達の取扱いを相当と認める。
そうすると、費用等を損金の額に算入するためには、当該費用等を損金の額に算入しようとする事業年度終了の日までに、単に債務が成立しているということだけでは足りず、確定債務3要件のうちの他の2要件である給付原因発生要件及び合理的算定要件をも充足することにより、債務が確定することが必要である。
(ロ)本件における債務の確定
A 請求人は、本件各役員報酬等について、法人とその役員及び従業員との間に法律の規定と異なる特段の取決めがない場合には、原処分庁が主張するように取り扱うべきであるが、本件取決めによって、各支払事業年度終了の日までにその債務が確定しているのであるから、当該各支払事業年度の損金に算入すべきである旨主張する。
B 確かに、請求人が主張するように、本件取決めによって、請求人と本件役員及び本件従業員との間において、請求人がいう法的な債務が成立し、本件各役員報酬等が具体的に支払われていることが認められる。
しかしながら、本件各役員報酬等が、法人税法上いずれの事業年度の損金の額に算入されるべきかを判断するに当たっては、本件取決めの有無、内容及び法的性格等を考慮しつつも、あくまでも上記1の(3)のイないしハの法人税に関する法令等の規定に従って、上記(イ)のとおり、法人税法が要件としている債務が確定しているかどうかを検討すべきである。
C そうすると、請求人が本件各役員報酬等をその支払事業年度である本件各事業年度の損金の額に算入するためには、本件各事業年度終了の日までに確定債務3要件すべてを充足しなければならないところ、上記1の(4)のとおり、本件取決めによっても、辞任や退職等によって労務の提供等がされない場合には、役員報酬等の支払義務が生じないことと定められていることからしても、後記Dの金額を除いた本件各役員報酬等は、それぞれ本件各事業年度の翌事業年度において役務の提供等を受けることを具体的な給付をすべき原因として支出されたものであるから、給付原因発生要件を充足しているとは認められない。
したがって、請求人が平成10年4月期及び平成11年4月期の損金の額に算入した本件各役員報酬等の金額は、後記Dの金額を除いて、それぞれ平成10年4月期及び平成11年4月期の各事業年度終了の日までに、当該事業年度の損金の額に算入すべき債務が確定しているものとは認められないので、具体的に役務の提供等を受けた事業年度の損金の額に算入すべきである。
D 他方、10年4月役員報酬及び11年4月役員報酬のうち別表4の1及び2の各「〔2〕」欄に記載された金額は、上記1の(4)のとおり、平成10年4月期及び平成11年4月期に対応する費用等の金額であり、確定債務3要件を充足していると認められることから、それぞれの金額を各事業年度の損金の額に算入することが相当である。
ロ 本件前払通達
(イ)本件前払通達の後段の取扱い
A 前払費用は、企業会計上、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合において、いまだ提供されていない役務に対して支払われる対価で、時間の経過とともに次期以降の費用となるものをいう。また、前払費用のうち、重要性の乏しいものについては、重要性の原則から、これを経過勘定項目として処理しないことができるとされ、その代表的なものは、未経過保険料、未経過利息、前払賃借料等で、時の経過に応じて自動的、合理的に費用化されるものである。
B そして、前払費用は、本来、その支出事業年度の損金に算入されないのが原則であるが、本件前払通達は、上記Aのような企業会計の趣旨から、法人税法第22条第4項に規定する一般に公正妥当と認められる会計処理の基準といえる重要性の原則に沿う限りにおいて、後段の取扱いを例外として適用する旨定めているものと解される。
C そうすると、本件前払通達の後段の取扱いは、重要性の原則の範囲内においてその適用が認められるべきものであり、同原則の範囲内か否かの判断に当たっては、前払費用の金額だけではなく、当該法人の財務内容に占める割合や影響等も含めて総合的に考慮する必要があると考えるべきである。
D これに対して、請求人は、〔1〕本件前払通達の後段の取扱いには「重要性の乏しいものを対象にする。」などの文言はなく、「重要性の有無」で適用対象を判断すると納税者の予測可能性が担保されなくなること、〔2〕本件前払通達の後段の取扱いを具体的な適用基準を明確にしないまま適用するのは、租税法規の補完という通達の性格に反することを理由として、租税法律主義に反する旨主張する。
しかしながら、このような重要性の原則は、企業会計上の明確な原則であり、その適用範囲も合理的に判断できるものであるから、本件前払通達の後段の取扱いが重要性の原則に基づくことやその判断基準が本件前払通達に明示されていないからといって、租税法律主義に反するとはいえない。
(ロ)本件各役員報酬等に対する本件前払通達の後段の取扱いの適用
上記(イ)のCの基準に照らして、本件前払通達の後段の取扱いが、本件各役員報酬等に適用されるか否かについて、以下検討する。
A 請求人は、本件各役員報酬等が、本件前払通達の後段の取扱いの各要件に該当するので、後段の取扱いが適用され、本件各事業年度の損金の額へ算入すべきである旨主張する。
B しかしながら、本件各役員報酬は請求人の業務を執行したことに対する対価として、本件各給料及び本件各賞与は請求人の指揮命令の下に労務を提供したことに対する対価として、それぞれ支払われるものであって、このような人件費は、企業が営利活動を行う上で必要なものであり、企業活動の根幹に係る行為に対する対価であることからすると、会計科目としての重要性を有するといえる。
また、請求人の本件各事業年度の申告所得金額に対する人件費(請求人が決算書に記載している「給与」金額をいい、以下同じ。)の割合は、おおむね314.3ないし853.2%、売上金額に対する人件費の割合は、おおむね52.5ないし56.3%で、本件各事業年度に係る人件費のうちに本件各役員報酬等の金額が占める割合も、おおむね31.0ないし40.7%と、高率かつ可変的であり、金額的にみても重要性を有するといえる。
そうすると、本件各役員報酬等は、時の経過に応じて自動的、合理的に費用化されるような重要性の乏しい費用とは本質的にその性質を異にするものであると認められ、本件各役員報酬等に対して、本件前払通達の後段の取扱いを適用することはできないと解するのが相当である。
したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。
ハ 以上のことから、請求人が平成10年4月期及び平成11年4月期の損金の額に算入した本件各役員報酬等の金額は、上記イの(ロ)のDの金額を除き、いずれも当該事業年度の損金の額に算入されない費用等として取り扱うのが相当である。
なお、9年4月役員報酬の合計金額のうち、別表4の3の「〔3〕」欄に記載された金額は、平成10年4月期に対応する費用等の金額であるから、同事業年度の損金の額に算入すべき費用等として取り扱うのが相当である。
(3)平成10年4月期及び平成11年4月期の所得金額及び税額
イ 平成10年4月期
(イ)請求人の平成10年4月期の所得金額は、別表5の1のとおり、更正処分前の請求人の平成10年4月期の所得金額である別表1の「確定申告」欄の○○○○円に、平成11年4月期に対応する費用等の金額に当たる〔1〕10年4月役員報酬の合計金額のうち別表4の1の「〔3〕」欄の金額25,398,050円、〔2〕10年4月給料の合計金額14,983,200円及び〔3〕10年4月賞与の合計金額1,205,000円を加算し、平成10年4月期に対応する費用等の金額に当たる、9年4月役員報酬の合計金額のうち別表4の3の「〔3〕」欄の金額25,398,050円を減算した、○○○○円となる。
(ロ)そして、上記(イ)の所得金額に対する請求人の納付すべき法人税額(差引合計税額)は、11,583,000円となる。
なお、原処分庁は、法人税法第67条《同族会社の特別税率》の適用に当たり、平成10年4月期に留保した金額から9年4月役員報酬の合計金額を減算していないが、9年4月役員報酬の合計金額のうち平成10年4月期の損金の額に算入される金額25,398,050円は、平成10年4月期の留保金額を算定する上で、同期に留保した金額から控除されるべきである。
(ハ)そうすると、請求人の納付すべき法人税額は、平成10年4月期に係る更正処分の額を下回るから、平成10年4月期に係る更正処分は、その一部を取り消すべきである。
ロ 平成11年4月期
(イ)請求人の平成11年4月期の所得金額は、別表5の2のとおり、更正処分前の請求人の平成11年4月期の所得金額である別表1の「確定申告」欄の○○○○円に、平成12年4月期に対応する費用等の金額に当たる〔1〕11年4月役員報酬の合計金額のうち別表4の2の「〔3〕」欄の金額25,754,096円、〔2〕11年4月給料の合計金額21,392,400円及び〔3〕11年4月賞与の合計金額4,540,000円を加算し、平成11年4月期に対応する費用等の金額に当たる〔4〕10年4月役員報酬の合計金額のうち別表4の1の「〔3〕」欄の金額25,398,050円、〔5〕10年4月給料の合計金額14,983,200円、〔6〕10年4月賞与の合計金額1,205,000円及び〔7〕上記イで認定した所得に基づいて、新たに平成10年4月期の損金の額に算入される事業税の金額1,942,600円を減算した、○○○○円となる。
(ロ)そして、上記(イ)の所得金額に対する請求人の納付すべき法人税額(差引合計税額)は、8,478,300円となる。
(ハ)そうすると、請求人の納付すべき法人税額は平成11年4月期に係る更正処分の額を下回るから、平成11年4月期に係る更正処分はその一部を取り消すべきである。
ハ 本件各賦課決定処分
平成10年4月期及び平成11年4月期に係る更正処分は、上記イの(ハ)及びロの(ハ)のとおり、いずれもその一部を取り消すべきであり、過少申告加算税の賦課決定処分の基礎となる税額は、平成10年4月期が6,400,000円、平成11年4月期が2,940,000円となる。
また、この税額の計算の基礎となった事実については、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。
したがって、請求人の過少申告加算税の額は、平成10年4月期が701,000円、平成11年4月期が294,000円となる。
そうすると、平成10年4月期については、賦課決定処分の額を下回ることから、平成10年4月期の過少申告加算税の賦課決定処分は、その一部を取り消すべきである。
他方、平成11年4月期については、賦課決定処分の額と同額であるから、平成11年4月期の過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。
(4)その他
原処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。
上記、裁決事例より、重要性についての見解を窺うことができるものである。
文責:法人ソリューション部
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。